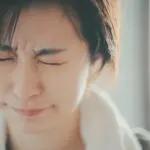突然の腹痛や吐き気、下痢を自己判断で済ませていませんか。その症状、原因の約9割がウイルスとされる急性胃腸炎の可能性があります。(※1)間違った対処は回復を遅らせる原因です。
市販の下痢止めは病原体の排出を妨げ、長いと1か月以上ウイルスを排出し続け、知らぬ間に家族へうつしてしまう危険もあります。この記事では、専門医が危険な症状の見分け方から、回復を早める適切な対処法、大切な家族を守る感染対策まで解説します。
正しい知識で、つらい症状を一日も早く乗り越えましょう。
急性胃腸炎の主な症状4つ
急性胃腸炎は、ウイルスや細菌などが原因で胃や腸の粘膜に急性の炎症が起こる病気です。急性胃腸炎の主な症状には、「腹痛」「下痢」「嘔吐」「発熱」などがあげられます。
①腹痛
急性胃腸炎の腹痛は、腸の炎症による異常な動き(蠕動運動の亢進やけいれん)で起こります。痛みは「キリキリ」「シクシク」「ギューッ」などさまざまで、みぞおちから下腹部まで場所も異なります。
多くは下痢や嘔吐を伴いますが、腹痛は他の病気でも起こるため注意が必要です。特に以下のような場合は、虫垂炎や腸閉塞など緊急性の高い病気の可能性があります。
- 時間とともに痛みが増す
- 冷や汗が出るほどの激痛
- 軽く押しただけで激痛、または離したときに痛む
- 動くと響くように痛む
安静にしても改善しない場合や上記の症状がある場合は、自己判断せず速やかに医療機関を受診してください。
②下痢
下痢は、ウイルスや細菌、毒素を便と一緒に排出する体の防御反応です。急性胃腸炎では水のような便(水様便)が1日に何度も出るのが特徴です。長引くと水分とともに塩分・カリウムなどの電解質も失われ、脱水症状を引き起こします。
特に子どもや高齢者は重症化しやすく、水分と電解質の補給が重要です。便の状態は病気の手がかりになります。
以下のような便が出た場合は、ウイルス性胃腸炎以外の病気も考えられます。
| 便の状態 | 主な疑われる病気 |
| 血便 | 細菌性腸炎、虚血性腸炎 |
| タール便(黒色便) | 胃や十二指腸からの出血 |
| 白色便 | ロタウイルス感染症、胆道疾患 |
| 膿や粘液混じり | 細菌性腸炎、潰瘍性大腸炎など |
市販の下痢止めは病原体の排出を妨げる可能性があり、自己判断での使用は避けましょう。まずは水分補給を優先してください。
③嘔吐
嘔吐は、胃に入った有害物質を外へ出す防御反応で、ウイルス性胃腸炎では初期に多く見られます。特にお子さんは下痢より嘔吐が目立つことがあります。
吐き気が強いときは無理に飲食せず、1〜2時間は休みましょう。水分補給を再開する際は、経口補水液などをスプーン1杯、またはペットボトルのキャップ1杯程度から試すのがポイントです。
数分おきに繰り返し、吐かずに飲めるようなら少しずつ量を増やしていきます。ただし以下のような症状がある場合は、重度の脱水や他の病気の可能性があるため、夜間・休日でもすぐに受診しましょう。
- 嘔吐が頻繁で、全く水分を受け付けない
- 吐いたものに血が混じっている(鮮血、またはコーヒーかすのような黒いもの)
- 緑色の液体(胆汁)を繰り返し吐く
- ぐったりして活気がない、呼びかけへの反応が鈍い
また、吐物の誤嚥を防ぐため、体は横向きで安静にしましょう。
④発熱
急性胃腸炎での発熱は、免疫が病原体と戦っているサインです。体温を上げることで免疫細胞の働きが活発になり、ウイルスや細菌の増殖を抑えます。熱は37.5〜38℃以上まで出ることがあり、寒気や関節痛、頭痛、全身のだるさを伴うこともあります。
高熱が続くと体力消耗や脱水が進みやすく、特に以下の場合はすぐに医療機関を受診しましょう。
- 38.5℃以上の高熱が24時間以上続く
- 水分が取れず尿が極端に少ない
- 呼びかけに反応が鈍い、意識がはっきりしない
- けいれん(ひきつけ)がある
熱がつらいときは、首の付け根や脇の下、足の付け根など、太い血管が通っている場所を冷やすと少し楽になることがあります。ただし、寒気が強いときに冷やしすぎると逆効果になるため、注意しましょう。
食中毒や逆流性食道炎との見分け方
お腹の不調は症状が似ており、「急性胃腸炎か、食中毒か」と迷うことがあります。以下の表に代表的な違いをまとめています。
| 急性胃腸炎(ウイルス性) | 食中毒(細菌性) | 逆流性食道炎 | |
| 主な原因 | ノロウイルス、ロタウイルスなどのウイルス | サルモネラ菌、カンピロバクターなどの細菌やその毒素 | 胃酸や胃内容物の逆流(加齢、食生活・生活習慣など) |
| 症状の出方 | 1〜2日の潜伏期間を経て、比較的ゆるやかに発症 | 原因となる食事の後、数時間〜数日で急激に発症 | ・慢性的 ・食後や横になった時に症状が悪化しやすい |
| 主な症状 | ・嘔吐や下痢、腹痛、発熱が中心 ・冬場に多い | ・激しい腹痛や下痢、嘔吐、血便(原因菌による) ・夏場に多い | 胸やけ、酸っぱいものがこみ上げる(呑酸)、喉の違和感 |
| 感染力 | 強い(人から人へうつる) | 原因菌によるが、人から人にうつることもある | 人から人へはうつらない |
例えば、加熱不十分な鶏肉や卵などを食べた数時間後に急な腹痛や下痢が始まった場合は、食中毒の可能性が高まります。一方、嘔吐や下痢はなく、胸やけや喉のつかえ感が主な症状であれば、逆流性食道炎が考えられます。
ただし、症状だけで確実な判断はできません。強い症状や長引く場合は、医療機関で診断を受けてください。
急性胃腸炎の原因の大多数はウイルス性
急性胃腸炎の大多数は、ノロウイルスやロタウイルスなどによるウイルス感染が原因です。感染力が強く、以下の経路で広がります。
- 接触感染(ドアノブ・手すり)
- 飛沫・塵埃感染(咳・くしゃみ・乾燥した嘔吐物)
- 経口感染(カキなどの汚染食品を加熱不足で摂取)
サルモネラ菌やカンピロバクターなどによる細菌性胃腸炎(食中毒)もあり、血便や激しい腹痛を伴うことが多く、特定の食品が原因です。ウイルス性と細菌性で、以下のような違いがあります。
| 種類 | 主な原因 | 流行時期 | 特徴 |
| ウイルス性 | ノロ、ロタ | 冬(空気が乾燥する時期) | 人から人へ感染しやすく爆発的流行も |
| 細菌性 | サルモネラ、カンピロバクター | 夏(細菌が繁殖しやすい時期) | 血便や強い腹痛、食品が原因に多い |
同じウイルスに感染しても、症状の重さには個人差があります。これは、その人の持つ遺伝的な要因や免疫力の違いが関係するためです。
ウイルス性は特効薬がなく、治療は水分補給が中心です。ロタウイルスのようにワクチンで重症化を防げるものもあり、原因を理解して適切な対処と予防につなげることが大切です。
症状を和らげるための対処法5つ
ご家庭でできる症状を和らげる対処法として、以下の5つを解説します。
①経口補水液で水分補給する
②消化に良い食事(おかゆ・うどん等)を選ぶ
③市販の下痢止め・吐き気止めを安易に使わない
④危険な症状があればすぐ病院へ行く
⑤病院で薬や点滴による治療を受ける
①経口補水液で水分補給する
急性胃腸炎(特にウイルス性)では、嘔吐や下痢で水分とナトリウム・カリウムなどの電解質が失われ、脱水症状を起こす危険があります。電解質不足は、めまい・けいれんなどを招き、重症化すると命に関わります。
治療の基本は水分と電解質を補うことで、水やお茶より「経口補水液」が最適です。一方で、スポーツドリンクは糖分過多で下痢を悪化させることがあります。
水分補給のポイントとしては、まず嘔吐後は30分から1時間ほど休んでから、スプーン1杯程度の少量から再開することが大切です。飲み方は、一度に多く飲まず、5〜10分おきに少しずつこまめに与えるようにしましょう。また、冷たい飲み物よりも常温のものを選ぶと、胃腸への刺激が少なく安心です。
②消化に良い食事(おかゆ・うどん等)を選ぶ
急性胃腸炎の急性期は胃腸を休ませることが最優先で、まずは経口補水液での水分を補給しましょう。食欲が出てきたら、胃腸にやさしいものを少量ずつ再開してください。
食事を再開する際は、以下のステップを参考に、胃腸の様子を見ながらゆっくり進めていきましょう。
- 回復初期:具なしスープ、重湯、すりおろしリンゴなどの流動食
- 回復中期:おかゆ、やわらかいうどん、白身魚、豆腐など
- 回復後期:徐々に通常食へ移行する(消化に悪い食品は避ける)
一方で、揚げ物やカレー、ラーメンなどの脂っこいもの、ごぼう・きのこ・海藻・玄米といった食物繊維の多いものは消化管に負担をかけるので避けましょう。
③市販の下痢止め・吐き気止めを安易に使わない
下痢や嘔吐は、急性胃腸炎や食中毒の原因となるウイルス・細菌・毒素を体外に排出するための防御反応です。この反応を市販薬で無理に抑えると、病原体が腸内に留まり症状が悪化したり、回復が遅れたりする恐れがあります。
特に細菌性食中毒では、毒素が体内に吸収され重症化する危険性があるので、安易に自己判断して使用するのはおすすめできません。
それでも市販薬を使う場合は、安静にして体力を温存することに加えて、経口補水液などでこまめに水分を補給するようにしましょう。
薬の使用は、医師や薬剤師に相談してください。血便や高熱がある場合は市販薬を避け、速やかに受診しましょう。
④危険な症状があればすぐ病院へ行く
多くの急性胃腸炎は、自宅で安静にし水分補給をすれば数日で回復しますが、危険な症状が出た場合は重度の脱水や別の病気の可能性があります。以下のような症状があれば、夜間や休日でも迷わず受診してください。
- 水分が全く摂れない:嘔吐を繰り返し経口補水液も飲めない
- 意識がもうろう:反応が鈍い、呼びかけに答えない
- 脱水がひどい:尿が半日以上出ない、唇が乾燥、乳幼児で涙が出ない
- 激しい腹痛:お腹が硬く張っている、我慢できない痛み
- 便や嘔吐物の異常:血や緑色の液体(胆汁)が混じる
- 高熱が続く:38.5℃以上が下がらない
- その他:けいれん、呼吸困難
特に、乳幼児や高齢者、糖尿病や心臓病などの持病がある方、妊娠中の方は、症状が比較的軽くても早めに医師に相談しましょう。
⑤病院で薬や点滴による治療を受ける
医療機関では症状や経過を確認し、必要に応じて検査を行います。便検査でノロウイルスやロタウイルスなどの原因を特定できれば、適切な治療や感染対策が可能です。治療は主に脱水の改善と症状を和らげる、以下のような対症療法が中心です。
| 治療法 | 内容 |
| 補液療法(点滴) | 水分や電解質を血管内に直接補給し、速やかに脱水を改善 |
| 整腸剤 | 腸内細菌のバランスを整え、消化機能を回復 |
| 制吐剤 | 嘔吐が強く水分補給ができない場合に使用 |
| 解熱剤 | 高熱で体力消耗が激しい場合に処方 |
| 抗生物質 | 細菌感染時のみ使用(ウイルスには無効) |
症状が強いときは、自己判断せずに医師に相談することが大切です。
急性胃腸炎の感染対策3つ
ウイルス・細菌の感染経路を正しく理解し、適切な対策を講じることで、感染の拡大は十分に防ぐことが可能です。急性胃腸炎の感染対策として、以下の3つを解説します。
①家庭内で感染を広げないように消毒する
②手洗いやワクチンで予防する
③感染者と生活の動線を分ける
①家庭内で感染を広げないように消毒する
急性胃腸炎は家庭内での二次感染が起こりやすく、嘔吐物や便の適切な処理と消毒が大切です。嘔吐物や便には数百万~数億個のウイルス・細菌が含まれています。
乾燥するとウイルスが空気中に舞い上がり(塵埃感染)、吸い込むことで感染が広がるため、適切な処理と消毒が重要です。
処理と消毒の基本的な手順は以下のとおりです。
- 換気:窓を開けて空気を入れ替える
- 準備:マスク・手袋・エプロンを着用し、肌の露出を防ぐ
- 拭き取り:ペーパータオルで外側から内側に向けて静かに集める
- 廃棄:汚れたペーパータオルは袋に入れ密封する
- 消毒:塩素系漂白剤(次亜塩素酸ナトリウム)で10分間覆い、その後水拭きする
- 片付け:使用した手袋やマスクを密封して廃棄し、石鹸と流水で手を洗う
蛇口やリモコンなど、感染者が手で触れた可能性のある場所もこまめに拭きましょう。
②手洗いやワクチンで予防する
急性胃腸炎の感染を未然に防ぐ基本は、病原体を体内に入れないことです。病原体は目に見えないため、こまめな手洗いを習慣にしましょう。
手洗いのタイミングは、トイレの後、調理や食事の前、おむつ交換後、外出後などです。
手洗いの手順は、まず流水で手を濡らして汚れを落とし、その後石鹸をよく泡立てて、手のひら、手の甲、指の間、爪のまわり、親指の付け根、手首までを30秒以上かけて丁寧に洗います。次に流水で石鹸の泡を完全に洗い流し、最後に清潔なタオルまたはペーパーで水気をしっかり拭き取ります。タオルを共用しないことも大切です。
また、ウイルスの中にはワクチンで重症化を予防できるものがあります。乳幼児の重い胃腸炎の主な原因となるロタウイルスには、定期接種となっているワクチンがあります。
実際に、新潟県新発田市で行われた研究では、ロタウイルスワクチンの普及によって、目に見える変化がありました。2020年以降、ワクチン接種率が94%まで向上した結果、急性胃腸炎で入院する子どもの数が明らかに減ったと報告されています。(※2)
お子さんがいる場合は、手洗いとあわせて、ロタウイルスワクチンの接種で子どもの健康を守りましょう。
③人に移る期間を把握する
急性胃腸炎は症状がなくなっても、しばらくの間は便から病原体が排出され続けます。この間は本人に自覚がなくても、家族や周囲へ感染を広げる可能性があります。
回復後1週間程度は特に注意が必要で、ノロウイルスでは1か月以上続くこともあります。期間中は以下を徹底しましょう。
- トイレ後は石鹸と流水で入念に手洗い
- タオルや食器、歯ブラシは家族と共有しない
- 入浴は可能であれば最後に行う
- 調理や食品に直接触れる作業を避ける
- トイレや共用部分は使用後に消毒する
上記のような対策が、家庭や職場での二次感染防止につながります。
回復までの過ごし方で気をつけるポイント2つ
症状が軽くなったからといって、胃腸が完全に回復したわけではありません。消化機能が追いつかずに症状がぶり返したり、回復が長引いたりすることがあります。
「①仕事や学校を休む期間と復帰の目安を守る」「②仕事を休めない場合は感染拡大を防ぐ工夫をする」の2点を解説します。
①仕事や学校を休む期間と復帰の目安を守る
復帰時期は体調だけでなく、周囲への感染防止の観点からも重要です。ノロウイルスなどによる急性胃腸炎は「学校保健安全法」で予防すべき感染症に指定されており「急性症状から回復し全身状態が良好であれば登校可」とされています。(※3)
一般的には、嘔吐・下痢が完全に治まり、普段通りの食事ができる状態になってから、さらに24〜48時間は自宅で安静にします。
いつから仕事や学校に復帰できるかは、ご自身の体調だけでなく、周りの人へ感染を広げないためにも重要な問題です。仕事や学校に復帰できるかは、以下を参考にしてみてください。
- 嘔吐が完全に止まっているか
- 下痢がおさまり、普段に近い固さの便に戻っているか
- 食欲が戻り、消化の良い固形物が食べられるか
- 体のだるさや気分の悪さがなく、普段通りに動けるか
- 職場や学校の規定がある場合、医師から復帰の許可を得ているか
②仕事を休めない場合は感染拡大を防ぐ工夫をする
やむを得ず仕事を休めない場合でも、急性胃腸炎の感染力は強いため、職場での感染拡大を防ぐための対策を怠ってはいけません。ご自身と大切な同僚を守るために、以下の対策を意識しましょう。
- 石鹸と流水による手洗いを徹底する
- 不織布マスクを常に正しく着用する
- 共用部分をこまめに消毒する
- タオルの共用は避ける
- トイレの使用方法に注意する
- 食品の取り扱いや配膳は控える
特に調理、介護、保育など感染リスクの高い職種では、職場に報告し、医師や上司の指示に従うことが必要です。
まとめ
突然の嘔吐や下痢は、体に入った病原菌を外に出そうとする体の防御反応です。治療で重要なのは、脱水を防ぐためのこまめな水分補給と、胃腸を休ませるために安静にすることです。
自己判断で市販の下痢止めを使うと、かえって回復を遅らせることもあるため注意しましょう。我慢できないほどの激しい痛みや、全く水分を受け付けないような危険サインが見られる場合は、医療機関を受診してください。
つらい症状で不安になると思いますが、正しい知識で適切に対処すれば、回復に向かいます。まずは焦らず、ご自身の体をゆっくりと休ませましょう。