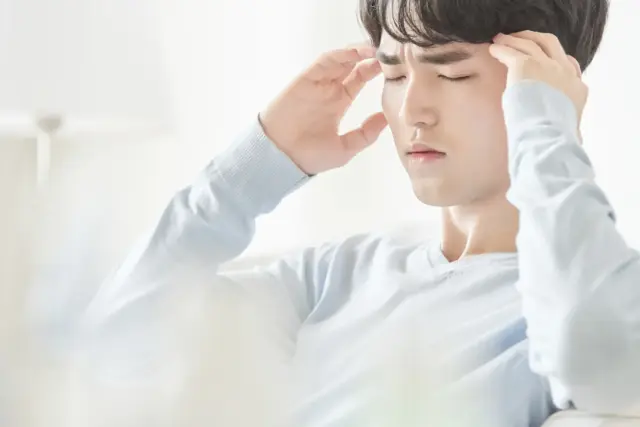目次
はじめに
コロナ禍以降、電車に乗る時や人混みの中にいる時はマスクをつけることが習慣化したという人もいるのではないか。マスクのお蔭で感染症の流行が抑えられているというメリットもあるが、一方で、東京女子医科大学脳神経外科頭痛外来の清水俊彦客員教授は、「マスクが頭痛に影響を与えている」と指摘する。その理由、対策などについて話を聞いた。
Q1.マスクで頭痛を起こす人もいるのでしょうか?
マスクが手放せなかったコロナ禍では、頭痛の患者さん、特に片頭痛の患者さんが増えました。私は「マスク頭痛」と呼んでいます。
Q2.原因はなんですか?
まずは、血液中の二酸化炭素濃度の上昇です。綿密な化学繊維でできている不織布マスクは飛沫抑制効果に優れているのですが、言い換えれば通気性が悪い。しかも、マスクが顔にフィットするよう隙間なく装着する。すると、自分が吐いた呼気がマスク内に溜まります。呼気には二酸化炭素が含まれているので、それをまた吸うことになります。二酸化炭素は非常に強力な脳血管拡張因子であり、血液中の二酸化炭素濃度の上昇によって、脳の血管が拡張。血管を取り囲むように分布しセンサーの役目をしている三叉神経を刺激し、脳が痛みとして認識するのです。三叉神経が刺激されて痛みが起こるメカニズムは片頭痛と同様で、結果、片頭痛の患者さんが増えているのです。
Q3.ほかにも原因がありますか?
どなたでもそうなんじゃないかと思いますが、マスクをつけている間は緊張状態にある。自宅に帰り、マスクを外すと、ホッとし、ようやくリラックスできる。その時、副交感神経が一気に優位になって、脳の血管が拡張し、三叉神経を刺激して頭痛が起こる。片頭痛持ちの患者さんに、この傾向がみられる。
片頭痛の患者さんでは、マスクに弱いという点もあります。アロディニア(異痛症)といって、片頭痛の患者さんはちょっとした刺激で痛みを感じる人が少なくない。三叉神経が敏感という特徴に加え、片頭痛が起きる予兆としてアロディニアがあるのですが、マスクやマスクの紐が皮膚に当たり、ピリピリ痛んだりするのです。アロディニアがみられる場合、放置すると、強い片頭痛を起こす可能性があります。なお、片頭痛の予防手段に「サングラスをかける」があります。しかし、片頭痛の患者さんには、アロディニアでサングラスをかけられない人も珍しくありません。
Q4.マスクで耳が引っ張られて頭痛を感じることがあります。
普段頭痛持ちでない人から、同様の訴えを聞きます。筋肉の緊張が原因ですね。マスクをつけていると、表情をあまり動かしませんし、口も大きく開けませんから、顔面の筋肉の緊張が継続し、それによる緊張型頭痛を起こす人もいます。在宅勤務で、活動量が一気に減り、同じ姿勢で過ごすことが増えるのも、緊張型頭痛に関係しています。
Q5.マスク頭痛に対して、どういった対策が有効でしょうか?

インフルエンザの流行期などマスクを手放せないという場合の対策として、周囲に人がいない、または人がいても十分なソーシャルディスタンスを取れている時にはマスクを外し、ゆっくりと深呼吸をして、二酸化炭素の血液中の濃度を下げる。風通しのいい屋外では、マスクを外す。
ブドウ糖を含む食品を少量取るのもお勧めです。ブドウ糖には、拡張した血管を収縮させる作用があります。二酸化炭素によって拡張した血管を、ブドウ糖で逆に縮めるのです。ブドウ糖を含む食品には、飴、ドライフルーツ、果物などがあります。取りすぎると肥満の原因になりますので、あくまでも少量で。また、チョコレートには注意。チョコレートもブドウ糖を含みますが、チョコレートの成分であるチラミンが脳血管拡張を助長し、片頭痛を引き起こす可能性があるので、これは避けるようにしてください。
冬は空気が乾燥します。乾燥対策として、マスクを浴室に一晩吊るし、湿らせるのもいいですよ。乾いた空気を吸って喉が乾燥すると、口腔内に分布する三叉神経が刺激されるからです。湿気を吸ったマスクでは、息も湿り気を帯びるので、口腔内に分布する三叉神経の刺激が弱まります。
Q6.頭痛の適切な治療を受けることも大事ですよね?
もちろんです。片頭痛は慢性頭痛の代表例で、市販の鎮痛薬では十分に対処できないこともあります。痛いからとその都度薬を飲んでいると、薬物の使用過多による頭痛(薬物乱用頭痛)を招く恐れもあります。自己判断で対処せず、頭痛に精通している医師の元で治療を受けるべきです。
改めて片頭痛についてお話ししますと、脳の血管が急激に拡張し、周囲の三叉神経が刺激され、刺激で発生する炎症物質がさらに血管を拡張しているのが片頭痛です。血管の拡張には、心身のストレスからの解放、寝過ぎ、寝不足、空腹、疲労、光や音の強い刺激など様々な誘因があります。
片頭痛を長期間抱えていると、三叉神経終末から大脳に繰り返し刺激情報が伝播する結果、脳が少しの刺激でも興奮しやすくなります。結果、立っていられないほどのめまい、頭の中で鳴り響くような耳鳴り(頭鳴)、頭重感、不眠といった症状が出てきます。
私は頭痛患者さんを診る際、脳の興奮状態を確認します。片頭痛の人の多くは、脳が過剰な興奮状態にあります。脳が興奮状態にある時は、片頭痛の治療薬の第一選択肢、トリプタン製剤だけでは片頭痛を抑えられません。そこで、バルプロ酸ナトリウムという片頭痛予防薬をガイドラインの推奨量の4分の1から半量処方します(妊婦など禁忌以外の人に対して)。脳波測定で脳の興奮が鎮まっていることを確認すれば、バルプロ酸はやめて、痛みがある場合にだけトリプタン製剤を用いるよう、患者さんに指導します。
Q7.バルプロ酸の量をガイドラインより少なくするのはどうしてでしょうか?
ガイドラインで推奨されている量の根拠となっているのが、欧米の研究結果だからです。臨床上、ガイドラインと同じ量では日本人には多すぎると感じています。薬である以上、副作用がつきもので、バルプロ酸は眠気や食欲増進の副作用があります。量を4分の1から半量にすることで、生活に影響が出にくくなります。
Q8.2021年、片頭痛の新薬が相次いで発売されました。
片頭痛が始まる時、三叉神経からCGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド)というタンパク質が脳血管周囲に三叉神経終末から異常に放出されることがわかっています。CGRPは片頭痛の痛みの主な原因とされています。
2021年、CGRPを無力化する2種類の薬剤、CGRPの受容体をブロックする1種類の薬が相次いで承認、発売されました。従来の薬が効かなかった患者さんに効果があるのではないかと、注目されています。
ただ、いずれも注射薬で、非常に高価。確かに、従来薬を用いた適切な治療を行なっても効果が見られなかった患者さんには新たな選択肢が登場し、喜ばしいことですが、多くの患者さんを診てきた観点から、頭痛で悩んでいる患者さんの中には、不幸にして的確な治療を受けられていなかった方も少なくありません。
脳波の確認、バルプロ酸の処方、または片頭痛には帯状疱疹ウイルスが関係しているものもありますから、その場合は帯状疱疹ワクチンを接種するなど。これらで頭痛が改善するかもしれません。治療の見直しを強くお勧めします。