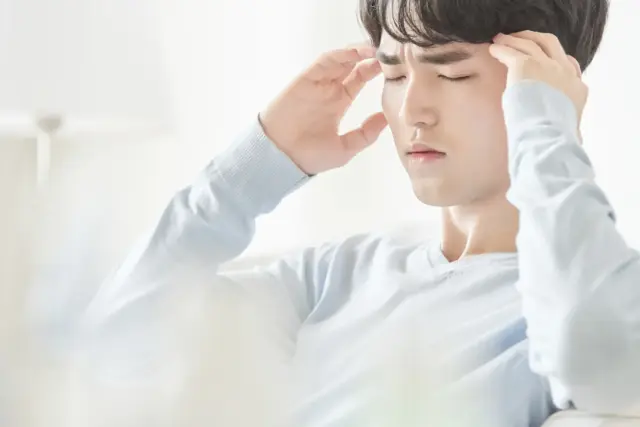目次
はじめに
帯状疱疹はウイルスの活性を抑える帯状疱疹ワクチン接種で発症や重症化のリスクを下げることができる。そして帯状疱疹ワクチンは、つらい片頭痛や群発頭痛の発症予防にもなると指摘するのが、東京女子医大脳神経外科頭痛外来客員教授の清水俊彦医師だ。話を聞いた。
Q1.帯状疱疹とはどういう病気でしょうか?
帯状疱疹は、水疱瘡(水痘)のウイルスによって起こる病気です。水疱瘡はみなさんよくご存知の通り、大抵は小児期に発症します。水疱瘡そのものは治っても、水疱瘡ウイルス(水痘ウイルス)はそのまま潜在的に、主に神経節という体内の神経のサテライトに帯状疱疹ウイルスとして残ります。帯状疱疹ウイルスは普段は免疫によって活動が抑えられていますが、加齢や疲労などなんらかの原因で免疫力が低下すると、活性化し、帯状疱疹を発症します。
症状としては、体の左右どちらかの神経に沿って、痛みを伴う皮疹ができます。50歳以上でリスクが高くなり、80歳までに3人に1人が発症するといわれています。
Q2.帯状疱疹ウイルスと頭痛はなぜ関係しているのでしょうか?
頭痛には、脳には異常がない一次性頭痛と、脳に異常があったり、そのほかの原因で生じる二次性頭痛があります。一次性頭痛には、ストレスや長時間同じ姿勢を取ることによる首や肩の筋肉の凝りなどで発症する緊張型頭痛、頭の片側にズキンズキンとした拍動性の痛みを感じる片頭痛、春先や秋口など季節の変わり目に連日連夜、片目の奥を火箸でえぐられるような激痛が続く群発頭痛などがあり、これらのうち片頭痛や群発頭痛と帯状疱疹の関係に私が着目したのは2007年頃になります。
群発頭痛の患者さんに予防治療として、神経や血管の炎症を抑える副腎皮質ホルモン剤を投与すると、群発頭痛が起こっている側の三叉神経領域に帯状疱疹を発症するケースが多々あったのです。副腎皮質ホルモン剤は免疫力を下げる効果があります。前述の通り、帯状疱疹は免疫力が低下したときに、神経節に潜在する帯状疱疹ウイルスが活性化して発症します。このことから、三叉神経に潜在する帯状疱疹ウイルスが、群発頭痛に関係しているのではないかと考えたのです。
そこで、群発頭痛の患者さん27人の帯状疱疹ウイルスの抗体価を測定してみました。すると、群発頭痛の発作期間に入ると、3分の2以上で抗体価が上昇、継続していたのです。これは、群発頭痛の発作時に帯状疱疹ウイルスが活性化していることを意味します。
さらに、群発頭痛の発作が起こった時に帯状疱疹の治療で用いる抗ウイルス薬を5日間投与した場合の反応も見ました。すると、群発頭痛の発作期間が短くなったり、頭痛が軽減したのです。
帯状疱疹ウイルスは、ワクチン接種によって増殖を抑制できます。この帯状疱疹ワクチンを打った群発頭痛の患者さん94人を追跡調査した結果では、36カ月後、71%の人が「改善した」、つまり発作が起きていないと回答。54カ月後には99%の人に何らかの改善が見られました。
Q3.帯状疱疹ウイルスは、片頭痛にも関係しているということですが・・・。

重症のひどい片頭痛の患者さんは、発作頭痛が起こる前に、片頭痛が起こる側の頭皮や顔面にピリピリした違和感を覚えることがよくあります。これは異痛症(アロディニア)といわれるもので、顔面や頭皮、脳血管周囲に分布している知覚神経である三叉神経が過敏になることが原因です。片頭痛の患者さんには、発作が起こる前触れとして、「メガネの縁が気になる」「くしで髪の毛をとくと頭皮が痛い」「コンタクトに違和感がある」などと訴える方もいらっしゃいますが、これらも三叉神経の過敏状態が関係していると考えられます。
そして、これらアロディニアが起こっている片頭痛の患者さんの帯状疱疹ウイルスの抗体価を調べると、頭痛発作が起こるタイミングで帯状疱疹ウイルスの抗体価も上昇傾向になっていたのです。群発頭痛と同様に、免疫力が低下し、三叉神経に潜在する帯状疱疹ウイルスが活性化してアロディニアを発症。その情報が脳血管周囲の三叉神経に伝わり、神経炎症タンパクであるCGRP(カリシトニン遺伝子関連ペプチド)やサブスタンスPが放出され、ひどい片頭痛発作が出現している可能性が示唆されたのです。これは、当時の私達の研究グループが厚労省の科研費で調査し、学会で発表しています。
Q4.海外でも調査結果が発表されていると聞きました。
帯状疱疹ウイルスと、片頭痛や群発頭痛などとの関連について、近年調査結果が欧米でもいくつか報告されています。
米国神経学会は、2014年12月17日付Neurology誌オンライン版で、片頭痛患者さんの大規模調査の検索から、片頭痛に罹患している人は帯状疱疹ウイルスが原因とされている顔面神経麻痺を発症する率が、片頭痛に罹患していない人と比べて3倍高いと報告しています。因果関係は明言されていませんが、双方の疾患には何か共通する素因もしくは増悪因子が存在しているかもしれないと触れられています。
この前の10月8日付Stroke誌オンライン版では、顔面の三叉神経領域に帯状疱疹を発症した人は、罹患後1年以内に脳卒中を罹患する率が高いと報告されています。帯状疱疹ウイルスは、脳血管内で増殖可能な唯一のウイルスで、大きな脳血管周囲に網の目状に分布している三叉神経から脳血管壁にウイルスが侵入し、損傷を来している可能性が高いという推論が掲載されています。
Q5.帯状疱疹と脳の病気が関係しているとは驚きです。清水先生も、そういった症例を診察したことがあるとか・・・。
帯状疱疹と脳血管障害との関連をうかがわせる症例にいくつも遭遇しています。
ある40歳代女性は、もともと片頭痛持ちで、月に4回ほど、片頭痛の治療薬であるトリプタン製剤で対処していました。あるとき、左三叉神経第二枝領域に帯状疱疹を発症。その1週間ほど前から、アロディニアとともに片頭痛発作も悪化しました。帯状疱疹は抗ウイルス薬で改善したのですが、3カ月後に左後頭部(帯状疱疹を発症した側と同じ側)に刺すような神経痛が生じ、1週間ほど続きました。その後、持続性の痛みに変化したため、頭部MRI検査をしたところ、左椎骨動脈に脳血管解離と脳動脈瘤の形成が認められました。幸いなことに、この女性は経過観察で自然修復、治癒しました。
また、別の50代女性は、頭部に帯状疱疹を発症した2週間経過後に痛みが再発、最初の頭部MRI検査で異常がなく、抗ウイルス薬で帯状疱疹は治りました。しかし2度目は抗ウイルス薬では治らず、再度MRI検査を行うと、脳の椎骨動脈解離を起こしていたのです。即座に治療を行い、命に別状はありませんでした。治療後、帯状疱疹ウイルスの抗体価を調べると、やはり数値は高く、帯状疱疹ウイルスの再活性化を示唆されたのです。
Q7.帯状疱疹ワクチンは接種した方がいいですか?
近年、帯状疱疹ウイルスがさまざまな病気のリスクを上昇することが分かってきています。すでに挙げた片頭痛や群発頭痛、脳血管障害、顔面神経麻痺や片側性眼瞼けいれんのほか、アルツハイマー型認知症、多発性硬化症などです。アルツハイマー型認知症は悪化や進行を遅延させる抗体治療薬が本邦および欧米でも承認されましたが、根治的治療薬はありませんし、脳血管障害は、治療が遅れれば命に関わります。
そもそも帯状疱疹そのものがつらい病気ですし、合併症として帯状疱疹後神経痛もあります。帯状疱疹後神経痛は、帯状疱疹の皮疹が消えて帯状疱疹が治った後も痛みが続くもので、衣服がすれるだけで痛いということも。予防策として、帯状疱疹ワクチン接種をお勧めします。少なくとも、片頭痛や群発頭痛を何度も起こしている人は、帯状疱疹への免疫抗体を測定し、有効な値でなければ帯状疱疹ワクチンを検討してみてはどうでしょうか。
なお、帯状疱疹ワクチンは50歳以上を対象に任意接種でしたが、2025年4月から原則65歳以上を対象に、公費助成のある定期接種となります。2025年度から2029年度までの5年間は経過措置として、その年度内に70、75、80、85、90、95、100歳となる方も対象となります。詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。
また、もし49歳以下で関心がある場合は、まずは医師に相談してみてください。特に小児期に水痘に罹患せずに、水痘ワクチンで免疫を獲得した方は、注意が必要です。なぜならば、ワクチン接種による受動免疫は、あまり長くは持続せず、個々の症例にもよりますが、20年くらいが限界ではないかとか考えています。水痘に罹患した場合でも40〜50年くらいが限界でしょう。
Q8.先日、清水先生が登場している新聞記事で、「冬の朝の頭痛は、血圧急上昇のリスクが考えられる」という内容が紹介されていました。詳しく教えてください。
寒い季節、それも朝には血圧が思っている以上に上昇している可能性があります。その理由は次の通りです。
まず、手足の末梢血管が収縮し、収縮期血圧が通常よりも上昇しがちになる。
次に、年末年始で暴飲暴食が増えるシーズンのため、塩分摂取量が増えがちになる。
加えて、朝、目覚めた直後に血圧が急上昇する「早朝高血圧(モーニングサージ)」という問題がある。これは、夜と朝の収縮期血圧の差が55以上あることで、日本人約2万1000人を対象にした研究では、朝だけ血圧が高い人は、日中正常血圧でも、脳卒中や心筋梗塞のリスクが2・47倍高いとの報告があります。
普段から血圧測定を日課にしている人なら別ですが、多くの方はそうではないのでは?血圧上昇を疑う症状の一つに、頭痛があるのです。血圧が急上昇すると、脳血流量が増加し脳がむくみがちになり(脳浮腫)、脳血管周囲の三叉神経が刺激されて、頭痛や頭重感が生じます。一般的に血圧上昇による頭痛は、血圧が高めの人に見られるのですが、もともと片頭痛がある人は、そうでない人より三叉神経が過敏になっているので、血圧がそこまで高くない人でも、頭痛が悪化するのです。
冬、特に寒い朝、頭の片側がズキンズキンと脈打つような痛みがあれば、早朝血圧の上昇を疑い、測定をした方がいいでしょう。
私はこういった患者さんには、頭痛緩和に加えて血圧低下の効果もある降圧薬を処方しています。具体的には、β遮断薬やアンジオテンシン受容体拮抗薬です。β遮断薬は、欧米の研究で脳神経細胞の異常な興奮を抑制する効果があり、片頭痛発作にも効くことが判明しています。ただ、片頭痛発作時の頓服薬であるトリプタン製剤のうち、リザトリプタンとは併用できません。その点、アンジオテンシン受容体拮抗薬はすべてのトリプタン製剤や、近年処方可能となったラスミジタンという新しい片頭痛発作の頓服薬とも併用可能で、脳血管安定作用や脳血管保護作用があり、片頭痛予防効果も欧米では報告されています。片頭痛持ちの方は、冬季の早朝高血圧をも、いち早く痛みの危険信号として察知する、それくらい敏感な脳の持ち主であると言っても過言ではないでしょう。