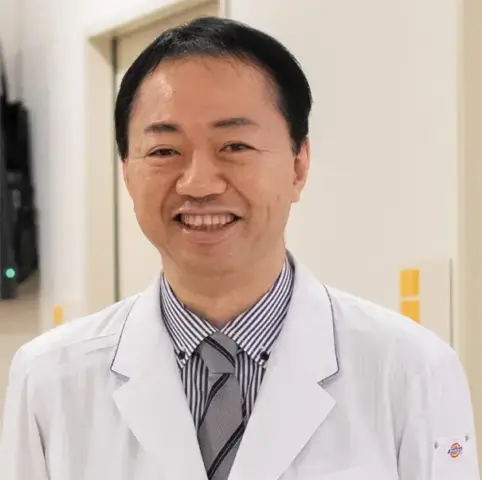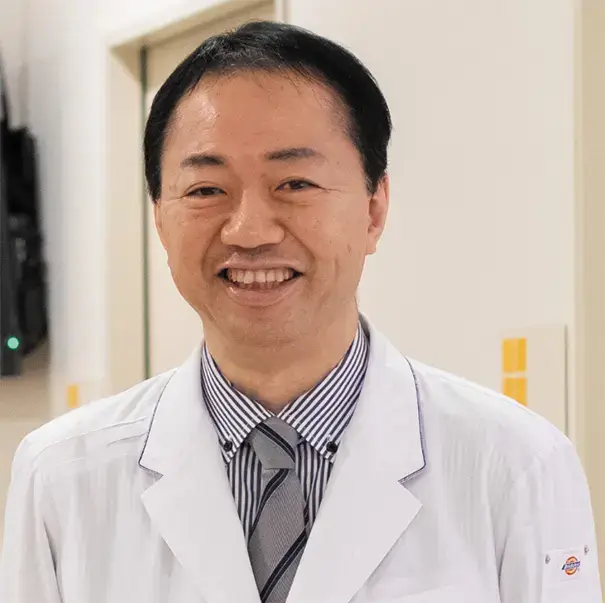目次
はじめに
環境省の熱中症予防情報サイトによると、熱中症を引き起こす条件は、「環境」「からだ」「行動」とのこと。
具体的には、「環境」は「気温が高い」「湿度が高い」「風が弱い」「急に暑くなった」など、「からだ」は「高齢者や乳幼児、「肥満」「脱水状態「体調不良」など、行動は「屋外作業」「激しい運動」など。これら3つが重なると、熱中症を引き起こす可能性がある。
熱中症対策でよく言われることのひとつが「水分摂取をきちんと行う」。神奈川県済生会横浜市東部病院患者支援センター長・栄養部担当部長の谷口英喜医師に聞いた。
熱中症とはどういった状態を指すのでしょうか?
広辞苑には、熱中症について「暑さ(高温)、蒸し暑さ(多湿)が原因で起こる体調不良」と書かれています。「食中毒」の「中」と、「熱中症」の「中」は同じ。「食にあたる(=食中毒)」、「暑さ(熱)にあたる(=熱中症)」なのです。
熱中症を起こす機序を教えてください。

前述の通り、私たちの体には、体温を調整する機能が備わっています。暑さなどで体温が上昇すると、汗による放熱と、皮膚からの放熱で、体温が上がりすぎないようにコントロールします。この体温コントロールができなくなり、熱中症に至ります。
熱中症ではこの体温コントロール不良だけが着目されますが、その前段階として熱中症へつながる大きな原因があります。最初に暑い・蒸し暑いという「暑熱環境」があり、そこから大汗をかき水分が不足する「脱水症状」となるのです。
つまり熱中症は、暑い・蒸し暑い環境で起こる体調不良で、体調不良の症状は「脱水症」、それから引き起こされる体温コントロール不良による「異常高体温」になります。
どういった症状が起こるのでしょうか?
脱水症と異常高体温の影響を受けやすい3つの臓器があります。それは、脳、消化器、筋肉。いずれも水分が必要とされる臓器になります。熱中症では、これらの臓器に関連する症状が一度期に出現します。
脳がダメージを受けるので、症状としてはめまい、立ちくらみ、集中力・記憶力の低下、頭痛、意識消失、けいれん。消化器の症状では、食欲低下、悪心、嘔吐、下痢、便秘。筋肉の症状では、筋肉痛、しびれ、まひ、こむら返りです。
暑い・蒸し暑いといった環境で、脳、消化器、筋肉の3つの臓器に関連する症状が重なってあらわれたら、熱中症を疑い、速やかに対策を講じることが肝心です。
自己対策でいいのでしょうか? それとも救急車を呼ばなくてはなりませんか?
熱中症の重症度は、Ⅰ度〜Ⅲ度(昨年からⅣ度も追加)に別れています。数字が大きいほど、重症になります。
めまい、立ちくらみ、生あくび、大量の発汗、こむら返りがあり、意識障害はない場合(Ⅰ度)、通常は現場で対応可能です。安静にし、体を冷やし、水とナトリウムが主成分の経口補水液を補給します。
頭痛、吐き気、倦怠感、虚脱感があり、集中力や判断力が低下した状態(Ⅱ度)なら、医療機関での診察が必要です。経口での水分・ナトリウムの補給が困難なときは、点滴を行います。
意識障害や痙攣発作があれば、入院・集中治療が必要なⅢ度。病院へ辿り着いていない場合は、救急車を呼んでください。(IV度はIII度の中で、特別な治療が必要な患者)
熱中症予防はどのようにすればいいですか?
熱中症は予防できる病気です。熱中症で倒れて救急搬送された場合、状況によっては、ダメになった細胞は元に戻らない。予防が非常に重要なのです。
体温コントロールに至る前段階をブロックする。暑い・蒸し暑いの暑熱環境、そして大汗で水分不足になる脱水症です。
暑熱環境は、熱中症指数や暑さ指数が環境省の熱中症予防情報サイトで発表されているので、それを見て行動するようにしましょう。
脱水症は、水分補給に加え、規則正しい食生活が肝心。水分補給は1日8回を目安にこまめに水分を取る。食事から入る水分も大切で、1食抜けば、それから入ってくるはずだった水分が取れないことになります。特に、水分が多く含まれる野菜や果物などは、夏場の脱水症状対策に適しています。野菜や果物にはビタミンC、ビタミンB群という熱中症予防に効果的な栄養素が含まれているのも、お勧めしたい理由です。
熱中症対策への水分や栄養摂取のポイントとは?
1日に必要な水分摂取用の約半分は食事から取れるので、1日3食きちんと摂取する。
水分はこまめに取る。一気飲みは、体内に吸収されても体外へすぐに排出されます。
大量に発汗したときは、水分と同時に塩分(ナトリウム)を取る。ミネラル、糖の補給も行えばなおいいです。