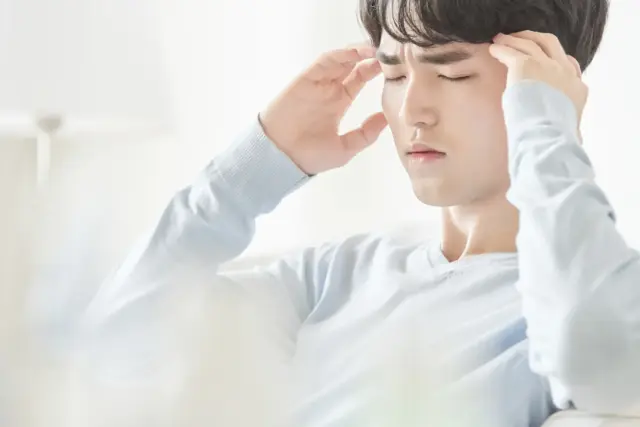雨が降る日はどことなく体調が悪い。古傷が痛む。気分が落ち込みがちになる……。こんな経験はないだろうか?
近年、気象と病気を関連付けて考える「気象病」が注目を集めている。どこの医療機関を回っても不調の原因が解明されなかった人が、実は気象病だった、というケースもある。「ゲリラ豪雨」「大型台風」「温暖化」といった世界的な異常気象がみられるが、特に気圧の変動による台風や梅雨が多い季節は、気象の影響を受けて体調を崩しやすい。
脳神経外科専門医、脳卒中専門医、そして気象予報士の資格も持つ公立福生病院脳神経外科診療部部長の福永篤志先生に気象病についてお話を伺った。
目次
Q福永先生が「気象病」に関心を抱くようになったきっかけを教えてください。
私が脳神経外科医として駆け出しの頃のことです。2月の非常に寒い日、クモ膜下出血で倒れた40代半ばの男性が、私が勤務していた病院へ救急搬送されてきました。幸いなことに命は助かりましたが、後遺症が残ってしまいました。
男性の家族に話を伺うと、その男性は寒い中、屋外で車を冷水で洗っていた時に、クモ膜下出血を起こしたそうです。普段から健康に留意し、健康診断の数値もすべて正常範囲の男性でした。こういう人でもクモ膜下出血を起こすのか、という驚きとともに、寒さと血圧の関係に関心を抱いたのです。それからさまざまな論文を読み、気象と病気の関係を調べるようになりました。
Q「気象病」とは、どういう病気ですか?

気象の変化、たとえば気圧配置や気温差などで起こる不調の総称です。季節の変わり目、梅雨の時期などに気象病に見舞われる方が多いです。普段は健康な人でも、「春や秋の気温の変化が激しい時は調子が悪くなる」といったケースもあります。
よくある病気としては、頭痛、関節痛、関節リウマチ、メニエール病、緑内障、気管支喘息、肺炎、心筋梗塞、脳卒中、うつ病などの精神疾患、てんかん、急性虫垂炎などがあります。
また、これらの一般的な気象病に加え、夏の暑い時期にリスクが増す病気など、その季節に関連した病気も、私は気象病と捉え、患者さんに注意を促しています。
Qなぜ気象の変化で不調が生じるのですか?
自律神経のバランスが崩れることが挙げられます。気圧が変動したり気温差が激しかったりすると、人間の身体はストレスを感じます。すると、それに対応するために自律神経が活性化します。
自律神経には交感神経と副交感神経があり、交感神経は日中など身体を活発に動かしている時に優位に立つ自律神経であり、副交感神経は夜、身体がリラックスしている時に優位に立つ自律神経です。
交感神経と副交感神経がうまくバランスを取ることで私たちは健康的に過ごせるのですが、どちらかが過度に優位になったり、本来は交感神経(または副交感神経)が優位な時間帯に、副交感神経(または交感神経)が優位になったりすると、頭痛、疲労感、うつ状態、眠気、不眠などさまざまな不調が生じ、時に深刻な病気を発症することがあるのです。
Q気象や気温はどれくらいの差があると「気象病」が生じるのでしょうか?
感受性に差があるので、少しの差でも不調を感じる人もいれば、大きな差があるのに、あまり不調を感じない人もいます。
日本で初めて「天気痛外来」を開設し、気圧や気温の差が関係する不調を「天気病」と呼ぶ愛知医科大学教授の佐藤純先生は、このような興味深い実験結果を報告しています。
それは、関節炎や坐骨神経損傷になったネズミを用いて行ったものです。前線が通過した時に起こり得る気圧の変動に合わせ、実験施設の気圧を10分ほどかけて通常よりも30ヘクトパスカルほど低く下げ、約15分後、また元の気圧に10分ほどかけて戻しました。その状況下で、ネズミの足の裏を細い棒で押し、痛みで足を持ち上げる回数から痛みを数値化したのです。すると、気圧を下げることで、ネズミは痛みが増していることが分かりました。
同様に、気温をセ氏22度から15度に変えた実験でも、気温が下がることでネズミは足を持ち上げる回数が増えた。つまり、痛みが増したのです。
この実験では、心拍数と血圧も調べました。気圧や気温が下がり、痛みが増すと、心拍数と血圧が10%高まり、ノルアドレナリンというストレスがかかったときに分泌される物質が増えていました。
一方で、背中の交感神経を切ったネズミは気圧・気温の変化と、心拍数・血圧の変化とは連動していませんでした。これらの結果から、気圧や気温の変動は自律神経に影響し、痛みが通常より強くなることが明らかになったのです。
Qどういった病気に気を付けた方がいいでしょうか?
梅雨の時期に増えるのは、うつ病、腰痛、関節痛、そして急性虫垂炎と言われています。
たとえばうつ病。梅雨で日照時間が減ると、副交感神経が優位な状態になります。本来はリラックスした状態に副交感神経が優位になるのですが、その状態が過度になれば、うつ状態になる。慢性化するとうつ病から自殺のリスクも高まります。
また、急性虫垂炎に関しては、意外に思う人もいるかもしれません。梅雨の時期は言うまでもなく、気圧や気温の変化が大きい。自律神経のバランスが崩れ、免疫に関係するリンパ球の働きが正常でなくなり、免疫力が下がって感染症である急性虫垂炎を発症しやすくなると言われています。
Q梅雨が過ぎれば夏です。暑さで注意すべき病気はありますか?

前述のように、その季節に関連してリスクが増す病気として、夏は、血栓症に注意していただきたい。血栓症は、血液中にできた血栓(血液の塊)が血管を詰まらせ引き起こされる病気で、心筋梗塞、脳梗塞、肺塞栓、下肢静脈血栓症(エコノミークラス症候群)などがあります。夏は汗をたくさんかき、血液の水分が少なくなります。コレステロールや中性脂肪が高い人、動脈硬化が進んでいる人は、血栓ができやすくなるのです。
65歳以上の脳梗塞の患者2万1000人以上を調べた海外の研究では、平均気温がセ氏32度を超えると、27~29度の時に比べて、脳梗塞による死亡率が1・66倍に増えるという結果が出ています。
脳梗塞というと、血管が収縮する冬に増えるというイメージがあるかもしれません。しかし国立循環器病研究センターの報告では、2008~13年の脳梗塞患者の件数は、6~8月が最も多かったのです。6~8月1004件に対し、3~5月961件、9~12月917件、12~2月966件でした。
Q「気象病」とどう付き合っていけばいいでしょうか?
自分の不調が気象病によるものかどうかを知るべきです。毎年、梅雨になると不調が起こる。検査を受けてもはっきりした原因がこれまで分からなかった――。そういう場合は、天気予報をチェックし、不調との関連がないかを調べるといいでしょう。
私は脳神経外科医として慢性頭痛の患者さんもたくさん診ています。頭痛は気象の影響を受けやすい病気のひとつ。患者さんには「頭痛ダイアリー」をお薦めしています。どんな頭痛か、どういうタイミングで起こったか、天気はどうだったかなど、細かく日記につけてもらうのです。これを見れば、もし気象の影響もある頭痛であれば、すぐに分かります。気象病による不調をしばしば経験するようなら、気圧や気温の変化が大きい時には、自律神経のバランスを崩すようなことを極力控えるべき。睡眠不足、食生活の乱れ、ストレスなど……。平たく言えば、規則正しい生活を心掛ける、ということですが、それによって、いつもの不調が軽く済むことは、患者さんの話からもよくあることです。
Q先生の美学を教えてください。
絶えず思っているのは、うぬぼれてはいけない、ということです。常に自問自答しながら、これでよいのか、と考える。自分が正しいと思っていると、それがミスにつながることがある。いくら経験を積んでいても、本当に大丈夫かと自分に問いかけて、慎重に。というのも、患者さんは同じ病名であっても、ひとりひとり、つらさや苦しさは違います。その方にぴったりあった方法を考えていくのが医療。だからこそ、繰り返しになりますが、常に「それで本当に大丈夫か」と自分に問いかける姿勢を忘れないようにしています。