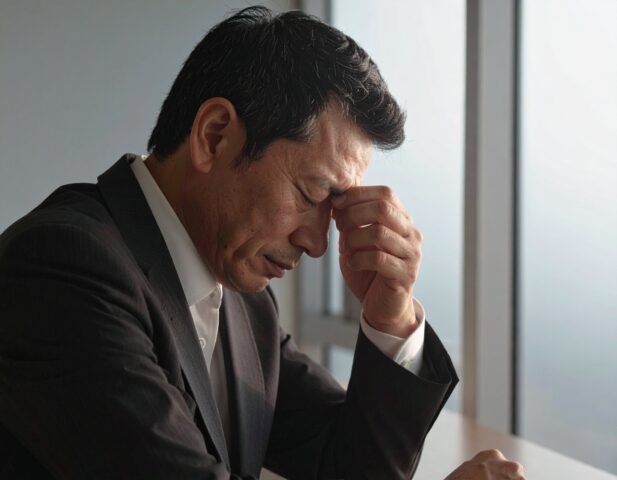2022₋1月に発行された最新の「ICD₋11(国際疾病分類第)」に、ゲーム障害とともに、燃え尽き症候群(バーンアウト)が追記された。「ICD₋11」は、WHO(世界保健機関)が作成している国際的な診断分類で、この改訂は約30年ぶりになる。
燃え尽き症候群は、だれもが陥るリスクを抱えている。厄介なのは、最初のうちは「なんだかやる気が出ない」「単なる疲れだろうか」と、本人はもちろん、周囲にも深刻さがないことだ。しかし介入のタイミングを遅くなれば、うつ病などのメンタル疾患へ移行してしまう恐れがある。
燃え尽き症候群とはどういう状態なのか?
どんな人がなりやすく、どういう対策を講じればいいのか?自身も燃え尽き症候群に陥った経験を持ち、産業医として燃え尽き症候群からうつ病に至った人に多く接している「リバランス」代表の池井佑丞氏に話を聞いた。池井氏は、燃え尽き症候群を分かりやすく解説した『「燃え尽きさん」の本 薪、火種、環境を整えれば「やる気」がよみがえる』(かんき出版)の著者でもある。
目次
Q1 燃え尽き症候群とは、どういう状態を指すのでしょうか?
これまでは多少困難があっても、それを乗り越え仕事をこなしてきた。ところが、まるで火が消えてしまったかのように、仕事へのやる気が出てこなくなり、適応できなくなる……。簡単にいうと、これが燃え尽き症候群です。
最初にこの用語が使われるようになったのは、1970年代。アメリカの精神心理学者ハーバート・フロイデンバーガーが、保健施設に勤務していた間、薬物常習の支援に当たっていた同僚たちが1年余りの間に徐々に、エネルギーが枯渇していくように、仕事への意欲や関心を失っていった状態を目の当たりにし、それを表現するのに、バーンアウトという言葉を用い、学術論文で取り上げました。バーンアウト(Burnout)、日本語訳での「燃え尽き」です。
Q2 燃え尽き症候群は、「病気」なのでしょうか?

燃え尽き症候群は、医学的には病気ではありません。国際的な診療ガイドラインの一つ、米国精神医学会の「DSM‐5(精神障害の診断・統計マニュアル第5改訂版)」には、病名として記載されていません。
ただし、2022年1月に発行された最新の「ICD-11」では燃え尽き症候群が記載されています。燃え尽き症候群は、「健康状態に影響を与える要因」の中の「雇用や失業に関連する問題」の一つとして盛り込まれ、「適切に管理されていない職場ストレスから生じるもの」として、次の3つが特徴とされています。
・エネルギーが枯渇するか、または消耗したという感覚
・仕事への忌避感の増加、または仕事に関する否定的ないし冷笑的な感情
・能率の低下
Q3 どんな人がなりやすいのでしょうか?
燃え尽き症候群は、いわゆる「頑張り屋さん」がなりやすい。しかしそう聞くと、「自分は〝頑張り屋さん〟じゃないから、燃え尽き症候群にならないだろう」と考える人もいるかもしれません。
真に「頑張り屋さん」じゃない人もいるでしょう。
しかし、産業医として複数の企業で多くのビジネスパーソンを見てきた私からすると、「頑張り屋さん」でない人はごく少数。仕事において、人間関係、職場環境、仕事の内容など、いいことばかりではありません。
多かれ少なかれ嫌なことがあり、しかしだからと言ってすぐにそこから逃げ出すのではなく、何らかの対処法を考え、こなしてきた人が大半だと思います。それがあるとき、燃え尽きて適用できなくなるのが、燃え尽き症候群。「どんな人がなりやすいのでしょうか?」という問いに対する私の回答は、「誰でも燃え尽き症候群になる可能性がある」になります。
Q4 燃え尽き症候群になると、どうなるのでしょうか?
身体的・精神的にさまざまな症状が表れます。どういう症状が表れるかは、人によって異なります。例えば、強い倦怠感、疲労感、脱力感、食欲の低下または亢進、睡眠障害、頭痛、肩凝り、腹痛、腰痛、関節痛、筋肉痛など。病院で検査をしても、異常(器質的疾患)は見つかりません。
生活面や社会面の変化では、遅刻や早退、欠勤が増える、仕事のミスが増える、身なりや生活が乱れる、表情が乏しくなる、投げやりな態度が増えるなど。
もっとわかりやすく言うと、シンプルにパワーが出なくなる。これを感じたら、燃え尽き症候群かも知れないな、と考えて、後で述べる対策を講じて欲しい。パワーが出なくなる状態が長く続くと、仕事のパフォーマンスは落ちていき、そうなると燃え尽き症候群でも結構進んだレベルになります。燃え尽き症候群そのものは病気ではありませんが、放置すると、うつ病などのメンタル疾患に移行してしまいます。
Q5 どういったケースがありますか?
仕事などで充実感を持って前向きな気持ちで頑張れる状態を「燃えている状態」とすると、心身ともに健康に燃え続けるには、やる気や意欲、頑張る理由(=火種)、火を燃やし保つための行動(=薪)が必要ですし、火種を大きくするための人間関係や業務の負荷(=環境)も重要です。火種、薪、環境がバランスよくそろってこそ、燃え尽きずに仕事を続けられるわけです。
火種、薪、環境の観点から、私は、燃え尽き症候群を大きく3つのタイプで捉えています。
【燃えすぎタイプ】
薪をくべすぎて火が大きくなりすぎ、焼き尽くして火が消えてしまうのが、このタイプです。難しいプロジェクトを任され、休日返上も厭わず全身全霊で仕事に打ち込み、その結果、無事成功。
ところが、プロジェクトが終わった後は気が抜けたようになり、数カ月経っても意欲や気力が抜けた状態が続いている。心身に高い負荷をかけ頑張りすぎたために、エネルギーが枯渇してしまったのですね。典型的な燃え尽き症候群が、この燃えすぎタイプです。
【燃え切らないタイプ】
火種(やる気)はあるのに、環境が合わずに燃えずにくすぶっているのが、燃え切らないタイプになります。
ある30代半ばの男性は、社内でも期待されている若手社員の一人。主任となり、業務の範囲が広がったのを機に、今ある課題の解決策を上司に精力的に提案。しかしなかなか理解してもらえず、逆に手厳しい言葉を投げかけられることが増えました。
次第に男性は、上司や後輩が自分のことを疎んじているのではないかと感じるようになり、仕事へのモチベーションが低下。「自分の力を発揮したい。仕事を頑張りたい」という気持ちの一方で、「やっても評価されない。やってられない」という不満や投げやりな気持ちが渦巻き、心身に不調をきたし、出社できなくなってしまいました。
【燃えないタイプ】
典型的な燃え尽き症候群である「燃え尽きタイプ」は、比較的中堅以上に多く見られます。それに対し、新入社員や若手に多く見られるのが、燃えないタイプです。
「燃えない」でも、「燃え尽き」症候群になるの?と疑問に思われるかもしれません。火種、薪、環境のどれに問題があっても燃え尽き症候群に至りますから、火種が小さく燃え上がることができない場合も、燃え尽き症候群になるのです。
有名大学を卒業し、第一希望の企業に就職を果たした20代女性。しかし配属されたのは、望んでいた部署ではなく、全く興味の持てない裏方部門でした。仕事に身が入らず、知識やスキルの習得も中途半端なまま何年も経ち、同期との業務レベルに差がどんどん開いていきます。そのことから一層やる気を失い、仕事のパフォーマンスも下がっていきました。遅刻や欠勤が目立つようになり、上司の勧めで私のところに相談に来ました。産業医として、上司も交えて面談。心身回復のための支援をすることとなり、上司も細やかに彼女をサポート。少しずつ自信を取り戻し、見事に「燃えられる」ビジネスパーソンに変身しました。
Q6 池井先生も、燃え尽き症候群を経験していると聞きました。
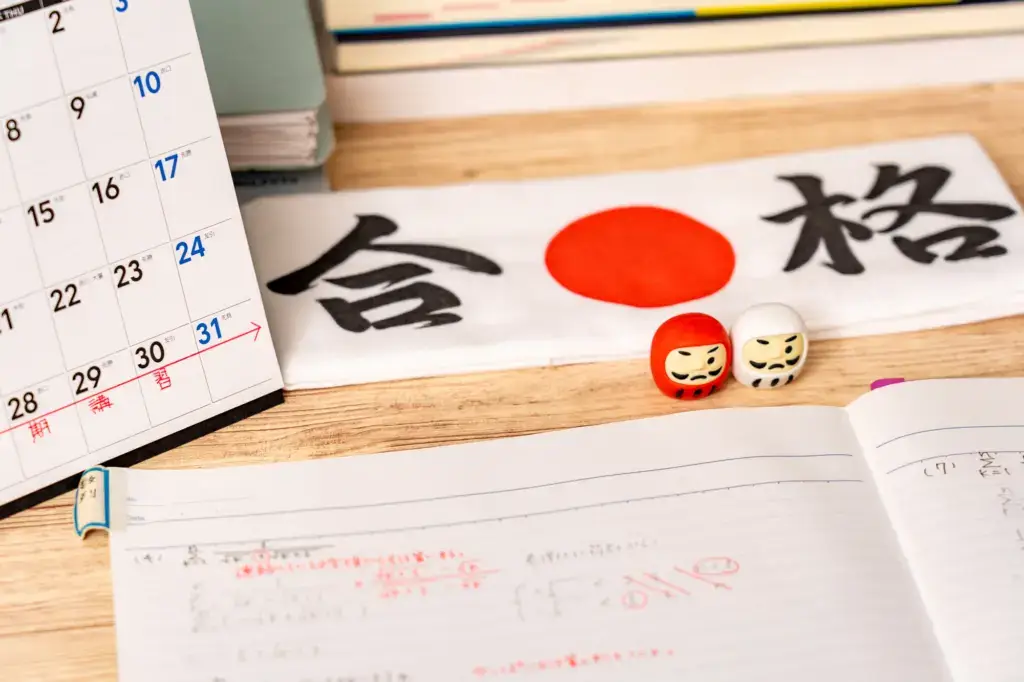
私は人生で二度、燃え尽きを経験しています。
一度目は、大学受験を控えた高校3年生の時。高校3年間ほとんど学校に通わず、勉強もしていませんでした。受験が迫ってきたので「そろそろ」と重い腰を上げたものの、ほとんど集中できない。それまでは、スタートすればすぐにペースを取り戻せると考えていたので、愕然としました。当然、大学受験は全滅で浪人生活に。予備校に通うのではなく、自分自身と向き合う時間を設けようと、自宅浪人を選びました。
受験勉強を頑張れなかったのは、頑張る理由が明確でなかったから。火種が小さく「燃えない」タイプの燃え尽き症候群です。自宅浪人で自分自身を見つめ直す時間を持つ中で、自分がこれからどう生きたいか、それはやはり医師となり人の役に立ちたい、同時に人一倍人生を楽しみたいという思いに気づきました。「やりたいこととやるべきことを頑張る」と自分ルールを決め、そのお蔭でやる気(火種)が大きくなり、1年間猛勉強を続けられたのです。
二度目は、医学部6年の年末。医師免許の国家試験まであと2カ月で、国家試験の勉強に全力で取り組まなければならない時期でした。しかし、全く勉強が手につかない。というのも、私は医学部生時代、プロのキックボクサーとしても活動しており、ちょうど医学部6年年末にはトーナメントで準優勝という、プロ格闘家としての大きな結果を手にしていたから。浪人時代に燃やした火種が大きな火となり準優勝につながったわけですが、目標達成のために燃えすぎ、そして燃え尽きてしまったのです。
「医師となり人の役に立ちたい」という火種はあるものの、浪人時代にように1年間も期間があるわけではない。国家試験まで2カ月。短期間で火種を燃え上がらせるのはとても困難でした。このとき力になってくれたのが、医学部の友人たちです。叱咤激励で強引に国家試験の勉強に引きずり込んでくれたお蔭で、勉強の感覚を取り戻し、国家試験に合格できたのです。
Q7 燃え尽き症候群になってしまったら……。どう対策を講じればいいのでしょうか?
第1ステップは、しっかり休養する。
考えてみてください。例えば風邪を引いて熱を出しているのに、「日頃の不摂生のせいだ」とジョギングしたりしますか? 休養を取って体を治すことに集中しますよね。ところがメンタル不調では、つらいと感じているのに、休養せずに仕事をしてしまう。それでは一層、状態が悪くなるだけです。
有給を取って仕事を休み、睡眠を十分に取る。休んでいるのに仕事のことを考えてしまうのも、燃え尽き症候群にありがちなケース。スマホやパソコンとは、少し距離を置くことをお勧めします。
休養をしっかり取れたら、第2ステップとして、「普通の生活を普通に送れる」ようにしましょう。イメージするのは、ゆったりした休日。朝起きて身だしなみを整え、食事をし、必要なものがあれば買い物に出かける。夜はゆっくりお風呂に入り、決まった時間に床に着く。
職場に復帰するのは、日常生活を安定して送れるようになってから。この第3ステップでは、1日仕事をできたら合格点、くらいに捉えてください。仕事量をセーブし、無理をしない。意図的に負荷を調整し、数週間から数カ月かけて、仕事のペースに自分を慣らしていくのです。目安は、休日に遊ぶ力があるくらいのペースです。
第4ステップ、つまり社会生活が無理なく送れるようになった段階では、「上手に燃えられる状態」を作っていきます。ポイントは、「火種を大きくする」「薪のくべ方をマスターする」「燃えられる環境を整える」。自分が「燃えすぎ」「燃え切らない」「燃えない」タイプのどれに近いかによっても、3つのポイントのうち特にどこに注意すべきかが変わってくるでしょう。
私の経験から特に伝えたいのが、何かあった時に話をしたり相談したりできる人を作っておきましょう、ということ。格闘技では、セコンドのような存在です。それも、セコンドは1人ではなく複数いるとベター。人生や仕事において燃え尽きずに闘い続けるには、セコンドの存在は非常に重要です。職場の上司や同僚、家族や友人、隣近所の人、学生時代の恩師、そして産業医やカウンセラーもセコンドになり得ます。家族や友人と疎遠になっている、隣近所の人と交流がないという場合は、自分からアプローチしてみるのも手です。