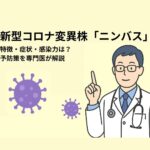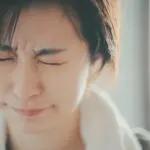下痢や便秘といった便通異常、そして腹痛…これらの症状が慢性的に続くと、日常生活にも大きな支障をきたしますよね。
実は、検査で異常が見つからないにも関わらず、このような症状に悩まされている方は少なくありません。もしかしたら、それは過敏性腸症候群(IBS)かもしれません。
IBSは、消化管に目立った異常がないにも関わらず、腹痛や便通異常が慢性的に続く病気です。 その症状は人それぞれで、下痢が続く、便秘に悩む、あるいはその両方を繰り返すなど、様々なパターンが存在します。
ご自身の症状がどのタイプに当てはまるのか、そしてその原因や最新の治療法まで、この記事で詳しく解説していきます。
過敏性腸症候群(IBS)の症状とタイプ別の特徴

過敏性腸症候群(IBS)は、大腸に炎症や潰瘍などの目に見える異常がないにもかかわらず、腹痛や便通異常といった症状が慢性的に続く病気です。日本人の10〜20%に見られる疾患で、消化器疾患で外来に通う人の3割を占めるといわれています。(※1)
検査では異常が見つからないため、周りの人に理解されにくく、不安やストレスを抱え込んでしまう患者さんも少なくありません。
IBSの症状は人によって実に様々で、下痢が続く方、便秘に悩む方、あるいはその両方を繰り返す方など、多様なパターンが存在します。これらの症状の特徴に基づいて、IBSは主に3つのタイプに分類されます。
ご自身の症状はどのタイプに当てはまるか、以下の説明を参考にしながら確認してみてください。
※1出典:全国健康保険協会.「過敏性腸症候群(irritable bowel syndrome;IBS)」
.https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/kochi/20140325001/20170911kabinseityoushoukougun.pdf ,(閲覧日 2025-07-13).
下痢型IBS:突然の下痢や腹痛に悩まされる
下痢型IBSの代表的な症状は、突然の激しい腹痛と下痢です。食後や緊張した場面など、特定のタイミングで症状が現れやすい傾向があります。朝食後や満員電車の中など、日常生活の様々なシーンで突然便意に襲われ、トイレに駆け込むことも少なくありません。
下痢の回数は1日に数回から十数回に及ぶこともあり、便は水様便や泥状便であることが多いです。このような症状のために、外出を控えたり、仕事や学業に集中できなかったりするなど、日常生活に大きな支障をきたす場合もあります。
便秘型IBS:残便感やお腹の張りを感じる
便秘型IBSでは、便が硬く、排便が困難になります。数日間排便がないことも珍しくなく、排便後も残便感があり、スッキリしない感覚が続きます。便の形状はウサギの糞のようにコロコロとした形状になることが多いです。
また、便秘に伴い、お腹の張りや膨満感を感じることも多く、ガスが溜まりやすいため、腹部膨満感に悩まされる患者さんもいます。
混合型IBS:下痢と便秘を繰り返す
混合型IBSは、下痢と便秘を交互に繰り返すタイプです。例えば、数日間便秘が続いた後、突然下痢になる、といったように、排便状態が不安定で、予測がつきません。
このような排便パターンの変動は、患者さんにとって大きなストレスとなり、日常生活に影響を及ぼす可能性があります。下痢型や便秘型に比べて、精神的な負担を感じやすい傾向があるとも言われています。
腹痛や腹部膨満感:IBSに伴うよくある症状
腹痛や腹部膨満感は、IBSの患者さんに共通してよく見られる症状です。腹痛は排便前に強く、排便後に軽減することが多いのが特徴です。
腹部膨満感は、ガスが溜まっているような感覚で、常にお腹が張っているように感じる方もいます。これらの症状は、食事の内容や時間帯、ストレスなどによって変化することがあります。
その他の症状:吐き気、頭痛、疲労感など
IBSの症状は、腹痛や便通異常といった消化器症状だけにとどまりません。吐き気や頭痛、疲労感、めまい、動悸、肩こりなど、様々な全身症状が現れることがあります。
また、不安感や気分の落ち込み、イライラなどの精神的な症状を伴う場合もあり、これらは自律神経の乱れと関連していると考えられています。これらの症状は、IBSの診断において重要な手がかりとなるため、医師に相談する際には、些細なことでも伝えるようにしましょう。
過敏性腸症候群(IBS)の原因と診断
過敏性腸症候群(IBS)の原因は特定されていませんが、複数の要因が複雑に絡み合い、IBSの症状を引き起こすと考えられています。
ここでは、IBSの原因として考えられている要因と診断方法について詳しく解説します。
ストレスや生活習慣:IBSの引き金となる要因
ストレスは、IBSの大きな誘因の一つと考えられています。精神的なストレスは、自律神経のバランスを崩し、腸の運動に影響を及ぼします。慢性的なストレスを抱えている方は、そうでない方に比べてIBSを発症するリスクが高くなります。
例えば、職場でのプレッシャーや人間関係のトラブル、家庭環境の変化、大切な人の死別といった出来事が、IBSの症状を悪化させる要因です。
また、夜更かしや不規則な食生活、睡眠不足、運動不足といった生活習慣の乱れも、IBSの症状に影響を与える可能性があります。
腸内環境の乱れ:善玉菌と悪玉菌のバランス
私たちの腸内には、数百種類、数百兆個もの腸内細菌が生息しており、腸内フローラ(腸内細菌叢)を形成しています。この腸内フローラは、消化吸収の補助や免疫機能の調節など、健康維持に重要な役割を果たしています。
腸内細菌は大きく分けて、身体に良い影響を与える善玉菌、悪い影響を与える悪玉菌、どちらにもなりうる日和見菌の3種類に分類されます。
健康な状態では、これらの菌がバランスを保っていますが、食生活の乱れやストレス、抗生物質の使用などによってバランスが崩れ、悪玉菌が優勢になると、腸の運動が不安定になり、IBSの症状を引き起こしたり悪化させたりする可能性があります。
遺伝的要因:家族歴との関連性
IBSの発症には、遺伝的な要因も関与していると考えられています。
例えば一卵性双生児の研究では、片方がIBSの場合、もう片方もIBSを発症する確率が二卵性双生児よりも高いことが示唆されています。(※2)また、家族にIBSの患者がいる場合、そうでない場合に比べてIBSを発症するリスクが2〜3倍高くなるという報告もあります。(※3)
ただし、遺伝的要因だけでIBSの発症が決定されるわけではありません。環境要因も大きく影響するので、生活習慣に気を付けることでIBSの発症リスクを低減できる可能性があります。
※2
出典:Bengtsson M, Ohlsson B, Håkanson R, et al. Irritable bowel syndrome in twins: genes and environment. Neurogastroenterol Motil. 2006;18(5):400–409.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17008364/ (閲覧日:2025年7月13日)
※3
出典:Mohammed I, Cherkas LF, Riley SA, Spector TD, Trudgill NJ. Genetic influences in irritable bowel syndrome: a twin study. Am J Gastroenterol. 2010;105(4):747–753.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21333900/ (閲覧日:2025年7月13日)
脳腸相関:脳と腸の密接な関係
脳と腸は、自律神経系、内分泌系、免疫系などを介して密接に関連しており、相互に影響を及ぼし合っています。この脳と腸の密接な関係は「脳腸相関」と呼ばれています。
ストレスを感じると、脳から腸へ信号が伝わり、腸の運動が変化します。例えば、ストレスによって腸の蠕動運動が亢進し、下痢を引き起こすことがあります。逆に、ストレスによって腸の蠕動運動が抑制され、便秘を引き起こすこともあります。
脳と腸が双方向に影響し合うメカニズムも、IBSの症状発現に大きく関わっているでしょう。
診断方法:問診、身体診察、検査
IBSは他の消化器疾患を除外することで診断される「除外診断」です。医師はまず、患者さんから詳しい症状(腹痛の程度や頻度、便通の状態、発症時期など)や生活習慣、病歴などを丁寧に聞き取ります(問診)。
問診に加えて、身体診察(腹部を触診するなど)を行い、必要に応じて血液検査、便検査、大腸内視鏡検査などの検査を行います。これらの検査で器質的な異常(炎症、潰瘍、腫瘍など)が認められず、RomeⅣ診断基準などの診断基準を満たす場合に、IBSと診断されます。
| 【RomeⅣ診断基準】(※4)繰り返す腹痛が、最近3カ月の間で平均して少なくとも週1日あり、次のうち2つ以上の基準を満たす排便に関連する排便頻度の変化を伴う便形状(外観)の変化を伴う ※少なくとも診断の6カ月以上前に症状があり、最近3カ月間は基準を満たしていること |
IBSは症状や原因が複雑な病気であるため、自己判断せずに医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けることが重要です。
※4
出典:日本大腸肛門病学会.「過敏性腸症候群(IBS)」.
https://www.coloproctology.gr.jp/modules/citizen/index.php?content_id=5 (閲覧日:2025年7月13日)
過敏性腸症候群(IBS)の治療法と日常生活の注意点

過敏性腸症候群(IBS)の治療は、つらい症状を和らげ、より快適な日常生活を送れるようにするためのものです。
IBSは完治する病気ではありませんが、症状をコントロールし、再発を予防することで、生活の質を向上させることが可能です。
薬物療法、食事療法、認知行動療法、生活習慣の改善など、治療のアプローチは多岐にわたります。
薬物療法:症状に合わせた薬の選択
IBSの薬物療法は、基本的に対症療法、つまり症状を抑えることを目的としています。下痢がひどい方には下痢止め、便秘がちな方には便秘薬、腹痛が強い方には鎮痛剤といったように、症状に合わせて薬が選択されます。
下痢止めとしては、ポリカルボフィルカルシウムなど便の水分を吸収する薬や、塩酸ラモセトロンなど腸の運動を抑制する薬があります。便秘薬には、酸化マグネシウムなど便を柔らかくする薬や、リナクロチドなど腸の動きを活性化する薬があります。また、腹痛が強い場合には、鎮痙剤や鎮痛剤が用いられます。
さらに、腸内環境を整えるために、整腸剤(プロバイオティクス)が処方されることもあります。プロバイオティクスは、腸内フローラのバランスを改善し、善玉菌を増やすことで、IBSの症状を緩和する効果が期待されています。ビフィズス菌や乳酸菌などが代表的なプロバイオティクスです。
これらの薬は、症状や体質に合わせて処方されます。自己判断で服用せず、必ず医師の指示に従ってください。また、副作用についても医師や薬剤師に相談することが大切です。
食事療法:低FODMAP食など、食事内容の見直し
食事は、IBSの症状に大きく影響を与えるため、食事療法はIBSの治療において重要な役割を担います。特に注目されているのが「低FODMAP食」です。
FODMAPとは、発酵性のオリゴ糖、二糖類、単糖類、そしてポリオール(糖アルコール)の頭文字をとったもので、これらは小腸で吸収されにくく、大腸で発酵しやすいため、IBSの症状を悪化させる可能性があります。
低FODMAP食では、これらのFODMAPを多く含む食品を制限します。例えば、果物ではリンゴやマンゴー、野菜では玉ねぎやニンニク、乳製品では牛乳やヨーグルト、穀物では小麦やライ麦、甘味料でははちみつや果糖ぶどう糖液糖などです。
ただし、低FODMAP食は、すべての患者さんに効果があるわけではなく、個人差があります。また、長期間続けると栄養バランスが崩れる可能性もあるため、医師や管理栄養士の指導のもとで行うことが重要です。
低FODMAP食以外にも、刺激の強い食品やアルコール、カフェインの摂取を控える、食物繊維をバランスよく摂取する、よく噛んで食べる、1日3食規則正しく食べる、といった基本的な食生活の改善も重要です。十分な水分摂取も、便通を改善し、症状を和らげるために効果的です。
認知行動療法:ストレスへの対処法を学ぶ
ストレスはIBSの症状を悪化させる大きな要因の一つです。認知行動療法(CBT)は、ストレスへの対処法を学ぶことで、IBSの症状を改善する効果が期待される心理療法です。
CBTでは、ストレスを感じやすい考え方のパターンを見つけて修正したり、ストレスにうまく対処する方法を身につける訓練を行います。
例えば、「仕事でミスをしたらどうしよう」といった不安な考え方に囚われていると、ストレスを感じやすくなります。CBTでは、このような考え方のクセを見直し、より現実的な考え方に変えていくことで、ストレスを軽減することを目指します。
生活習慣の改善:睡眠、運動、リラックス
規則正しい生活習慣は、IBSの症状を改善し、再発を防ぐために重要です。質の高い睡眠を十分に確保することは、自律神経のバランスを整え、腸の働きを安定させることにつながります。毎日同じ時間に寝起きし、睡眠時間を7時間程度確保するようにしましょう。
適度な運動も、ストレス軽減や腸の動きを活発にする効果があります。ウォーキングやヨガなど、無理なく続けられる運動を習慣に取り入れましょう。
また、趣味やリフレッシュの時間を持つなど、リラックスできる時間を作ることも大切です。ストレスを溜め込まないよう、自分なりのストレス解消法を見つけるようにしましょう。
症状悪化の予防:再発を防ぐための対策
IBSの症状が改善した後も、再発を防ぐためには、継続的なケアが必要です。自分に合った食事療法を続け、ストレスマネジメントを心がけ、規則正しい生活を送りましょう。
症状が落ち着いていても、定期的に医師の診察を受け、症状の変化などを相談することも大切です。IBSは慢性的な病気であるため、継続的な治療と自己管理が重要です。
IBSは、日常生活に大きな影響を与える病気ですが、適切な治療と生活習慣の改善によって、症状をコントロールし、快適な生活を送ることは可能です。諦めずに、医師と相談しながら、自分に合った治療法を見つけていきましょう。
まとめ
過敏性腸症候群(IBS)は、ストレスや腸内環境の乱れなどが原因とされる、決して珍しくない疾患です。完治が難しいといわれますが、薬や食事、生活習慣の改善などを組み合わせることで、症状の軽減は十分に可能です。
つらい症状を我慢せず、専門家の力を借りながら、自分に合った方法でじっくり向き合っていきましょう。