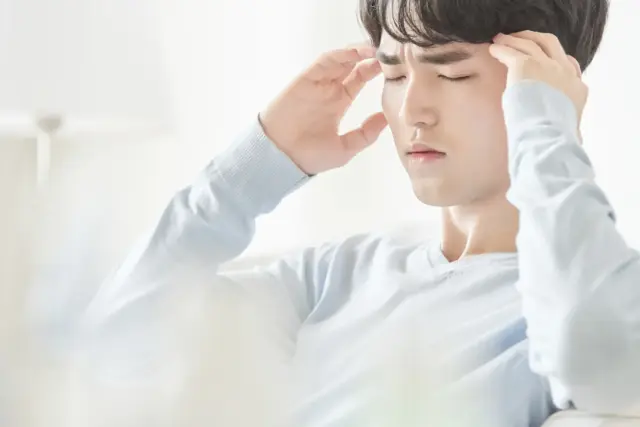目次
はじめに
「NTTドコモ モバイル社会研究所」によると、日本国内での携帯電話所有者のスマートフォン比率は増加の一途を辿っている。2010年にはスマホの所有率は約4%だったのが、15年には51.1%、20年には88.9%となり、24年のスマホの所有率は97%だ。シニアでもスマートフォン所有は当たり前となっており、未所有は1割未満。スマートフォンを2台以上所有している割合は全体で11.4%で、女性は若い世代ほど2台以上の所有者が多く、特に15〜19歳の女性では約2割2台以上所有していた(いずれも、「NTTドコモ モバイル社会研究所より」)。
スマホなしには生活が成り立たない、という人も少なくないだろう。使う頻度が増えるにつれ、心配になってくるのが体への影響。「スマホやパソコンの使い過ぎで頭痛が悪化する人は珍しくありません」と指摘するのは、日本頭痛学会専門医の清水俊彦医師。スマホをはじめとする電子機器と頭痛の関係、頭痛対策で押さえておくべきことを聞いた。
Q1.スマホやパソコンは、頭痛を誘発するのですか?
頭痛には、大きく分けて一次性頭痛と二次性頭痛があります。一次性頭痛は、片頭痛や緊張型頭痛、群発頭痛など「頭痛持ちの方の頭痛」で、生活の質(QOL)に大きな影響を与えますが、生命予後に支障はきたしません。
二次性頭痛は、くも膜下出血や脳腫瘍、頭部外傷、甲状腺機能障害や側頭動脈炎などの自己免疫疾患等、原因がはっきりしている頭痛です。これまで感じたことがない頭痛が突然起こるケースが一般的で、治療が遅れれば生命予後に関わるものもあります。
スマホやパソコンが関係している頭痛は、一次性頭痛。VDT症候群という言葉を聞いたことがあるでしょうか? VDTとは、 Visual Display Terminal(ビジュアル・ディスプレイ・ターミナル)の略で、スマホやパソコンの画面などを指します。スマホなどのタブレット端末やパソコンの長時間使用で生じた様々な心身の不調(例えば、目の疲れ、首・肩の凝り、頭痛、イライラや不安、抑鬱状態など)を、「VDT症候群」といいます。
厚労省は、平成10年から5年ごとに「技術革新と労働に関する実態調査」を実施(平成20年で廃止)。平成20年の調査では、「VDT作業でストレスを感じる」と答えた割合は34.6%、「VDT作業で身体的な疲労や症状がある」と答えた割合は68.6%。また、「VDT作業で身体的な疲労や症状がある」と答えた人のうち、どういう症状なのかについては、「目の疲れ・痛み」が90.8%、「首・肩の凝り、痛み」は74.8%でした。
私は、「電子機器と頭痛」を考える上でVDT症候群を問題視する一方、脳過敏症候群の深刻さも日々痛感しています。これをしっかり認識し、頭痛治療に当たる医療関係者は積極的に治療に取り組まねばならないと考えていますが、現実は追いついていません。
Q2.脳過敏症候群とは、どういう状態を指すのでしょうか?

まずは、片頭痛の説明から始めましょう。
片頭痛は頭の片側がズキズキと脈打つように痛む頭痛で、特に女性に多いといわれています。
この片頭痛ですが、脳が過敏であること、脳の異常な興奮で引き起こされることが、近年の研究で明らかになっています。脳がストレスや気圧、温度の変化など外的な刺激を受けることで異常な興奮が引き起こされます。特に女性の場合、女性ホルモンの変動周期に敏感に反応し、脳血管内の血液中の血小板からセロトニンが異常に放出されたのちに代謝して今度は枯渇し、それに反応して脳血管が異常に拡張する結果、血管の周囲にある三叉神経が刺激され、片頭痛の激しい痛みが生じるのです。
片頭痛がある場合、速やかに病院で適切な治療を受けていればいいのですが、たかが頭痛と考えて、鎮痛薬で痛みをごまかしたり、痛みを我慢して過ごしたりする人は少なくありません。
すると、脳の興奮状態を放置したままになるため、脳はちょっとした刺激でも興奮し、些細なことで頭痛以外の不快な症状を生じるようになります。これを私が脳過敏症候群と命名し、2010年に日本頭痛学会、2011年に国際頭痛学会で発表しました。
一般的に、加齢とともに動脈硬化で脳血管が広がりづらくなり、片頭痛の痛み自体は感じにくくなっていきますが、脳の興奮状態が鎮まったわけではありませんから、脳の興奮が慢性化。脳の働きが混乱し、頭の中で雑音が鳴り響くような頭鳴、立っていられないような浮動性めまい、頭重感、不眠が生じたり、物忘れ、イライラ、攻撃的な行動につながったりすることが、脳過敏症候群の主な症状です。
Q3.脳過敏症候群も、スマホやパソコンが関係するのでしょうか?
片頭痛は、「脳が過敏」「脳の異常な興奮」で引き起こされると述べました。もう少し具体的にいうと、脳の一番後ろにある後頭葉が異常な興奮状態になるわけですが、後頭葉はスクリーンのような役割を担っているため、スマホやパソコンのブルーライトが光刺激となり、興奮状態をより一層ひどくしてしまうのです。後頭葉のみならず大脳全般に興奮状態が伝播し、大脳の全ての機能に何らかの支障が生じ、正常な思考能力が削がれてしまうことも往々にしてあります。
Q4.ブルーライトは目や脳に良くない、とよく聞きます。
液晶画面から放たれるブルーライトは、蛍光灯から出る光と比較して直進性が高くなっています。人が目で見ることができる可視光線の中で最も強いエネルギーを持っているブルーライトを、目で全て受け止めることとなり、視神経から視索という視路を介して大脳の後頭葉へとダイレクトに届けられてしまうので、結果、脳を強く刺激してしまうのです。
ブルーライトは、スマホやパソコンの液晶画面を鮮明に見せるために開発されており、技術の進歩によるもの。しかし頭痛にとっては大敵です。ブルーライトをカットするメガネを使ったり、パソコンの画面の光量を落としたりなど、頭痛回避のための策を講じる必要があります。
Q5.眩しい光も頭痛を招きますか?
もちろんです。スマホやパソコンの画面の光と同様、太陽の光も、頭痛を誘発したり、増長させたりします。
Q6.そうなると、サングラスは頭痛対策に有効なのでしょうか?

私は患者さんに、サングラスを日常的に使用してくださいと、常々言っています。サングラスが強い光刺激から脳を守ってくれるからです。
ある頭痛持ちの路線バスの運転手さんが、こんなことをおっしゃいました。
「運転中、太陽の光が目に突き刺さるように異様に眩しく感じた時や、夜間の運転中、対向車のヘッドライトや前の車のテールランプが異様に眩しく感じた時、その後必ずと言っていいほど激しい頭痛が起こります。ひどい場合は、目の前にチラチラと閃光が走り、視界を妨げることがあります」
私はすぐさま、サングラスを着用するよう伝えました。運転手さんは、会社へサングラスの着用を申請。しかし、「品が良くない」「乗客からクレームが来る」との理由から、却下されました。そこで私が診断書を書き、運転手さんは再度会社へ申請。そこでようやく淡い色のサングラスなら可能と認められたのですが、私としては、常に異常なまでの陽光の中、飛行を続けている航空機のパイロットは濃いサングラスの着用が認められているのに、路線バスの運転手さんは何故却下されるのか、納得がいかない部分もあります。幸いなことに、この運転手さんは淡いサングラスのお蔭もあって、運転中の頭痛は生じなくなったそうです。またある片頭痛持ちの女性は天気の良い日に洗濯物を干すため空を見上げた瞬間にフワフワしためまいを感じ、その後、激しい片頭痛発作に見舞われたため、このような際には、サングラスを常用するようになったそうです。
日本人はサングラスへの偏見が強い。もっと普通にかけられるような環境になれば、強い光刺激で頭痛が誘発される人はかなり減るのではないかと考えています。
Q7.「脳の異常な興奮」という観点から、光刺激以外にも注意すべきことはありますか?
強い香り、そして大きな音です。
こんな患者さんがいました。片頭痛持ちの女性で「職場で頭痛が悪化する。休みの日はそこまでひどくない」とのこと。よく話を伺うと、職場はデパートの化粧品売り場で、化粧品や香水の香りが常に漂っている。頭痛持ちでなければ「いい香り」と感じるかもしれませんが、片頭痛持ちには、大変つらい環境です。診断書を提出し、化粧品や香水の香りのない職場へと異動となったことで、片頭痛が起こりづらくなりました。一般の人には「いい香り」、でも片頭痛の人には「頭痛の誘発因子」になる可能性があるものといえば、柔軟剤やシャンプーの香りなども該当します。
映画館でひどい片頭痛をよく起こす患者さんもいらっしゃいました。映画館は大音量が流れますよね。また、照明を落とした真っ暗な状態で、スクリーンから強い光が放たれる。座った座席によっては、隣の人がポップコーンを食べていたり、香水の香りが異常に強かったりして、その匂いが刺激となることもある。「大きな音」+「強い光」、そこに強い香りも加われば、三重苦です。
ただ、この患者さんの場合、空腹で映画を見ていることも、片頭痛につながっていました。空腹で血糖値が低下すると、脳血管が拡張し、血管周囲の三叉神経が刺激される。それを大脳が読み取り、興奮状態になって、頭痛が生じる。
私のアドバイスで、鑑賞前には飴玉など糖分を摂取し、血糖値が低下しないようにしたところ、映画館でひどい片頭痛に見舞われることはなくなりました。この患者さんにとっては、大きな音、強い光、刺激的な匂いに加えて空腹による血糖値の低下が、片頭痛に影響を与えていたということになります。
Q8.片頭痛は「トリプタン製剤で対処」というイメージが強かったのですが、さらに様々な対策があるのですね。
まさにその通りです。一次性頭痛の中でも、片頭痛のコントロールは難しいと感じている方は患者さんのみならず医師の方々にも多数いらっしゃるかと思います。「トリプタン製剤を飲んでいるのに、よくならないもしくは効果があまり感じられず寝込んでしまう」という人もいるでしょう。
私は頭痛患者さんの診察においては、必ず脳波を確認します。脳の過敏性がどれほど高まっているかを調べ、それが頭痛の引き金になっていることを患者さんにしっかり説明し、脳を興奮させるようなことは極力排除するよう、伝えます。トリプタン製剤も処方しますが、脳の興奮状態が高い方には、まずはこれを鎮める片頭痛の予防薬を処方し、様子を見ます。
さらに、ラスミジタン(商品名:レイボー)という片頭痛の病態に関連する三叉神経の大元である三叉神経核に作用する新薬も最近登場しているので、状況に応じて処方の工夫をいたします。トリプタン製剤は脳血管とその周囲にセンサーのように張り巡らされた三叉神経終末に主に作用します、すなわちこの三叉神経終末から放出されるCGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド: Calcitonin Gene-Related Peptide)という神経炎症タンパクが脳血管壁を刺激して脳血管が異常に拡張して片頭痛が起こるのですが、このトリプタン製剤は三叉神経終末すなわち末梢性に作用する薬剤であるがゆえに、頭痛が起こり始めたらなるべく早期に服薬しなければ効果が得られないことが多かったのです。
このような際に、新薬のラスミジタンを1~2時間後追加で服用することにより大本の三叉神経核からの片頭痛情報を完全に断ち切ることが可能となり、このような処方方法をトリプタンレスキューと称しています。もちろんトリプタン製剤でどうしても頭痛の起こり始めの早期服薬のタイミングが把握しづらいような際には、頭痛が起こり始めて1~2時間経過しても約15分で三叉神経核に到達し中枢性に作用するラスミジタンのみを初めから服用することも可能です。三叉神経終末を水道の蛇口に例えればトリプタン製剤で蛇口を閉めるタイミングが遅れた際に、このラスミジタンで水道局の大本の水道管を閉めてもらうことにより片頭痛を頓挫させることが可能なのです。
頭痛を診ている医師の中には、効果があまり得られていないにもかかわらず、漫然と薬を出しているケースが、少なからず散見されます。しかしそれほど、片頭痛とは個々の症例に応じてテーラーメイドの治療が必要となる治療困難な疾患なのです。生活の質を著しく下げる片頭痛は、脳の過敏さ、脳の異常な興奮をどう改善するかが、治療のキモになります。そのためには、脳波のチェックは必須。
さらに、脳を興奮させない具体的な生活指導も必須。いずれも受けていない…という人は、医療機関や主治医に今一度治療を根本的に見直してもらうことが必要かもしれません。