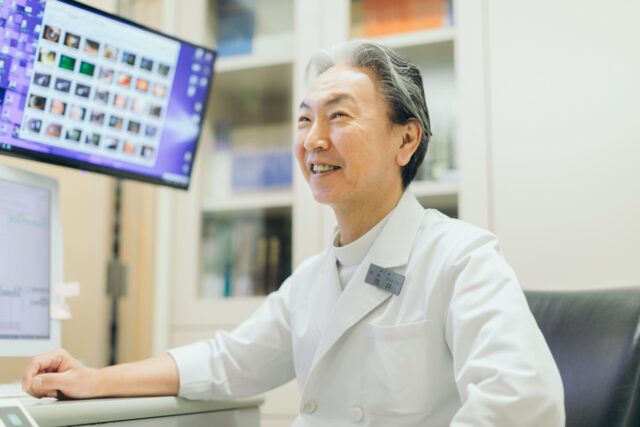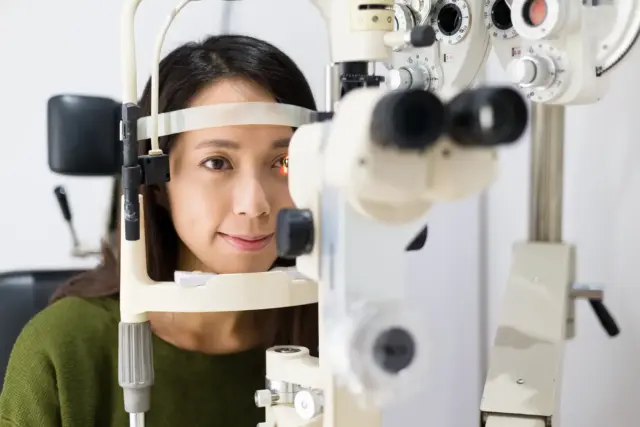目次
はじめに
視力低下が、懸念されている。原因は、パソコンやスマホなどを見続ける時間が増えたこと。
コロナ禍以降、会議などがオンラインとなることが増えた。朝から晩までパソコンの前に座り、画面と向き合っているという人は多いだろう。
子どもたちにしたってそうだ。パソコンやタブレットなどの画面を見ている時間が長時間化。
また、遊ぶときもゲームをしたり動画配信サービスを利用したりで、仕事や勉強の時間以外もスマホなどの小さな画面を近距離で見続けるようになった。
視力低下は、単なる「遠くの見え方が悪くなる」だけが問題なのではない。目の重大病発症のリスクを高めることが分かっている。YouTubeチャンネル「眼科医平松類」を運営し、『眼科医だけが知っている 一生視力を失わない50の習慣』(SBクリエイティブ)など目に関する著書が多数ある二本松眼科病院副院長の平松類副先生に話を聞いた。
★視力は年単位でも落ちるものなのでしょうか?
視力が低下しやすい生活を送っていると、年単位どころか月単位でも視力は落ちます。例を挙げましょう。2020年、当時の安倍首相(故人)の要請で、コロナの感染拡大防止のための全国一斉休校が始まりました。休校期間は最長で約3カ月。4月10日から一斉休校となった京都市では、一斉休校を終えた6月のタイミングで、市内の小学生に視力検査を実施。すると、視力が0.7未満の子どもが、コロナ前の前年より6%増の23%だったといいます。
この調査は子どもが対象でしたが、大人であっても、同じような結果が見られたでしょう。
★「近視であれば眼鏡をかければいい」との考え方もありますが…。

近視は、遠くが見えづらくなるだけではありません。目の重大病のリスクを高めることが明らかになっています。
ある研究論文では、近視でない人の病気発症のリスクを1とした場合、発症リスクがどれくらいになるかが、次のように示されています。ここでいう近視の程度(軽度、中等度、強度)とは視力ではなく、屈折度の単位であるジオプトリー(D)を用いています。軽度近視はマイナス3D以下、マイナス3Dを超えてマイナス6D以下は中等度近視、マイナス6Dを超えると強度近視と分類されます。
◎緑内障
- 軽度の近視で1.59倍
- 中等度以上の近視で2.92倍
◎白内障
- 軽度の近視で1.56倍
- 中等度の近視で2.55倍
- 強度の近視で4.55倍
◎網膜剥離
- 軽度の近視で3.15倍
- 中等度の近視で8.74倍
- 強度の近視で12.62倍
◎黄斑症(近視性)
- 軽度の近視で13.57倍
- 中等度の近視で72.74倍
- 強度の近視で845.08倍
★いずれも失明の危険性がある目の病気ですか?
まさにそうです。それぞれの病気の説明を簡単にしましょう。
【緑内障】
緑内障は、視神経が障害・圧迫され、見える範囲が狭くなる病気です。障害された視神経は元には戻らないので、早期発見し、それ以上進行しないように眼圧を下げることが基本の治療となります。
【白内障】
カメラのレンズに当たる水晶体が濁るのが白内障。視力の低下、光のまぶしさ、ぼやける、かすむ、視界が暗く感じるなどの症状があります。白内障は、加齢とともにリスクが高くなります。根本的な治療は手術しかなく、濁った水晶体を取り除き、人工の眼内レンズを入れます。
【網膜剥離】
眼球の内側の網膜という膜がはがれて視力が低下します。網膜は、カメラでいえばフィルムの働きをしているところ。加齢、糖尿病性網膜症のような一部の病気、頭部や眼球への物理的ショックが原因で起こります。網膜がそれほど剥がれていなければレーザー光線、すでに網膜剥離が起こってしまった場合は手術となります。
【黄斑症(近視性)】
強度近視で目の直径である眼軸が伸び、視機能に関連する黄斑部などに亀裂が生じ、視野にゆがみや暗点が生じて視力が低下します。
★頭痛や肩こりが、目に関係しているとも聞きます
過剰に近距離で物を見ると近視になりやすいですが、これが頭痛、肩こり、倦怠感、不眠といった不定愁訴の原因になっていることがあります。
スマホの使い方で、目を守るために絶対に避けて欲しいのが、暗いところでスマホを見ること。特にベッドの中、寝る前に見るのはNG。視力を低下させるのに加え、スマホが発する明るい光の刺激が、自律神経のうち興奮をつかさどる交感神経を優位に働かせます。本来は、鎮静をつかさどる副交感神経が優位に働くタイミング。それが交感神経優位になってしまうわけですから、神経が高ぶって寝つきが悪くなり、睡眠の質が低下します。自律神経のバランスが崩れ、それがやはり不定愁訴の原因にもなります。
★視力が良ければ、目に問題はないでしょうか?
「視力がいい」=「目がいい」と考えがちですが、実はそうではない。「見えるか、見えないか」ということにおいて、視力はひとつの能力に過ぎません。
視力検査を思い出してください。そのとき、その瞬間、ちゃんと見えれば正解になります。しかし日常生活では、起きている間ずっと目を使っているわけで、朝は快適に見えていても、午後からは見え方が悪くなってくることもあるでしょう。一方で、視力が低くてメガネやコンタクトレンズを使っていても、一日中、目が疲れることなく、快適に見えている人もいます。実際、私も視力は低いですが、目が疲れることはなく、見えにくいということはありません。
要は、どれだけ自分の目を使いこなせているか。近視であっても、めがねなどによってしっかり見えていれば、目が悪いとはいえません。
★目の健康を保つためには、定期的な目の検査が必要ですか?
白内障や緑内障など、目の病気は、見えにくくなっていても自覚しづらい。一方の目で、もう一方の目の見えにくさをカバーしてしまいますし、また視力低下が徐々に進んでいくため、見え方の変化に気づきにくいからです。本当は見えていないのに、脳が補ってしまい、見えているような錯覚を起こしているケースもあります。特に40歳を超えたら、眼科で定期的に目の検査を受けることをお勧めします。
★健康診断で目の検査があるのですが、それだけでは不十分ですか?
健康診断では、目の病気は見逃されやすい。視力検査しか行わない場合が多いからです。人間ドックを受けているから大丈夫と思っている人もいるかもしれません。しかし、必要な検査項目が入っていない可能性があります。受けるべき目の検査項目が入っているかを確認した方がいいでしょう。
視力検査以外で受けるべき目の検査は、まず眼圧検査。空気を目に噴射して、目の圧力を測定します。次に、眼底検査。黒目から黒目の奥に光を当て、眼底を直接見たり、カメラで撮影したりします。緑内障、網膜剥離、網膜色素変性症、黄斑変性などを見つけるための検査になります。この2つはぜひとも受けてください。
★老眼について教えてください。老眼は何歳くらいから始まるものなのでしょうか?
老眼は、40歳半ばくらいから始まります。40代以降で、手元が見えづらい、本や新聞の文字を読むと疲れる、夕方に物が見えにくくなる、細かいものが見づらい、肩こりや頭痛などの不調がある、という人は、老眼がすでに始まっている可能性があります。ただ、「老眼だから見えにくいんだ」と思って放置していると、先ほどから何度も触れているような目の病気が生じていることもあります。自己判断をせずに、眼科で検査を受けてください。
★老眼にならない方法はありますか?
歳を取らない方法がないのと同様に、老眼はだれしもに訪れます。ただ、老眼になりやすいかどうかは、生活習慣、体質、目の使い方、食生活などによって異なります。また、老眼はあるけども、生活にはさして不自由がないという人もいます。さらには、近年は遠方、中間、手元と3焦点にピントが合う白内障の眼内レンズが登場しており、白内障治療でこの眼内レンズを選択すると、老眼鏡がほぼ必要ないようになる人も少なくありません。
老眼ですが、外で紫外線をよく浴びる人、糖尿病などの生活習慣病がある人、同じ距離をじっと見続ける生活をしている人は、進行しやすいといわれています。パソコンやスマホをじっと見る生活が近視を増やしていると前述しましたが、その生活は、老眼にも影響を与えるかもしれないのです。
★スマホ老眼と老眼は同じですか?
スマホ老眼は、手元のスマホの画面をじっと見ることで、目のピント調節機能が正常に働かなくなった状態。見えづらさ、疲労感、頭痛、肩こりなどの不調が生じます。老眼は40歳以降に訪れますが、スマホ老眼は、若い人でも起こります。スマホを見るのをやめれば、スマホ老眼による不調は消えるでしょう。一方、老眼による見えづらさは、老眼鏡で解決するしかありません。
★老眼鏡は、老眼が進行するまで使いたくありません。
老眼鏡は「慣れ」が必要な道具。進行してから使うと、慣れるまでに時間がかかります。軽いうちから使うことを私はお勧めしています。
老眼鏡を使うと老眼が早く進むと考えている人もいます。しかし、老眼鏡は使っても使わなくても、老眼は進みます。進行のスピードは緩やかな人もいれば、速い人もいますが、老眼は必ず進むのです。人生100年時代、見えにくさを我慢して不調を抱えているなら、早く老眼鏡を使い出し、快適に「見える」日々を送った方がよくないでしょうか?
老眼鏡を作る際は、眼科で老眼鏡の処方箋を出してもらってください。その際、「何を見たくて老眼鏡を作るのか」を眼科医にしっかり伝えること。電車の中で文庫本を読みたいから老眼鏡を作る、仕事でパソコンを使うことが多いから老眼鏡を作る、ピアノを引くのが趣味で楽譜を見たいから老眼鏡を作る…など。老眼鏡を複数作ったり、距離の違う2箇所にピントを合わせられる多焦点レンズを作ったりする方が向いているケースもあります。
処方箋を出してもらったら、それを持ってメガネ屋さんに行くわけですが、メンテナンスをしっかりしてくれるメガネ屋さんを選んだ方がいいですよ。そしてメガネのチェックは、合わなくなったという実感がなくても、2年に1回くらいは行った方がいいです。どんなメガネでも、使っていれば劣化していきます。メガネを作り替えるときは、眼科で定期検診をかねてチェックすると、目の病気の有無も調べられるので、ベストです。