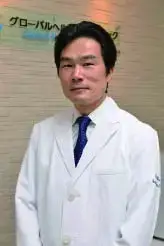目次
- はじめに
- Q1 世界で起きているアニサキス症(アニサキス属やシュードテラノーバ属に属する線虫が原因で発生する食中毒)の95%が日本で起こっているとも聞きます。どうしてでしょうか?
- ★どのようにしてアニサキス症になるのでしょうか?
- ★アニサキスが小腸まで到達し、腸閉塞を起こして緊急の開腹手術となったケースも耳にします。アニサキス症で手術にまで至るケースは珍しいのでしょうか。
- ★アニサキスで、魚介類全般が食べられなくなったというインタビュー記事を読んだことがあります。アニサキス症を起こすと、そのようになることがあるのでしょうか?
- ★アニサキス症の予防を教えてください。
- ★水野先生のクリニックでは2019年6月の開院以来、寄生虫関連の患者さんを多数診ているとのことですが、どういう疾患が多いのでしょうか?
- ★アニサキス症のように、激しい腹痛などが起こるのでしょうか?
- ★条虫といえば、テレビドラマ「ドクターX」でも観たことがあります。
- ★最近はジビエなども一般的になり、「レア」調理を食べられる機会が増えてきているように思います。寄生虫の感染などを避けるにはどうすればいいでしょうか?
- この記事を監修した医師
はじめに
アニサキスは、魚介類の寄生虫の一種。国立感染症研究所によるとアニサキス食中毒は増加傾向にあり、2013年の88件から、2023年には432件に増加した。アニサキスの食中毒が増えているのは、その存在が広く知られるようになったことに加え、輸送技術が発達し、魚を生で輸送できるようになったことが大きい。生で魚を輸送できる、すなわちアニサキスも生きたまま運ばれてしまうようになったのだ。アニサキスやその他の寄生虫について、日本感染症学会専門医で、特に寄生虫症の臨床と研究、海外渡航者の健康管理などに長年関わってきた「グローバルヘルスケアクリニック」院長の水野泰孝医師に聞いた。
Q1 世界で起きているアニサキス症(アニサキス属やシュードテラノーバ属に属する線虫が原因で発生する食中毒)の95%が日本で起こっているとも聞きます。どうしてでしょうか?
アニサキスはアニサキス亜科に属する線虫の総称です。体長2センチになるアニサキスの第3期幼虫が魚介類に寄生し、アニサキス症の病原体になります。
アニサキス症は、「魚介類の生食を避ける」、あるいは「加熱してから食べる」ことが確実な感染予防となります。また、冷凍処理するとアニサキスの幼虫は感染力を失うため、生食する場合は魚をいったん冷凍し、解凍後に食べることも感染予防に役立ちます。
言い換えれば、生で輸送された魚介類を、生のまま食べれば、季節を問わず、だれでも感染のリスクがあります。日本でアニサキス症の発生が多いのは、魚介類をお刺し身や寿司などで食べる「魚介類の生食文化」が根付いていることが挙げられます。
国立感染症研究所も、日本でのアニサキス症の症例が諸外国に比べて圧倒的多数であることを指摘しています。同研究所が33万人規模のレセプトデータ(医療機関が健康保険組合等に提出する診療報酬明細書)を用いて行った試算によると、日本国内でのアニサキス症の発生件数は、推計年間7147件※(2005年から2011年の年平均)。これに対し、海外での報告数は、オランダでアニサキス症の発生が報告された1960年から2005年までの45年間で、欧州で累計約500件、米国で累計約70件とされています。
★どのようにしてアニサキス症になるのでしょうか?
まずは、アニサキスの寄生のサイクルを紹介しましょう。
アニサキスは海中を浮遊しているところをオキアミが捕食し、そのオキアミをサバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどが捕食。そのサバなどをクジラが捕食。クジラの体内でアニサキスが卵を産み、その産んだ卵がフンと一緒にクジラから出され、海中でアニサキスがふ化。海中で浮遊しているアニサキスをオキアミが捕食し、サバなどがオキアミを捕食し…というサイクルを繰り返します。アニサキスはクジラの消化管で成虫になって卵を産むのであり、それまでは全部幼虫になります。
アニサキス症は、人間が、サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなど、アニサキスの幼虫が寄生している魚介類を、生食や加熱不足で食べることで起こります。アニサキスは人間のお腹の中では成虫にはならないので、ずっと居続けるわけではなく、一時的なものになります。食べて最速であれば数時間、遅ければ数日後に症状が出ます。
★アニサキスが小腸まで到達し、腸閉塞を起こして緊急の開腹手術となったケースも耳にします。アニサキス症で手術にまで至るケースは珍しいのでしょうか。

アニサキスは通常は胃液で死滅するため、ご指摘の通り、小腸まで至るケース、そして腸閉塞で手術にまで至るケースは非常に珍しいでしょう。
人間の体の中に入ったアニサキスの幼虫は、胃壁や腸壁に穿入し、食中毒を起こします。激しい上腹部痛、悪心、嘔吐で発症するのがアニサキス症の特徴です。何をどのように食べたかという問診と臨床症状からアニサキス症が疑われる場合、診断と治療を兼ねて胃内視鏡検査を行い、虫体が確認できれば摘出します(当院では、アニサキスの内視鏡検査等は行っていません)。アニサキスが体内に入っても無症状の方もいて、健康診断などの内視鏡検査で胃粘膜に穿入するアニサキスが見つかるケースもあります。
※内視鏡検査についての詳しい記事はこちら【医療ガイドブック「内視鏡検査とは?」】
★アニサキスで、魚介類全般が食べられなくなったというインタビュー記事を読んだことがあります。アニサキス症を起こすと、そのようになることがあるのでしょうか?
アニサキス症は、魚介類を生食や加熱不足で食べ、魚介類に含まれる生きたままのアニサキスが体内に入ることで、激しい腹痛や吐き気が起こるもの。アニサキスが含まれていない魚介類では起こりませんし、十分な加熱や冷凍でアニサキスが死滅していれば、アニサキス症を起こしません。つまり、魚介類全般を食べられなくなるわけではありません。また、アニサキスを内視鏡で摘出すれば、症状は治ります。たとえ内視鏡摘出を行わなくても、アニサキスは人間の体内では成虫にならないので、死滅すれば症状は数日間で治ります(ただし、激痛を数日間我慢するということになります)。
一方、アニサキスアレルギーという疾患があります。その名の通り、アレルギーの一種です。アニサキスをアレルゲンとし、アレルギー反応が起こるのです。症状はアニサキス症とは異なり、じんましん、喘鳴、呼吸困難、腹痛、嘔吐、下痢、血圧低下、意識障害などのアナフィラキシー症状。アナフィラキシーショックを起こせば、命に関わります。
このアニサキスアレルギーは、アニサキスの抗体に反応して発症するため、生きているアニサキスだけではなく、アニサキスの死骸やカケラでも起こります。アニサキスはほとんどの魚介類に寄生しているため、ほとんどの魚介類が調理法を問わず食べられなくなります。刺し身、焼き魚、煮魚、干物、練り物、魚介類の缶詰、魚で取っただし汁、だしじょうゆ、めんつゆ、魚介エキスが入った加工食品、カツオエキスが入っているせんべい、オキアミが入っているキムチ、魚介のだしが入っているラーメンやそば・うどん、アンチョビ…。食生活がかなり制限されてしまいます。
★アニサキス症の予防を教えてください。
前述の通り、魚介類の生食を避ける。60℃で1分以上加熱してから食べる。生食の場合は、マイナス20℃で24時間以上冷凍処理をした魚介類を選ぶ。魚介類の内臓はすぐ取り除き、生では食べない。目視も重要で、目で見て発見したら除去する。料理で使う程度のしょうゆ、わさび、酢では、アニサキスは予防できません。
★水野先生のクリニックでは2019年6月の開院以来、寄生虫関連の患者さんを多数診ているとのことですが、どういう疾患が多いのでしょうか?
2019年6月から2020年5月までの1年間に受診した患者さん1315名のうち、感染症内科を希望して受診した患者さんは368名。主訴が寄生虫関連だった患者さんは184名でした。当院ホームページに寄生虫症の項目が詳細に書かれてあるからか多くの方が受診されています。
中でも最も多いのが、日本海裂頭条虫、いわゆるサナダムシです。サケやマスの筋肉内にサナダムシの幼虫が寄生しており、アニサキス症と同様に条虫症は、お刺身や寿司をよく食べる日本人にはよくみられます。
★アニサキス症のように、激しい腹痛などが起こるのでしょうか?
条虫症の多くは感染しても無症状。感染後、数カ月程度で虫体の一部が切れて便と一緒に排泄されます。無症状ではあるものの、患者さんは、お尻から紐のようなものが出てくるので驚いて受診されます。治療は、プラジカンテルという錠剤を1回内服すれば終了なのですが、問題は、その薬を常備している医療機関が少ないこと、寄生虫症を的確に診断できる医師が少ないので、異なった薬が処方される場合があることです。お尻から出てくるので患者さんは消化器科を受診することが多いようですが、受診した医療機関が大病院であっても、適切な治療を受けられるとは限りません。
★条虫といえば、テレビドラマ「ドクターX」でも観たことがあります。
日本将棋界屈指の若手棋士がAI棋士との電脳戦の最中に痙攣を起こして倒れてしまう、という回ですね。頭部造影CTを撮ったところ、脳内にリング状の造影効果を呈する円形の病変があり、脳腫瘍ではないかと考えられました。しかし、米倉涼子さん演じる大門先生は、若手棋士は豚肉好きで、海外で生の豚肉をよく食べていた経験を聞き出し、皮膚に小さなコブができていたことから、有鉤条虫感染による脳有鉤嚢虫症と診断し、虫体を手術で摘出するという内容でした。
サケやマスに含まれるサナダムシは体内に入っても無症状です。一方、条虫の一種である有鉤条虫は豚に含まれていて、人間の体内に入ると体の中を動き回り、ふ化し、脳に移動すると脳有鉤嚢虫症といった深刻な病気を起こす可能性があります。豚肉の生、加熱不足で起こるのですが、ただし、日本では有鉤条虫の症例報告はほぼない。日本国内で豚肉を食べている限り、また海外でも豚肉をしっかり調理して食べている限り、心配する必要はないでしょう。
★最近はジビエなども一般的になり、「レア」調理を食べられる機会が増えてきているように思います。寄生虫の感染などを避けるにはどうすればいいでしょうか?
何を食べたか。どれだけ食べたか。寄生虫の感染は、これが最も大事です。ドラマでもそうですが、SNSなどで寄生虫のことを知り、心配されて来院される方がいます。
しかし、食べた経験がなければ、絶対に感染はしない。感染を避けるには、食べない。食べる量を少なくする。寄生虫でもウイルスでも、それが死滅する調理法をしっかり守って食べる。これに尽きます。
※編集部注:食中毒が疑われる場合、医師は確定診断を待つことなく直ちに保健所へ届け出る必要があるため、この数値は厚生労働省が発表している「アニキサス食中毒の発生件数」とは異なります。