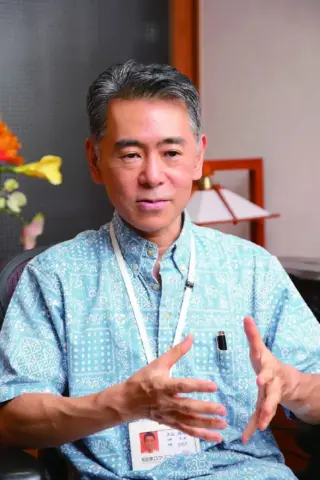目次
はじめに
お酒を飲む機会が増えるときにこそ、注意したい„痛風"。痛風は、高カロリー・高脂肪の食生活をしている人、肥満の人、アルコールを取り過ぎている人、激しい運動を日々している人、ストレスが強い人ほど、リスクが高くなります。今号では、痛風の患者さんの治療に専念し、またほかの重大病の予防につなげている両国東口クリニックの大山博司理事長にお話を伺いました。
Q1 痛風はどのような病気でしょうか?
「尿酸」という言葉を聞いたことがありますか? これは、「プリン体」という物質から生産されるもの。細胞の新陳代謝やエネルギーの利用によって生じるので、「体の老廃物」とよく言われます。
尿酸は腎臓に運ばれ、多くが尿と一緒に体外に排出されます。しかし、過剰に尿酸が作られると、水に溶けにくい性質のため結晶化し、関節や関節周辺に沈着していきます。尿酸の結晶は本来、体内にないもの。ですから、白血球が「異物」と判断して攻撃します。これによって炎症が起こり、激しい痛みが生じます。
血中の尿酸の量を示す血清尿酸値が7㎎/㎗を超えると、結晶化し、関節や関節周辺に沈着することが分かっています。尿酸値が高い状態をすべて「痛風」と呼ぶと考えている方が多いですが、正確には、尿酸値が高い状態(7㎎/㎗超)を「高尿酸血症」と呼び、痛風発作が出た後を「痛風」と呼びます。
Q2 症状について教えてください。
関節や関節周辺に痛みが生じます。「風が吹いても痛いことから痛風」と言われるように、非常に激しい痛みが特徴。炎症による痛みなので、患部が真っ赤に腫れ上がります。ただし、人によっては痛みや腫れの程度がそれほど大きくなく、最初の発作を「筋肉痛だと思った」とおっしゃる方もいます。
Q3 症状が出やすい場所はどこですか?

関節や関節周辺です。頻度が高いのは、足の親指付け根や足首、かかとなどです。
高尿酸血症・痛風の専門医として多数の患者さんを診ている中で感じたのは、「意外な場所」に発作を生じる方もいる、ということです。膝、肘、手首、手の指などです。これらも関節なので、尿酸の結晶がたまりやすい場所であることは確かですが、「痛風=足の親指付け根や足首、かかとなどの激しい痛み」というイメージがどうしても強い。痛風患者さんをあまり診ていない医師では、別の病気と間違えてしまうケースもあると聞きます。
Q4 痛風発作を起こしたら、どのような治療が行われますか? 市販の鎮痛薬で痛みを抑えてもいいのでしょうか?
痛風発作は夜中から明け方にかけて起こりやすくなります。発作が起きたら、まずは氷水などで患部を冷やします。心臓より高い位置にし、安静にしてください。痛風の痛みは炎症症状なので、マッサージなどをすると痛みが悪化します。
市販の鎮痛薬は場合によっては効くこともありますが、アスピリン系などは炎症を長引かせることもあります。やはりベストは、自己判断で薬を服用せず、医療機関を受診することでしょう。医療機関では炎症を抑える治療をまず行い、炎症が治まり痛みが消えてから、その人に応じた尿酸降下薬を使った薬物治療になります。
次に挙げるのは、絶対に避けていただきたいことです。特に初めての発作を起こした人によく見られる「勘違い」なので、気をつけてください。
これまで尿酸降下薬を飲んだことがない人、しばらく飲んでいない人が、発作が起きた時に、だれかから薬をもらい、服用すると症状悪化の原因になります。尿酸値が急激に低下し、関節内の尿酸の結晶の溶解が進んで不安定な状態になります。そのため白血球の攻撃が起こりやすくなって、痛風発作をさらに引き起こしたり、長引かせたりするのです。
尿酸降下薬を飲んでいる人が、発作時に、通常量より多く薬を飲むとやはり症状悪化の原因になり、痛みが増したり、症状が長引いたりしますので、普段から尿酸降下薬を飲んでいる方は、そのまま同じ量で飲み続けて下さい。
Q5 痛風発作を起こしやすい尿酸値は?
7㎎/㎗を超えると高尿酸血症と診断されますが、実際のところ、7㎎/㎗で痛風発作を起こす人はあまり多くありません。対策は生活習慣の改善が中心になります。しかし、8㎎/㎗、9㎎/㎗と高くなるにつれ、発症の率は確実に高くなります。
Q6 リスクが高い人は?
高カロリー・高脂肪の食生活をしている人、肥満の人、アルコールを取り過ぎている人、激しい運動を日々している人、ストレスが強い人です。該当することが多いほど、リスクが高くなります。
よく「ビールをよく飲むから尿酸値が高い。痛風対策のために、ビールをやめて焼酎にした」とおっしゃる方がいます。確かにビールには、尿酸のもとになるプリン体が多く含まれています。
しかし実は、アルコールそのものが痛風に悪影響を与えるのです。アルコールがプリン体を増加させ、さらに尿酸値の排泄量を低下させるからです。「ビールを」というよりも、「アルコール全般を」控えめにしてください。
Q7 女性はならない病気ですか?
高尿酸血症・痛風は、圧倒的に男性に多い病気です。女性にも見られますが、痛風発作を起こすような方は非常にまれです。
しかし、安心してはいけません。尿酸値が高い状態が続くと、慢性腎臓病、心筋梗塞、脳血管障害、動脈硬化、尿路結石などの合併症を起こしやすくなります。このうち尿路結石以外の血管のダメージによる合併症は、女性の方が男性より低い数値で起こしやすいという報告があるのです。尿酸血の基準値は前出の通り7㎎/㎗ですが、女性の合併症に関しては、6㎎/㎗台でもリスクが高いといわれています。
Q8 治療をせずに放置すると、どうなりますか?
Q7で挙げた合併症を起こしやすくなります。
私は高尿酸血症・痛風を、「生活習慣病のうち、最初の方に出てくる病気」だと考えています。生活習慣病の原因は、肥満、塩分や脂肪の取り過ぎ、運動不足、アルコールの過剰摂取、不規則な生活、ストレスなどです。それらによって、糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病を発症するわけですが、高尿酸血症・痛風は、比較的早い段階で出てくる。つまり、高尿酸血症・痛風の治療をきちんと行うことで、そのほかの生活習慣病の発症を食い止めることにもなる。ひいては、心筋梗塞、脳卒中といった死を招く病気の予防にもなる。そう考えているのです。
Q9 完治は可能でしょうか?
もちろん可能です。薬を服用し、生活習慣を徹底して改善して、薬をやめられた患者さんもいらっしゃいます。
「完治」というわけではありませんが、痛風はコントロールをしやすい病気。薬と生活習慣の改善によって、痛風を再発せず、一生うまく付き合っていくことは十分に可能です。
Q10 両親のどちらか、あるいは一方が高尿酸値血症・痛風の場合、発症リスクは高くなりますか?
高尿酸血症・痛風は、遺伝に関連がある病気です。ただ、家系に患者がいたからといって、自分も発症すると考えず、尿酸値を上げない生活を送ること。それによって、発症は抑えられます。
尿酸値を上げない、高尿酸血症・痛風にならない生活とは、「あれもダメ これもダメ」というものではありません。
たとえば、アンキモやシラコなどはプリン体が多い食品ですが、毎食たくさん食べる人はあまりいないでしょう。時々、少し食べる程度なら問題ありません。お酒も同じです。飲みすぎないことが肝心。ほかの病気の予防にも通じる規則正しい生活を心掛けてください。
Q11 先生の美学を教えてください。
大学では痛風を含めて尿酸・核酸についての研究を行っていました。臨床では糖尿病などを含めた内科全般の病気を診ていたのですが、ある時から高尿酸血症・痛風の患者さんを専門に診るようになりました。きっかけは、クリニック(両国東口クリニック)のホームページに高尿酸血症・痛風の相談を受けるサイトを設けたこと。すると、「痛風を発症したけれど、どの科を受診していいか分からない」「痛風対策のためにはビールはやめたほうがいいのか?」「薬をやめるにはどうすればいいのか?」など、さまざまな相談が寄せられたのです。その時感じたのは、「高尿酸血症・痛風の患者さんは多いけれど、専門医は少ない。患者さんたちの悩みに応えたい」ということ。そこで、高尿酸血症・痛風の専門医として再スタートを切ることにしました。
専門医として多くの患者さんを診ることで、新たな発見もありました。たとえば、医学の教科書では「足の指などに発作が起こる例が多い」とありますが、指や肘、手首に痛風発作を起こした患者さんもいらっしゃいます。そういった発見は経験として蓄積され、患者さんへフィードバックされます。結果的によりよい医療ができるのです。
痛風の治療が、ほかの重大病の予防につながる。常に最新の知識を持って患者さんに向き合うことが私の美学です。