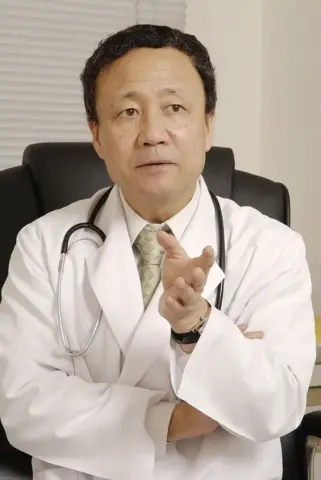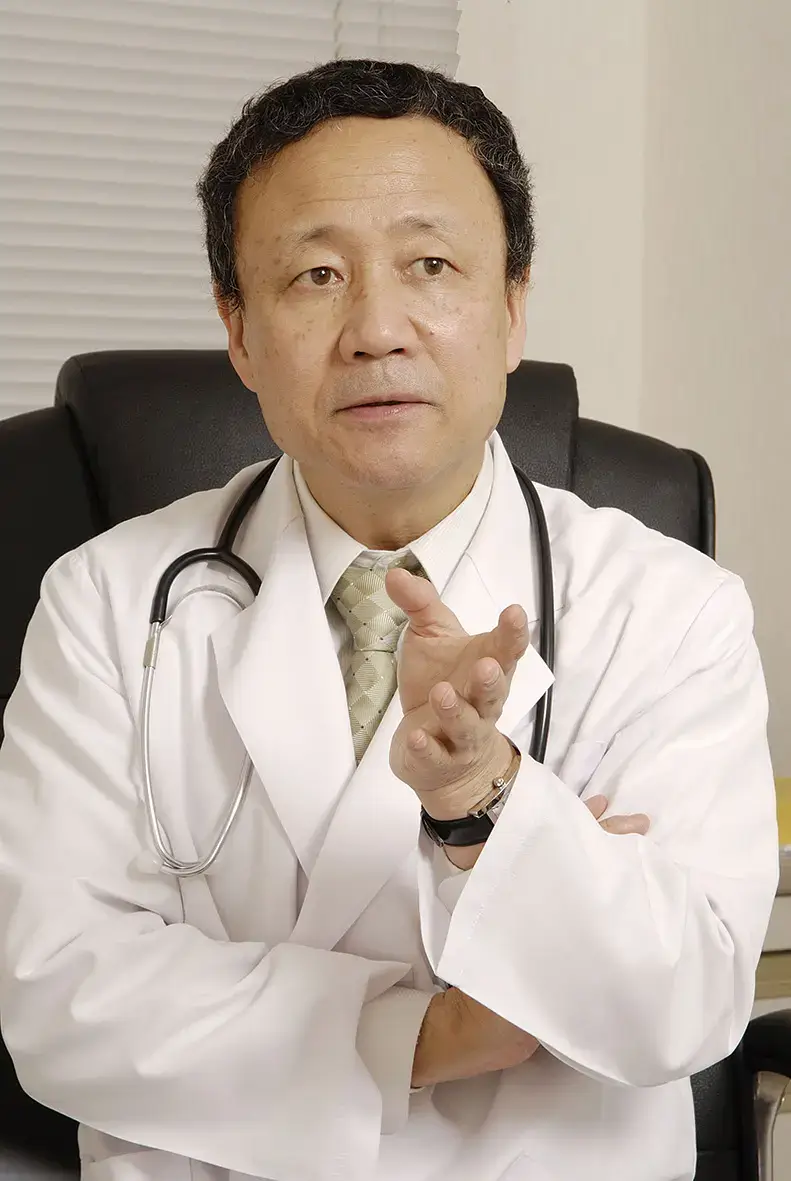目次
はじめに
皆さんは、自分の体温を知っていますか?
「冷え」はあらゆる病気の原因に深く関係しています。いかに「健康体」の体温、36.5度を維持するかが、病気のリスクを低くするコツとなります。
今回は、数多くのマスコミに登場し、また著書で知られるイシハラクリニックの院長、石原結實先生にお話をお伺いしました。
Q「冷え」は体によくないですか?
「葛根湯医者」という落語をご存知でしょうか? 患者が「風邪をひいた」とやって来たら「それなら葛根湯」、「下痢をした」という患者さんにも「それなら葛根湯」、「湿疹ができて痒い!」という患者さんにも「やっぱり葛根湯」。どんな症状にも葛根湯しか処方しない、でもそれで十分に病気を治せている医者を取り上げたのが「葛根湯医者」です。
葛根湯は、葛の根、麻黄、生姜、大棗、芍薬、桂枝、甘草など体を温める生薬で構成されています。確かに葛根湯を飲むと、20分ほどで体が温まってきます。そして、風邪、肩凝り、頭痛、下痢、湿疹、ジンマシンなどがよくなってくる。漢方の専門書を読むと、葛根湯が効く病名は、風邪、気管支炎、肺炎、扁桃炎、結膜炎、口内炎、蓄膿症、はしか、五十肩、湿疹、ジンマシン、高血圧などなど、実に様々です。
どうして葛根湯は、幅広い症状に効果があるのでしょうか? 注目すべき点は「温める」です。葛根湯が様々な症状に効果があるのは、体を温めて冷えを改善するから。だから「すべてにOK」とまではいかないにしろ、多くの病気に効くのです。
ヒトは熱帯に発生したと推測されていて、そのため動物のような体毛がないと考えられています。だから、暑さに耐えるための体温調節器官はありますが、寒さに対する特別な機能は持っていない。ちょっとした生活習慣の変化でも体が冷え、そして「冷え」に弱く、冷えると病気にかかりやすくなる。ほとんどの病気の死亡率が冬に上昇し、健康な人でも体温が低い起床後すぐはボーッとしていて体が思うように動かなかったりするのは、体温の変化が大きく関係しています。
本来、人間が最もよく働ける体温は36.5度〜37度の体温です。ところが現代人は、36.5度未満の体温が「普通」です。糖尿病や高血圧などの生活習慣病、うつ病、脳卒中、心筋梗塞、がんといったあらゆる病気が増加傾向にあるのは、「冷え」で「ベスト体温」が保てないことと無関係でない。冷えは体によくない。これははっきりいえることです。
Q体温が下がるとどんな症状が現われますか?

体温が1度下がると免疫力が30数パーセント下がります。つまり、それだけ病気にかかりやすくなります。
もっと具体的に見ていきましょう。前述の通り、36.5度が健康体で免疫力が旺盛な状態です。36度になるとふるえて熱産生を増加させようと体が働きます。35.5度が続くと排泄機能が低下して便秘や下痢に。自律神経失調症やアレルギー症状が出てきます。
35度はがん細胞が最も増殖する体温です。34度は水におぼれて救出された人が生命維持できるかギリギリの体温。33度は冬山での凍死寸前の体温、30度で意識消失、29度で瞳孔拡大、27度以下で死体の体温……。
病気のリスクが低く、意欲的に活動できる「健康体」でいようと思ったら、いかに体温を維持することが大切かお分かりでしょうか?
Q体が冷える原因はどういうものでしょうか?
私は常々、患者さんに次のような原因があると話しています。
①筋肉不足
体のどこから熱が生まれるかというと、安静時の部位別産熱量で一番多いのは骨格筋(筋肉)で全体の約22%です。体を動かすと筋肉の産熱量はもっと多くなり、筋肉質の人の場合では80%近くまで上昇します。
つまり、筋肉が少ないと産熱量がそもそも少なく、さらに運動不足の人はより産熱量が少なくなります。
②冷房と、1年中の「夏型の暮らし」
現代社会では、夏、どこにいっても冷房が利きすぎるくらい利いています。本来、熱い夏は人間の体の基礎代謝が低下し、産熱しにくい状態にあります。それなのに冷房で体を冷やせば、より冷えた体になっても仕方ないでしょう。
また、キュウリ、ナス、トマト、アイスクリーム、ビール、氷菓子、そうめん、冷麦、氷を浮かべた冷たい飲料などは、体を冷やすために夏に取られていたもの。でも今では1年を通して食べたり飲んだりすることができます。「夏型生活」が1年中可能、ということ。これも「冷え」を招く原因になります。
③ストレス
ストレスがかかると、緊張のホルモンであるアドレナリンやノルアドレナリンの分泌が高まり、血管が収縮して血行が悪くなります。そして体温が低下してくる。ストレス社会である現代は、冷え社会でもあるのです。
④入浴法
冬でも湯舟につからずシャワーで済ませるという人が、特に若い世代や1人暮らしに多く見られます。
湯舟にきちんと入ると、全身の血流がよくなって、全臓器、細胞の代謝を促進させて体熱を上昇させます。発汗や排尿を増やして、冷えの一因である体内の余分な水分を排泄し、さらなる体温上昇も促してくれます。シャワーだけで済ませるのは、体を温める機会をみすみす逃していることになります。
⑤食べ方の間違い
まず、食べ過ぎがよくありません。食物を消化するために、胃腸の壁に多量の血液が配給され胃腸を働かせるからです。そして筋肉をはじめ胃腸以外の器官や細胞への血液供給量が低下し、栄養や酸素、水、白血球、免疫物質などが十分に運ばれずに働きが落ち、体熱の産生が減るのです。よって体熱が低下します。
体を冷やす食べ物を日常的にとるのも問題です。①で、本来は夏に食べられていた食品、飲料が1年中食べられるようになったことが、冷えの原因になっているとお話しました。それ以外にも、白砂糖、化学調味料、バター、パン、マヨネーズ、クリーム、脂肪、薬などは体を冷やす方向に働きます。
健康維持のために減塩に努め、水分を多く摂ることを心がけている人もいることでしょう。しかし実は、これらの「健康法」も、体を冷やす原因になります。塩分摂取の多さを指摘される東北の人々が、どうして塩分を多量に取ってきたかというと、暖房が十分でない厳寒の冬を乗り切るため。塩分には体を温める作用があるからです。
また、水、冷え、そして痛みは相互関係にあります。寝冷えすると下痢(水様便)をする、冷房に入ると頭痛が起こる、雨が降ると腰痛や神経痛がひどくなる、という人がいることを考えるとよく理解できます。体内で「水」が増えれば、冷え、痛みを引き起こしやすくなります。
ちなみに、体内に余分な水分がたまり、排泄できない状態を東洋医学では「水毒」といい、体の不調の原因になると考えます。これらのことから、心の底から本当に水を飲みたければ別ですが、飲みたくないのに「健康のために」と水分をせっせと飲むのは、東洋医学の観点からするとナンセンス。生命にとって大切な水ですが、多すぎると排泄し切れず、不調を招くのですから。
Q男性も「冷え」ですか?
女性より男性のほうが筋肉量が多いので、男性は冷えを感じにくいです。だから「オレは冷え性じゃない」と思われている人が多いですが、自覚なくても、冷えている場合があります。
体温は何度でしょうか? 36.5度未満なら間違いなく「冷え」です。前の項目で挙げた「冷える原因」に一つでも該当すれば、やはり「冷え」。汗のかき方もチェック項目になり、運動をしていなくてもやたらと汗をかく、食事をしただけで汗がダラダラ流れる、という人は、冷えの原因になる「水」が体内にたまり過ぎている、つまり「冷え」である、と考えた方がいいでしょう。
Q体を温めるにはどうすればいいですか?
もうお分かりですね? 冷える原因とは別のことをするといいのです。しっかり運動をし、夏の冷房漬けを避け、体を冷やす食品は取らない。毎日湯舟につかって体を温めるのと同時に心身ともにリラックスさせ、間違った食生活を改める。
私は76歳で、40年近く薬を一切飲んでいませんし、病気を全くしていません。伊豆の保養所と東京のクリニックを行ったり来たりし、講演や執筆活動などで忙しい日々を送っていますが、気力体力ともに絶好調です。疲れを感じません。
その秘訣は、冷えない生活、体を温める生活を送っていることにあります。私が食事を摂るのは1日1食、夜だけ。朝は人参ジュースと黒砂糖と生姜を入れた紅茶、昼も生姜紅茶、夜はたとえばご飯、納豆、味噌汁、イカの炒め物、タコの刺身など。ビールは1杯だけ飲みますが、後は焼酎お湯割りです。そして、週に2〜3回50〜100キロのベンチプレスを持ち上げ、ジョギングをやります。肉もバターも牛乳も取りません。イカやタコは食べますが魚は食べない。寝る前には湯舟にしっかりつかりますし、無理せず自分の信念のままに過ごす生活ですのでストレスもない。これらはすべて「冷えない」に作用しています。
Q美学について教えてください。
「和して同ぜず、決して群れない」が私の美学。長崎大学を卒業して上京して以降、どこの団体にも所属せず、自分が信じるままにやってきました。
大学卒業後の専攻は血液内科。その後、長寿地域として有名なコーカサス地方やスイスのB・ベンナー病院などで最前線の自然療法を研究し、「体を温めれば病気は改善する」という考えで治療に当たってきました。別の考えを持つ人も、もちろんいるでしょう。それを否定はしません。でも、体を温めることで長年の不調が改善され、お元気になられた方も多数いらっしゃいます。私の食事療法を実践する伊豆の保養所に毎年何千人という方が訪れているのも、それを裏付けているでしょう。
これからも「群れず」をモットーに、治療にあたっていこうと考えています。