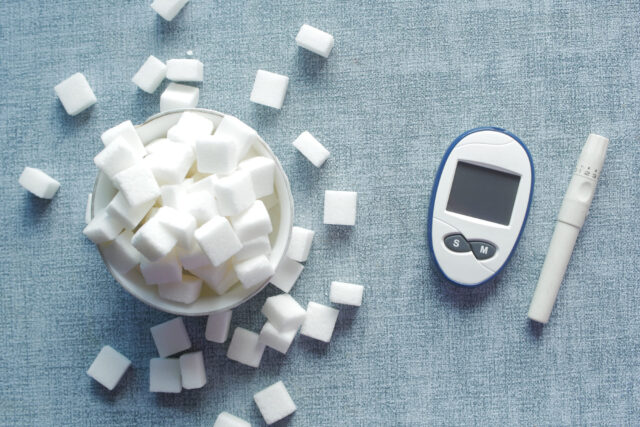毎年冬が近づくと流行するインフルエンザを「ただの風邪?」と軽く考えてしまいがちな方も少なくありません。インフルエンザは突然の高熱や動けなくなるほどの倦怠感が特徴で、特に高齢者や乳幼児、基礎疾患がある方は重症化するリスクも潜んでいます。
COVID-19の流行期には一時的に患者数が減少しましたが、近年はインフルエンザの流行が再燃し、2024-2025シーズンではここ5年間で感染者が多く活動が再び活発化しています。ある研究では、流行後に入院した子どもは以前より咳などの症状が強くなる気管支過敏性の発症や肺炎などの傾向も報告されており、これまで以上の対策が必要です。(※1)
この記事では、インフルエンザ予防接種の知識や、日常生活で実践できる具体的な感染対策を解説します。正しい知識で、あなたと大切な家族をインフルエンザから守りましょう。
インフルエンザとは?
インフルエンザは、インフルエンザウイルスが引き起こす急性の呼吸器感染症です。毎年、空気が乾燥するにつれて流行し始め、多くの人が高熱や体の痛みなどの症状に悩まされます。
インフルエンザと普通の風邪との大きな違いは、以下のとおりです。
| 項目 | インフルエンザ | 普通の風邪 |
|---|---|---|
| 発症 | 突然、急激に始まる | 比較的ゆるやかに始まる |
| 発熱 | 38℃以上の高熱が多い | 微熱から軽度の発熱のことが多い |
| 全身症状 | 強い(悪寒、頭痛、関節痛、筋肉痛) | 軽い場合が多い |
| 合併症 | 肺炎、脳症など重症化することがある | ウイルスによるが肺炎なども生じる |
インフルエンザの原因となる主なウイルスにはA型とB型があります。特にA型は2パターンがあり、ウイルスの表面の形を少しずつ変えるため、過去に感染して免疫があっても、新しい形のウイルスに対抗できず、毎年流行を繰り返します。
COVID-19の流行以降、流行前よりインフルエンザによる咳などの症状が強まっている傾向が報告されています。症状の重症化に伴い、入院期間も長くなっているため、インフルエンザの感染予防は重要です。(※1)
インフルエンザ予防接種の5つの基礎知識
インフルエンザの発症を防ぐには、予防接種を行うことが大切です。ここでは、以下のワクチン接種の5つの基礎知識を解説します。
①インフルエンザ予防接種の効果と持続期間
②接種に適した時期と費用の目安
③ワクチン接種後の副反応と正しい対処法
④子ども・高齢者・妊婦が接種する際の注意点
⑤新型コロナワクチンとの同時接種が可能
①インフルエンザ予防接種の効果と持続期間
インフルエンザ予防接種の効果の一つが、感染後の重症化を防ぐことです。
インフルエンザの予防接種をすると、体内でウイルスに対抗する力(抗体)が作られます。抗体があるおかげで、感染しても症状が軽く済んだり、肺炎や脳症などの命に関わる合併症を防いだりする効果が期待できます。
予防接種の効果は重症化の防止だけではありません。予防接種をすることで発症の予防効果があることも報告されています。(※2)
予防接種の効果は、接種後約2週間で現れ始め、およそ5か月間持続すると考えられています。インフルエンザウイルスは毎年少しずつ姿を変えて流行するため、一度得た免疫が翌年も有効とは限りません。その年の流行を予測して作られたワクチンを、毎年接種することが大切です。近年では2歳から18歳を対象に、経鼻ワクチン(フルミスト)が認可され、こちらは発症予防は6から12か月と長期となっております。
②接種に適した時期と費用の目安
インフルエンザの予防接種は、流行が本格化する前の10〜12月中旬までに終えるのが理想的です。日本のインフルエンザ流行は、例年12月下旬から始まり、1〜2月にピークを迎えますが、近年では早期になる傾向があります。流行のピークに間に合わせるためには、早めの準備が肝心です。
インフルエンザの皮下注射での予防接種は保険適用外のため、費用は医療機関によって異なり、一般的には3,000〜5,000円程度が目安です。お住まいの自治体によっては、公的な費用助成を受けられる場合があります。点鼻ワクチンでは8000円程度です。
高齢者の方は、特にインフルエンザの重症化リスクが高いため、接種が強く推奨されています。65歳以上であれば助成対象となりますので、費用など助成制度に該当するかお住まいの市区町村のホームページなどでご確認ください。
③ワクチン接種後の副反応と正しい対処法
インフルエンザの予防接種により抗体が作られる過程で、一時的に副反応が起こることがあります。副反応は、体がウイルスと戦う準備を始めた正常なサインでもあります。多くの場合は数日で自然に軽快するため、過度に心配する必要はありません。
インフルエンザワクチンの副反応へは、以下のような対処方法があります。
| 主な副反応 | 対処方法 |
|---|---|
| 接種部位の赤み・腫れ・痛み | 濡れタオルなどで冷やすと症状が和らぐことがある |
| 発熱・頭痛・だるさ |
|
| 関節痛・筋肉痛 | 安静を心がける |
予防接種後30分以内に強いアレルギー反応(アナフィラキシー)が起こる可能性があります。アナフィラキシーは、息苦しさやじんましん、意識が遠のくなどの症状が特徴です。
万が一に備え、接種後30分程度は医療機関内やその近くで安静に過ごし、様子を見ることが重要です。帰宅後に普段と違うつらい症状が続く場合も、接種した医療機関へご相談ください。
④子ども・高齢者・妊婦が接種する際の注意点
以下のような方は、インフルエンザが重症化しやすいため、予防接種が推奨されます。
| 対象者 | 注意点 |
|---|---|
| 13歳未満の子ども |
|
| 高齢者 |
|
| 妊婦 |
|
母体由来の抗体は、予防接種をできない生後6か月未満の赤ちゃんをインフルエンザから守る効果も期待できます。さまざまな要因で免疫力が低下するため、注意点を把握したうえで、適切に予防接種を受けましょう。
⑤新型コロナワクチンとの同時接種が可能
インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンは、同じ日に接種できます。以前は2週間以上の間隔をあける必要がありましたが、2025年現在は問題ありません。
接種する際は、左右の腕に1本ずつ打つことが一般的です。発熱や腕の痛みなど、両方のワクチンによる副反応が起こる可能性がある点には注意してください。
同時接種のメリットは、医療機関への受診が一度で済むことです。同時に接種しても、それぞれの副反応が特別強くなるという報告もありません。ご自身の体調やスケジュールに合わせて、医師と相談しながら最適なタイミングを決めましょう。
日常生活でできるインフルエンザ感染予防対策4つ
予防接種に加え、日々の生活の中で感染対策を実践することが、ご自身と大切なご家族をインフルエンザから守るための鍵です。
今日からすぐに始められる感染予防対策として、以下の4つを紹介します。
①手洗い・マスク・アルコール消毒
②室内の湿度管理と換気
③適切な食事・睡眠・運動
④最新の流行状況の確認
①手洗い・マスク・アルコール消毒

インフルエンザをはじめとした感染症対策の基本は、ウイルスを体内に侵入させないことです。以下の表に感染症対策のポイントをまとめました。
| 対策 | ポイント |
|---|---|
| 手洗い |
|
| マスクの着用 |
|
| アルコール消毒 |
|
ウイルスは、ドアノブや電車のつり革など、さまざまな場所に付着しています。ウイルスの体内への侵入を防ぐために、正しい対策を行いましょう。
②室内の湿度管理と換気
インフルエンザウイルスは、低温で乾燥した環境を好むため、適切な湿度管理と定期的な換気を行うことが感染予防に重要です。
空気が乾燥すると、のどや鼻の粘膜も乾き、ウイルスの侵入を防ぐバリア機能が低下します。加湿器を置いたり、濡れたタオルや洗濯物を室内に干したりし、湿度を50〜60%に保ってください。湿度計を室内に置き、こまめに確認することが大切です。
定期的に室内の換気も行いましょう。1時間に1〜2回窓を開け、数分程度放置することがおすすめです。対角線にある2か所の窓を開けて空気の通り道を作ると、効率良く換気ができます。
③適切な食事・睡眠・運動
インフルエンザウイルスに負けない体を作るには、体の内側から免疫力を高めることが欠かせません。免疫力とは、体に備わっている病原体から身を守る防御システムのことです。
免疫力を高めるために、以下の生活習慣を取り入れてみましょう。
| 生活習慣 | 具体例 |
|---|---|
| バランスの良い食事 |
|
| 十分な睡眠 |
|
| 適度な運動 |
|
無理のない範囲で楽しみながら続けられる習慣を取り入れ、免疫力を高めていきましょう。激しすぎる運動は免疫力を下げることがあるので、注意してください。
④最新の流行状況の確認
インフルエンザは、毎年流行するウイルスの型や時期が異なるので、自分が住んでいる地域の流行状況を知ることは、感染対策につながります。
以下の情報源から、最新のインフルエンザ流行状況を確認してください。
| 情報源 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 国立感染症研究所感染症疫学センター | インフルエンザ流行レベルマップで、全国の流行状況を地図上で色分け |
| 厚生労働省 | インフルエンザ定点報告情報で、毎週の患者報告数が更新 |
| お住まいの自治体のWebサイト、衛生研究所のデータ | 地域の保健所などが身近な流行状況や注意喚起を提示 |
これらの信頼できる情報源を定期的に確認し、日々の感染対策に役立てましょう。
インフルエンザにかかった後の対処法

インフルエンザと診断された時は、早めに医療機関を受診し、抗インフルエンザ薬を服用しましょう。発症から48時間以内に抗インフルエンザ薬を使い始めると、発熱期間を短くするなどの効果が期待できます。(※3)
症状が現れている間は安静にすることが重要です。無理に動かず、体を横にして休むことで、免疫が働きやすい環境を整えられます。
高熱で汗をかくと、思った以上に体の水分が失われ、脱水症状に陥る危険があります。経口補水液やスポーツドリンク、麦茶などで、こまめに水分を補給してください。
また以下のような症状が見られる場合は、重症化の可能性があるため注意が必要です。
- 呼吸が速く、息苦しさを感じる
- 意識がもうろうとしている
- けいれん
- 顔色が悪い
- 嘔吐や下痢が続いている
- 症状が長引き悪化してきた
学校保健安全法の基準では、学校がある子どもは、発症後5日かつ解熱後2日経過するまで通学してはいけません。(※4)大人でも、子どもと同じくらいの期間は出勤を避けましょう。
まとめ
インフルエンザ対策で大切なのは、予防接種と日々の感染対策を組み合わせることです。予防接種は、感染を100%防ぐ効果はありませんが、万が一かかってしまった際の肺炎や脳症などの重症化を防ぐ手段の一つです。
予防接種とあわせて、こまめな手洗いや適切な湿度管理、バランスの良い食事や十分な睡眠を心がけることが大事です。
自分と大切な家族をインフルエンザの流行から守るために、正しい知識でしっかりと備えましょう。もし体調に異変を感じたら、無理をせず早めに医療機関に相談してください。
参考文献
- Lin F, Liang JL, Guan ZX, Wu M, Yang LY. “Hospitalized children with influenza A before, during and after COVID-19 pandemic: a retrospective cohort study.” BMC pediatrics 24, no. 1 (2024): 828.
- Aye Moa, Mohana Kunasekaran, Zubair Akhtar, Valentina Costantino, C Raina MacIntyre.Systematic review of influenza vaccine effectiveness against laboratory-confirmed influenza among older adults living in aged care facilities.Human Vaccines & Immunotherapeutics,2023,19(3),2271304.
- F Y Aoki, M D Macleod, P Paggiaro, O Carewicz, A El Sawy, C Wat, M Griffiths, E Waalberg, P Ward.Early administration of oral oseltamivir increases the benefits of influenza treatment.Journal of Antimicrobial Chemotherapy,2003,51(1),123-129.
- こども家庭庁:「学校における感染症対策」