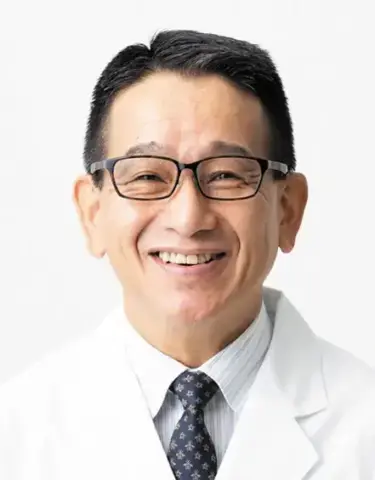目次
- はじめに
- ★今回、内藤先生に取材を行った1月26日は「腸内フローラの日 」。この日は幕府の医師にオランダ医学を学んで小浜藩医となり、解剖書の翻訳に取り組んだ杉田玄白の話から入りました。
- ★いずれも、今にも通じる内容です。内藤先生は同じく福井県出身の石塚左玄にも触れられました。
- ★体力ある高齢者が増えていますね。
- ★内藤先生の最近の研究では、腸内環境を整えることは、寿命にも影響を与えていることが明らかになったそうですね。
- ★食事内容がいいから、サルコペニア、フレイルが少ない。食事内容の良さは腸内環境の良さにもつながり、免疫力を高く保て、感染症のリスクも下がるということですね。
- ★世界最高齢の記録を持つ男性も、京丹後市在住だったと聞きました。
- ★腸内環境を整えるためには、何をすべきですか?
- ★酪酸菌は、善玉菌でしょうか?
- ★腸内フローラを考える上で、特に念頭に置いておいた方がいいことを、最後に教えてください。
- この記事を監修した医師
はじめに
健康を守る上で、腸内環境を整えることが非常に重要であることは広く知れ渡っている。読者の中には、腸内環境をよくする「腸活」を心掛けている人も多いだろう。どのような腸活がいいのか?そもそも腸内環境を整えると、どういったメリットがあるのか?京都府立医科大学大学院生体免疫栄養学講座教授で、腸内研究の第一人者である内藤裕二医師に、最新の研究内容も含めて話を聞いた。内藤医師は、2025大阪・関西万博パビリオンアドバイザーも務めている。
★今回、内藤先生に取材を行った1月26日は「腸内フローラの日 」。この日は幕府の医師にオランダ医学を学んで小浜藩医となり、解剖書の翻訳に取り組んだ杉田玄白の話から入りました。
杉田玄白は、私の生まれ故郷、福井県の出身。2007年に公立小浜病院から名称が変わった杉田玄白記念公立小浜病院の前には、杉田玄白像が立っています。
よく知られる通り、杉田玄白は「解体新書」や「養生七不可」(ようじょうしちふかとふりがな打てませんか?)を書いています。「養生七不可」には長寿の秘訣が記されており、養生のためにやってはいけないことが7つ挙げられています。
- 昨日の非は、恨悔すべからず(昨日の失敗を悔やまないこと)
- 明日の是は慮念すべからず(明日のことは過度に心配しないこと)
- 飲と食とは度を過ごすべからず(食べ過ぎ、飲み過ぎに注意すること)
- 正物に非(あら)ざれば、いやしくも食すべからず(風変わりなものは食べないこと)
- 事なき時は薬を服すべからず(何事もない時は薬を飲まないように)
- 壮実を頼んで、房を過ごすべからず(元気だからといって無理をしないこと)
- 動作を勤めて、安を好むべからず(楽をせず適当に運動を)
★いずれも、今にも通じる内容です。内藤先生は同じく福井県出身の石塚左玄にも触れられました。
〜食育の祖である石塚左玄は、食養・食育論として「家庭での食育の重要性」「命は食にあるという食養道の考え」「人間は穀食動物である」「食物は丸ごとで食べる」「地産地消で地域の新鮮で、旬のものを食する」「バランスある食事」を示しています。100年以上も前に、こういったことを述べているのです。
日本人は、いまや女性の約2人に1人、男性の4人に1人は90歳まで長生きする。女性75歳の平均余命は15.67年、男性は12.04年というデータもあります。40年前と比較すると、75歳からの平均余命は男性で約4年、女性では約6年長くなっており、長くある高齢期の備えが必要なのです。それには、杉田玄白、石塚左玄のメッセージは非常に重要になります。
★体力ある高齢者が増えていますね。

2023年11月11日の日本経済新聞では、「高齢者の体力スコアは上昇傾向にあり、不調を訴える高齢者の比率は下がっている」との記事が掲載されており、体力が上がっている主な背景のひとつに、食事や運動などライフスタイルの変化が挙げられていました。
一方、65歳以上の主な死因別死亡率は1位がん、2位心疾患(高血圧症は除く)ときて、3位が老衰です。老衰は平成20年ごろから上がってきている。これから老衰の人が増えてきて、老衰の前には心筋梗塞や脳梗塞での要介護もいますが、厚労省の国民生活基礎調査を見ると、圧倒的に多いのがフレイルによる要介護です。長い高齢期を、健康で全うするには、フレイルの早期発見、予防対策が極めて重要で、考えなくてはならないのが、人生100年時代の健康栄養学。かつての栄養欠乏時代の食物栄養学から、栄養過剰時代の人間栄養学を経て、人生100年時代の健康栄養学へと変化してきているのです。
★内藤先生の最近の研究では、腸内環境を整えることは、寿命にも影響を与えていることが明らかになったそうですね。
私たちは2017年から京丹後長寿コホート研究を実施しています。長寿コホート研究は、その地域の高齢者を対象にデータを取り15年、20年と長期に渡りずっと追いかけるというものです。まだ短い期間ではあるのですが、それでも興味深いことがだんだんとわかってきました。
京都府京丹後市は、京都府の北部の日本海側にあります。この地域は、満100歳以上の方が116人(2023年9月1日時点)いて、人口10万人当たりの100歳以上の数にすると226.32人。全国平均の3.1倍、京都府平均の約2.7倍になる、日本国内でも有数の長寿地域になります。なお、短命県で知られる青森県では、弘前市が人口10万人当たりの100歳以上66.95人になります。
京丹後市の高齢者では、大腸がんが少ない。私がこの地に興味を持ったきっかけが、長寿者が多いこと、大腸がんが少ないこと。大腸がんは肥満や生活習慣、腸内環境が関係してるので、長寿研究にいいと思ったのです。
大腸がんだけではありません。サルコペニア、フレイルの高齢者は少なく、インフルエンザに感染する人も極めて少ない。高血圧症は比較的多いのですが、血管年齢を調べると、驚くほど若いのです。
★食事内容がいいから、サルコペニア、フレイルが少ない。食事内容の良さは腸内環境の良さにもつながり、免疫力を高く保て、感染症のリスクも下がるということですね。
〜腸内環境を整えるにあたって食生活は重要ですが、日常的な身体活動量も大きく関係しています。京丹後市の高齢者の1日はとても規則正しく、夜は暗くなったら寝て、朝は早く起きる。起きたら畑仕事に向かい、それが身体活動量を上げている。睡眠時間もしっかりとっている。
少し前まで京丹後市には総合病院はありませんでしたが、この地域の高齢者にとっては、それが特に困りごとにはなっていなかったのです。
★世界最高齢の記録を持つ男性も、京丹後市在住だったと聞きました。
木村次郎右衛門さんで、2013年にご逝去されましたが、116歳54日という記録はいまだ破られていません。
6人兄弟の3番目に生まれた木村さんは、20歳から65歳までの45年間、郵便局にて勤務されていました。毎日午前5時半に起き、午後8時に就寝する生活。朝はヨーグルトやさつまいも、梅干しを食べ、夜は生乳を飲むことを習慣としていました。
★腸内環境を整えるためには、何をすべきですか?
現時点で京丹後の調査から見えていることについての話になりますが、肥満、ポリファーマシー(多剤併用)、睡眠の質の悪さ、運動不足は、フレイルに関係していると言えるでしょう。
フレイルと腸内環境を調べた論文があります。腎臓が少しずつ悪くなっていく慢性腎臓病は、筋肉が痩せ衰える症状が出てくることがあります。慢性腎臓病患者の腸内細菌を調べたところ、大腸菌の一種であるシトロバクター菌が多いとフレイルが進行し、酪酸菌の一種であるロゼブリア菌が多いとフレイルにはなっていませんでした。酪酸菌は酪酸という成分を産生する菌の総称で、体内で酪酸が減ると筋肉に炎症が起こり、筋肉が萎縮することは、マウスの実験だけでなく、ヒトの研究でも発表されています。
京丹後では、前述の通り、サルコペニアも少ない。加齢で筋肉が減少する現象がサルコペニアですね。そして、サルコペニアにはグレリンというホルモンが関係しています。マウスの実験で、グレリンを分泌する遺伝子をノックアウトすると、マウスの筋肉は萎縮。次にマウスの腸内細菌を調べると、ロゼブリア菌とクロストリジウム14B菌が減っていました。クロストリジウム14B菌も、酪酸菌の一種です。
★酪酸菌は、善玉菌でしょうか?
腸内環境を整えるには、善玉菌を増やして悪玉菌を減らす――。よく言われることですが、現在、腸内細菌の研究ではこのような考え方はしません。代表的な善玉菌といえばビフィズス菌や乳酸菌でしょうが、現実的には無理ですが例えとして腸内細菌のすべてがビフィズス菌だったら長生きできるのかというと、そんなことは絶対にありません。
善玉菌や悪玉菌というものは存在しない。大事なのは、腸内細菌の多様性なのです。腸内環境を整えるということは、つまり腸内フローラ(腸内細菌叢)を健康にするということ。そしてそれは、善玉菌VS悪玉菌ではなく、多様性のある腸内フローラにするということです。そのためには食べるものも多様性にしなくてはなりません。ヨーグルトがいいからヨーグルトばかりを食べるのではなく、普段の食生活でさまざまなものを取り入れるようにしていただきたい。
★腸内フローラを考える上で、特に念頭に置いておいた方がいいことを、最後に教えてください。
繰り返しになりますが、さまざまな食品をバランスよくとること。ただ、控えめにした方がいいものがあります。それは、赤肉、高脂肪食。一方で積極的に取ることを推奨しているのが、豆腐や厚揚げなど大豆製品、発酵食品、野菜(とくに根菜類)やキノコ、玄米、果物といった食物繊維が豊富な食品。
WHOの委託を受けニュージーランドのオタゴ大学が行った研究(世界的学術誌「ランセット」に掲載)では、食物繊維が脳卒中、心疾患のリスクを減らすことを示し、1日25〜29グラムの摂取が効果的としています。そして、日本人の摂取量はこの量に全然到達していないことがわかっています。
私は食物繊維を1日25グラム以上取ることを心がけていますが、普通に食べているだけでは難しい。朝はりんご、キウイ、柿など季節の果物と食物繊維の豊富なスペシャルスムージーを飲み、主食は玄米や全粒穀類にしています。京丹後では、野菜とワカメ、豆腐などが入った具沢山の味噌汁を飲んでいる高齢者を多く見かけました。
※「腸内フローラの日」は、1993年に京都の伝統的な漬物「すぐき漬け」から植物性乳酸菌「ラブレ菌」が発見されたことから、カゴメ株式会社大阪支店が制定した。