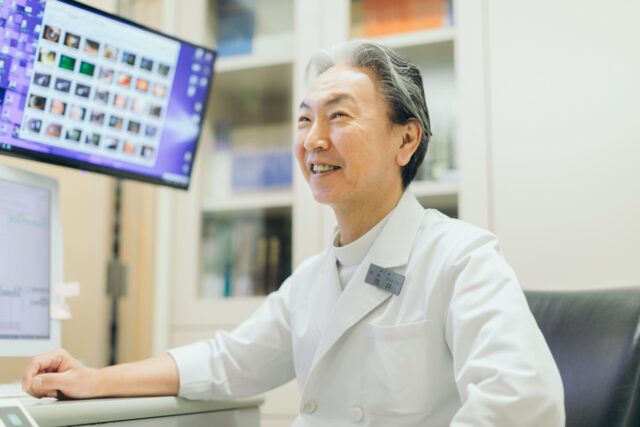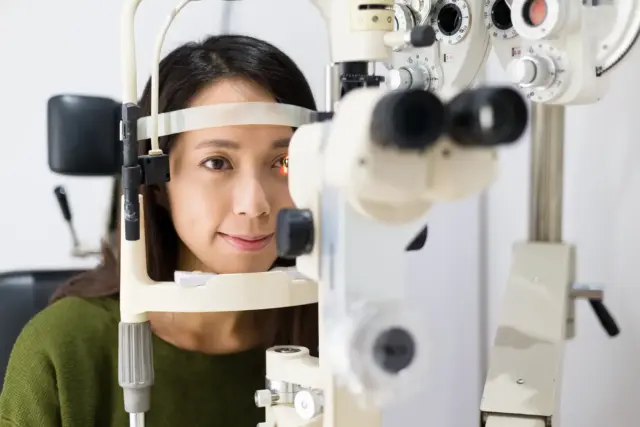目次
はじめに
年代を問わず、ドライアイや眼精疲労に悩む人が増えている。パソコンやスマートフォンがなくてはならないものになり、また近くを見る機会が圧倒的に多い生活が原因だ。
ドライアイも悪化すれば角膜を傷つけ、眼がしょぼしょぼしたり、光がまぶしくなったり、痛みを感じたりして、生活の質を著しく下げるが、デジタル機器の使い過ぎで怖いのは、視力低下も招くこと。
全国から眼の病気に悩む患者が来院する二本松眼科病院(東京・平井)副院長の平松類先生は、最近『眼科医だけが知っている一生視力を失わない50の習慣』(SB新書)を上梓。近視人口が増えていることに警鐘を鳴らす。
近視は、何が怖いのか?対策を講じることはできるのか?平松先生に話を聞いた。
Q.コロナ禍以降、ドライアイなど目の不調を訴える人は増えたと聞きます。
明らかに増えました。二本松眼科病院に来る患者さんの話を伺っていてもそうですし、眼精疲労やドライアイで市販の点眼薬を使う機会が増えたという話もよく聞きました。
原因は、デジタル機器の使用頻度の増加です。オンラインでの会議や打ち合わせが一般的になり、お子さんもデジタル機器を用いて授業を受けることが珍しくなくなりました。それによって、従来はあり得なかった光の刺激を大量に、近距離で、長時間にわたり受けるようになった。結果、起こっているのが視力の低下です。
そもそも視力低下は、コロナのずいぶん前から増えています。デジタル機器の普及のスピードが速すぎて、目の進化がそれに追い付けていないのです。そこにコロナによる一層のデジタル化が加わった。現在は、人類史上最大の目の危機を迎えていると言っても過言ではないでしょう。
Q.それほど近視は増えているのでしょうか?
近視人口の増加は、日本だけではなく世界的な傾向です。オーストラリアのブライアン・ホールデン視覚研究所は、2010年には約20億人だった近視人口が、2050年には50億人に達すると予測しています。これは、世界人口の約半分の人数。しかも、50億人の近視人口のうち、9億3800万人が強度近視になると指摘しているのです。
前項でも触れたように、コロナで一層視力低下に陥りやすい状況になった。ブライアン・ホールデン視覚研究所の発表は2016年に行われたものなので、近視人口50億人に達するのは、2050年よりも前になる可能性もあります。
Q.子どもの視力低下が深刻だと聞きます。

昨年6月、京都市では一斉休校の終了を受けて、市内の小学生に視力検査を行いました。すると視力が0.7未満の子供は、前年比で6%増の23%でした。子供の視力低下にどんな対策を講じるか、これに関しても世界の眼科医が頭を悩ませています。
Q.そもそも視力低下はなぜ起こるのですか?
実は、視力低下の発生メカニズムは完全には解明されていません。有力なのは、目のピント調節機能にラグが生じている、という説です。
目のピント調節は「毛様体筋」という筋肉が担っています。近くを見る時、ピント調節の毛様体筋がぎゅっと収縮。目のレンズである水晶体が分厚くなり、目の奥にある網膜上でピントが合い、物がはっきりと見えるようになります。
私たちの生活は、ただでさえ近くを見る機会の方が多いですよね。パソコンやスマホを見る時間が増えると、“ものすごく近くの距離”を長時間凝視していることになります。すると網膜より奥でピントが合うようになり、物がぼやけて見えるようになってしまう。そこを何とかしようとしているうちに、通常、24ミリくらいの「眼軸(目の直径)」が26〜27ミリに伸びてしまい、目の構造が変わってしまうのです。こうなると、ピントが合いづらかった近距離でも見やすくなる代わりに、遠くはぼやけて見づらくなってしまいます。一度伸びてしまった眼軸は元に戻りません。
Q.「近視でも眼鏡やコンタクトレンズを装着すれば問題ないのでは…」という声もあります。
近視は単に、遠くが見えづらくなるだけではありません。近視は、失明のリスクを高めることが明らかになっています。
近視の人は、眼のレンズである水晶体が濁る「白内障」、眼球の圧力が高くなり視神経が傷害される「緑内障」、眼球の内側にある網膜がはがれる「網膜剥離」、黄斑の網膜に隙間ができたり、網膜がはがれたりする「近視性黄斑症」といった病気を発症しやすいのです。これらはいずれも、視力が弱り、治療が遅れれば失明してしまう病気です。ある論文では、近視の程度によってどれくらいリスクが上がるか、次のようなデータを発表しています。
- 緑内障/軽度近視で1.59倍、中等度以上の近視で3.3倍
- 白内障/軽度近視で1.56倍、中等度近視で2.55倍、強度近視で5.5倍
- 網膜剥離/軽度近視で3.15倍、中等度近視で8.74倍、強度近視で21.5倍
- 近視黄斑症/軽度近視で13.57倍、中等度近視で72.74倍、強度近視で845.08倍
なお、近視の軽度、中等度、強度は視力ではなく、眼の調整力を表す「D(ディオプトリ―)」の程度。軽度近視は0〜マイナス3、中等度近視はマイナス3〜マイナス6以下、強度近視はマイナス6以下になります。
Q.これ以上視力低下を招かないために、日常生活で気を付けることは何ですか?
パソコンやスマホなどのデジタル機器を使う時間を減らせれば一番ですが、現代社会ではそれは不可能です。パソコンやスマホなどを使いつつ、これだけは守ってほしいということがあります。
まずは、暗い所ではパソコンやスマホを見ないことです。ベッドに入ってスマホを見るなんて極力避けてほしい。暗い所では、多くの光を取り入れるために目の瞳孔が開きます。その状況でスマホを見ると、大量の光が至近距離から目に入り、ダメージを受けます。
次に、長時間パソコンやスマホを見続けないこと。ピントを調整する毛様体筋が凝り固まってしまいます。意識して、定期的に遠くを見る。1時間ごとに遠くを見られればベターです。何か遠くのものにピントを合わせるようにして見てください。
さらに、仕事環境を眼に優しいものに変えましょう。明るい部屋でデジタル機器を見るようにし、パソコン画面と眼の距離は40〜70センチほどに。目線は画面と水平から15度下の角度になるようにしてください。冬は目が乾きやすくなるので、加湿器を置いて、湿度を40〜70%に保ちましょう。
Q.食生活や運動も視力低下防止に役立ちますか?
もちろんです。食事では、目に良いことが数々の研究で証明されているルティンという抗酸化物質を積極的に取るといいでしょう。ホウレン草やゴーヤなど、緑の濃い野菜に含まれています。サバやサンマ、イワシなどに多いDHA、EPAは眼の老化を抑制し、まぶたのマイボーム腺という器官から油の分泌を促してドライアイ対策になります。抗酸化物質であるビタミンA、C、Eもお勧めです。適度な運動は血流を良くして、眼に酸素や栄養成分が届きやすくなります。可能であれば、屋外で運動を。米国の研究で、1日2時間以上屋外で過ごす子供は近視が少ないとの結果が出ているのです。近視には遺伝因子も関係しますが、両親とも近視の子供も近視になりにくいとの結果でした。
また、台湾では20歳以下の約8割が近視という状況を改善しようと、政府が小学校の体育の授業を屋外で週150分間行うことを義務化。理科の授業では屋外観察を推奨しました。すると、7年間で視力0.8未満の小学生の割合が50%から44.3%に減少したというのです。毎年増加し続けていた視力不良の生徒の数も大幅に減少したそうです。
お子さんの視力低下が心配な方は、親子で日中、人の少ない所を散歩したりするのもいいですね。在宅勤務で通勤時間がなくなった人は、屋外に出る時間が激減しているでしょうから、ランチタイムは外に出掛けるなどして、屋外で過ごす時間を増やしてください。
Q.平松先生の著書で「ガボール・アイ」を知りました。これも視力にいい効果をもたらすのですか?
ガボール・アイは、脳を使った視力回復法。眼の機能を良くするのではなく、脳の視覚野に働きかけ、画像を鮮明に処理できるようにしようというものです。物理学者デニス・ガボールが作成した縞模様(ガボール・パッチ)を見て、どういう模様かしっかり把握し、制限時間内に同じ模様を探し出します。ガボール・パッチが視覚野に作用しやすく、臨床データもいくつも報告されています。私の著書でガボール・アイの縞模様を紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
Q.眼の健康を守るうえで、ほかに考慮すべきことはありますか?
紹介した「気を付けるべきこと」は必要最低限やっておいてほしいこと。さらに、眼の定期健診はきちんと受けてほしいと思います。緑内障などの発症リスクが高くなるのは40歳代以上ですが、20歳代、30歳代でも眼の病気と無縁ではありません。自覚症状がなくても、ちゃんと見えているのか、眼科で調べることは大切です。ましてや、見えづらさなど何らかの症状があるようなら、様子見などせず、眼科で早めに検査を受けてください。
平松先生おすすめの近視予防法
1.ベッドに入ってスマホを見ない
2.長時間パソコンやスマホを見続けない(定期的に遠くを見る)。
3.仕事環境を眼に優しいものに変える
(室内を明るい環境に保ち、パソコン画面と眼の距離は40~70cmに。目線は画面と水平から15度下の角度にする)
4.食生活に気をつける
(緑黄色野菜に含まれるルティンやビタミン、青魚に多いDHA、EPAを多く摂取する)
5.屋外で運動をする