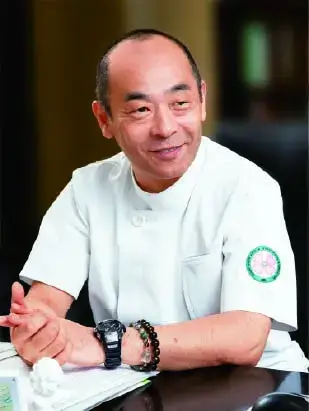目次
はじめに
全国的に認知症の高齢者が加害者となる交通事故が多発し、社会問題になっている今日。「自分の親は大丈夫だろうか」と心配な方も多いのではないでしょうか。そんな方におすすめしたいのが、認知症検査法「TOP-Q」です。
その特徴は、「患者も嫌がらず、2~3分の自然な問診だけで終わる」点。物忘れが増えてきた親御さんをいきなり大きな病院に連れていこうとしても、本人に受け入れてもらえない可能性があります。そこで、まずは手軽に試せる「TOP-Q」を活用し、その結果から„もしかして"と思ったら、認知症専門医を受診し、早期発見・早期治療にお役立てください。くどうちあき脳神経外科クリニック(東京・大田区)の工藤千秋院長に話を聞きました。
Q.認知症とは、どういうものですか?
認知症は、なんらかの原因で脳の神経細胞が壊れるために起こる症状や状態を指します。本人にしても、周囲にしても、最初は「ちょっとした違和感」程度ですが、進行するにつれ、これまででは考えられないような理解力・記憶力の低下、性格の変化などが見られます。
認知症には主に、アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症の4つがあり、大半を占めるのはアルツハイマー型認知症です。一般的に、認知症というと、アルツハイマー型認知症を指しているケースも少なくありません。
Q.それぞれの病気はどうして起こるのですか?
アルツハイマー型認知症は、脳に特殊なタンパク質がたまり、神経細胞が壊れ、脳が萎縮していきます。脳血管性認知症では、脳梗塞、クモ膜下出血などで脳の血管が詰まったり出血したりすることで、神経細胞が死滅して発症します。
レビー小体型認知症は、レビー小体という特殊なタンパク質がある部分に集まって脳細胞が壊れて減少する病気。
前頭側頭型認知症は、頭の前にある前頭葉と横にある側頭葉が萎縮して起こります。
Q.症状はどういうものですか?

アルツハイマー型認知症で最初の段階からよく見られる症状は、物忘れです。外出したのになんのために外出したか思い出せない、昼ごはんを食べたかどうか覚えられないなどです。これまでなんなくできた料理の手順や親しい人の名前などを思い出せないなどの記憶障害に加え、何を着ていいかわからないといった判断能力の低下、今日の日付や自分の居場所がわからなくなる見当識障害もあります。さらに「周辺症状」といって、「○○を盗られた」と被害妄想にかられたり、お風呂に入るのを嫌がったり、理由もなく出かけてふらつく「徘徊」などがあります。
脳血管性認知症では、脳の壊れてしまった部分によって低下する機能が違います。記憶や計算に関する部分の神経細胞が壊れていれば、それらの能力が落ちます。ほかはあまり変わりません。意欲がなくぼーっとしている時もあれば、はっきりしている時もあり、感情の起伏も激しくなりがちです。
レビー小体型認知症は、物忘れより幻視や幻聴が先に出て、パーキンソン病のように筋肉がこわばったり、動作がスムーズにいかなくなったりするなどの症状が出ることがあります。
前頭側頭型認知症では、社会的ルールを無視した行動や、集中力や自発性の低下、同じ行動の繰り返しなどがあります。
ここに挙げた症状はいずれも典型的なものの一部。「○○○の症状があるから、アルツハイマー型認知症だ」といったようにシンプルに診断できるケースはごく少数で、むしろ、複数の症状が混ざっていて、認知症専門医でなければ判断しにくいケースのほうが「普通」です。ただ、共通しているのは、よく知っている人から見て、その人の症状が「これまででは考えられないこと」であることです。
Q.親が認知症ではないかと心配です。とはいえ、認知症が疑われる場合も、親を病院に連れて行こうとするのは難しいという話を聞きます。いい方法はありますか?
おすすめが「TOP-Q」 という方法です。東京大森医師会認知症簡易チェック法で、「Tokyo Omori Primary Questionnaires for Dementia」の頭文字から「TOP-Q」と名付けられました。「患者も嫌がらず、2〜3分の自然な問診で、認知症をスクリーニングする技術」と、大田区以外の専門医、専門医以外、両方の認知症にかかわる医師の間で高い評価を得ています。
Q.それは、医師でなくてもできますか?
できます。一般の人でもできますし、子供でもできます。私は、小学生を対象にした講演会で「家に帰って、おじいちゃん、おばあちゃんにやってみてね」と話すこともあるくらいです。
まずはさりげない会話で、2020年の東京オリンピックの話をしましょう。
「もうすぐオリンピックだね。楽しみだね」
おじいちゃん、おばあちゃんは「うん、うん」とうなずくと思います。そこで、「5年後の東京オリンピックでは何歳になっている?」と聞きます。さらに、「51年前の東京オリンピックの時は何歳だった?」「そういえば、誕生日はいつだっけ」などと話を持っていきます。この時どのように答えるか、どのような反応を見せるかを、よく観察しておいてください。
次に、相手にある2つのポーズを作ってもらいますが、私はいきなりそうは言わずに、「体の柔軟性を見ようか」などと話しかけます。
「前へならえ」のように、両腕を肩の高さに水平に上げてもらいます。そして、両手を内側、外側にくるくる回す「キラキラ体操」をしてもらいます。
「では、こういうポーズできる?」
両手で「キツネ」と「ハト」を作ってもらいます。ここで観察するのは、「キツネを作れるか」と「ハトを作れるか」。加えて、「両腕は同じ高さに上がっているか。片方の腕が下がらないか」「キラキラ体操ができているか」もチェックしてください。
Q.どのように判定すればいいですか?
認知症の可能性を見るポイントは、「5年後の年齢」「51年前の年齢」「誕生日」をすべて言えるか? ひとつでも失敗なら「×=1点」です。
そして、「キツネ」と「ハト」をそれぞれ作れるか? いずれか1つが失敗なら「×=5点」2つも失敗なら「××=2点」です。1~3点なら、認知症の疑いあり。進んだ検査が必要です。点数が高いほど、その疑いは強くなります。
この検査では、もっと突っ込んだこともわかります。5年後と51年後の年齢や誕生日を聞いた時、同行者(近くの家族)に「どうだっけ?」「あんた知ってる?」などと聞いた場合、これは「振り向き徴候」といって、アルツハイマー型認知症によくある「取り繕いの症状」です。
両手を肩の高さに水平に上げた時、どちらか片方の腕が下がっているようなら、「ハンド・バレー徴候」。下がっている方の腕と反対側の脳に脳梗塞などが起こっている可能性があります。つまり、脳血管性認知症の疑いがあるのです。
そして、キラキラ体操がうまくできなければ、この体操は「回内・回外運動」といって、レビー小体型認知症のパーキンソニズムという症状があるかどうかの確認になります。
Q.なぜこの検査が高い評価を得ているのでしょうか?
認知症を正しく診断しようと思えば、記憶力を見るスケール、認知症の問題行動を見るスケール、日常生活を見るスケールに加え、高齢者のうつを評価するスケールも必要です。MRI、CTなどの画像診断も外せません。
必然的に、認知症専門医以外では、なかなか難しい。しかし、高齢化で認知症を発症する人は年々増えていますから、専門医以外も認知症診断に携わらないわけにはいきません。
このTOP-Qは、だれでもできるように考え出したもの。「スクリーニングのスクリーニング」と私は呼んでいますが、ご家庭でまずやってみて、おかしいと思ったら、専門医を受診してほしい。大田区ではかかりつけ医が実施し、専門医へつなげる活動がおこなわれています。
認知症の初期では、患者さん自身が、記憶力や認知機能の低下など「これまでにない自分」に最も戸惑っています。そんな状態で「いきなり病院へ行こう」と言っても、本人も受け入れがたい。ましてや、病院に行ったとしても、正しく診断されないケースもあります。すると、ますます病院に行きたがらなくなるでしょう。その問題を解決するために、このTOP-Qを考え出したのです。
Q.認知症は、ほかの病気と間違われることはあるのですか?
よくあります。
認知症がほかの病気と間違われているケースも少なくありませんが、ほかの病気を認知症と間違われているケースのほうが上回るのではないでしょうか? 患者さんの年齢から、医師の頭にはまず認知症という疾患が浮かぶことが原因かもしれません。
たとえば、当クリニックに認知症を疑って来院した患者さんは、「最近、物事の覚えが悪くなった」「これまでにはなかった変な行動や言動が目立つようになった」「ぼーっとしていることが増えた」の3つにわかれます。
認知症に詳しくない医師では、患者さんの年齢と、これらの症状から、条件反射的に認知症を連想するでしょう。認知症を判断するために、長谷川式やミニ・メンタルステート検査といった記憶力テストを行いますが、これでも点数が低いと、「やはり認知症」となりかねません。
しかし、最後の「ぼーっとしていることが増えた」は、うつ病も疑われる症状です。うつ病であれば、集中力や注意力、意欲の低下などで記憶力テストが、認知症の場合と同様に低くなります。記憶力テストだけでは、うつ病を除外診断できないのです。
認知症とうつ病とでは薬の処方が異なり、さらに対応策もまったく逆です。認知症だと判断し、それに基づいた対応をしていれば、うつ病はますます悪化します。
厄介なのは、最新の研究で、うつ病と認知症の関連性が証明されたこと。うつ病の高齢者の中には、症状が認知症と似ているうつ病を最初に発症し、次第に軽度認知症、認知症となっていく人もいる。しかし、症状が認知症と似ているうつ病のうちに治療を行えば、認知症までいかない。認知症とうつ病の誤診が、後々、本当の認知症を招く可能性があるということなのです。
Q.ほかには、どういう病気が間違われやすいでしょうか?
治療で治る特発性正常圧水頭症という病気を認知症と間違われているケースも最近は特に指摘されています。ほかには、慢性硬膜下血腫、パーキンソン病なども間違われやすいことが指摘されています。
Q.先生の美学を教えてください
生きていると、楽しいことばかりでなく辛いこともたくさんふりかかってきます。
バラ色に満ちた生活を夢見ていたはずなのに…。なぜこんなに苦しいのか。子育てがうまくいかなくて、毎日イライラ。あれほどハツラツとしていた親が、あれほど優しかった近所のおじちゃんおばちゃんが、直前に話した同じことを何度も何度も電話してきたり、ある日徘徊している姿を目の当たりにしたりすると、……信じられない!
特に目の前にいる親については、自分が幼かった頃の日常の声、大きな体が眼に耳に焼き付いています。いつまでも人は昔のままではいられません。
心も体も、環境の変化とともに良い意味でも悪い意味でもどんどん変化していきます。でも、どんなに苦しい状態でも、誰かが早くみつけて、手を差し伸べれば、苦しみから少しでも解放されます。認知症も同じです。かかりつけ医、家族ぐるみ、町ぐるみで、早くもの忘れのある方に手をさしのべられるよう、認知症専門医として、私も努力していきたいと思います。