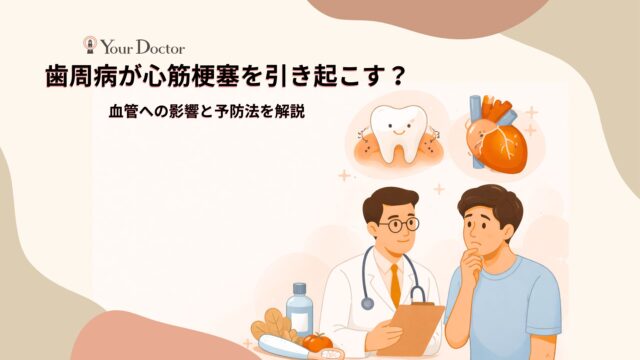「糖尿病と診断されたけれど、歯のことはあまり気にしていない」
もしそう考えているなら、注意が必要です。実は、糖尿病と歯周病は一見無関係のようで、互いの症状を悪化させる「負の連鎖」を引き起こす関係にあります。
歯周病による慢性的な炎症が血糖コントロールを妨げ、心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる病気の引き金にもなりかねません。
この記事では、なぜ糖尿病だと歯周病になりやすいのか、「負の連鎖」を断ち切るための具体的な予防法までを詳しく解説します。
関連記事はこちら
糖尿病と歯周病の関係
糖尿病と歯周病は、お口と全身の病気として別々に考えられがちです。しかし、この二つの病気は互いに悪影響を及ぼし合う、強い関連性があります。
関連記事はこちら
なぜ糖尿病の人は歯周病になりやすいのか
なぜ糖尿病の人は歯周病になりやすいのでしょうか。
その大きな理由のひとつは、血糖値が高い状態が続くと白血球(特に好中球)の働きが弱まり、細菌に対する抵抗力が落ちてしまうことです。その結果、口の中の歯周病菌に感染しやすくなります。さらに高血糖は体の水分バランスを崩し、唾液の分泌を減らすことがあります。唾液には口の中を洗い流す役割があるため、分泌が減ると細菌が繁殖しやすい環境になり、歯周病を悪化させる要因となります。
加えて、高血糖は全身の血管を傷つけ、特にに細い血管をもろくしてしまいます。そのため歯ぐきの血流が悪くなり、炎症が起きても修復に必要な酸素や栄養が届きにくくなり、治りが遅れるのです。
歯周病が糖尿病を悪化させる悪循環
歯周病による慢性的な炎症は、糖尿病そのものを悪化させる原因です。
歯ぐきで炎症が続くと、体は「TNF-α」といった炎症性物質を作り出します。この物質が血流に乗って全身に広がると、血糖値を下げるホルモン「インスリン」の働きを妨げてしまうのです。これを「インスリン抵抗性」と呼びます。
インスリンが効きにくくなると、血糖値が下がらず、糖尿病のコントロールがさらに難しくなります。そして、悪化した高血糖がまた歯周病を進行させるという、まさに悪循環に陥るのです。
糖尿病が歯周病を招く3つの理由
ここでは糖尿病が歯周病を招く3つの理由を詳しく見ていきましょう。
高血糖で免疫力が下がり、細菌に弱くなる
私たちの体には、外から侵入してきた細菌やウイルスと戦う「免疫」という防御システムが備わっています。しかし、血糖値が高い状態が続くと、この免疫システムの働きが鈍くなってしまいます。
特に、細菌を処理する役割を持つ白血球(好中球)の機能が低下します。そのため、お口の中の歯周病菌に対する抵抗力が弱まります。その結果、普段なら抑え込めるはずの歯周病菌が増殖し、歯ぐきに炎症を起こしやすくなるのです。
口の中が乾燥しやすく、菌が繁殖しやすくなる
糖尿病で高血糖の状態が続くと、体の水分バランスが崩れ、唾液の分泌が減ることがあります。唾液が少なくなると、口の中の環境にさまざまな変化が生じます。
まず、食べかすや細菌を洗い流す自浄作用が弱まり、細菌が残りやすくなります。さらに唾液に含まれる抗菌成分の働きも低下するため、細菌の増殖を抑える力が落ちてしまいます。こうした変化によって口の環境は不安定になり、虫歯や歯周病のリスクが高まるのです。
血管がもろくなり、歯ぐきの炎症が治りにくくなる
血糖値が高い状態が続くと、全身の血管、特に毛細血管がダメージを受けます。これは糖尿病の三大合併症の原因として知られていますが、歯ぐきの中を通る細い血管も例外ではありません。
高血糖は、血管の壁を傷つけて弾力性を失わせたり、血液の流れを悪くしたりします。そのため、歯ぐきに炎症が起きても、組織を修復するために必要な酸素や栄養素が十分に行き渡らなくなります。その結果、歯ぐきの炎症が治りにくく、歯周病が進行しやすくなってしまうのです。
放っておくと怖い!歯周病が全身に与える影響

歯周病は単に歯ぐきが腫れたり、歯が抜けたりする問題ではありません。お口の中で起きている慢性的な炎症は、全身の健康に深刻な影響を及ぼすことが明らかになっています。
ここでは、歯周病が全身に与える具体的な影響を解説します。
血糖コントロールがさらに難しくなる
歯周病があると、糖尿病のコントロールがさらに難しくなる悪循環に陥ります。歯周病とは、歯ぐきで歯周病菌と体の免疫機能が絶えず戦っている状態です。この「慢性的な炎症」が、血糖値に直接影響を与えます。
炎症が続くと、体は「TNF-α(ティーエヌエフアルファ)」といった炎症性物質を大量に作り出します。この物質は、血糖値を下げるホルモンである「インスリン」の働きを邪魔する性質があります。これがいわゆる「インスリン抵抗性」です。
インスリンが効きにくくなると、血糖値がなかなか下がりません。結果として、糖尿病のコントロールは悪化してしまいます。
近年の研究では、お口の中の細菌バランスが乱れることも問題視されています。ポルフィロモナス・ジンジバリスといった悪玉菌が増えることが、全身の炎症を強め、糖尿病の管理をより難しくする一因と考えられています。(※1)
心筋梗梗塞や脳梗塞のリスクが上がる
歯周病は、命を脅かす心筋梗塞や脳梗塞のリスクを高めることがわかっています。歯周病によって炎症を起こした歯ぐきは、傷口と同じ状態です。そこから、歯周病菌やその毒素が血管内に侵入してしまいます。
- 1. 歯周病菌が血管内に侵入する:炎症を起こした歯ぐきの血管から、菌や毒素が血液中に入る
- 2. 菌が全身を巡り、血管の壁に付着する:血流に乗った歯周病菌などが、血管の壁に炎症を引き起こす
- 3. 動脈硬化が進行する:血管の壁で炎症が起きると、動脈硬化の原因となる「プラーク(粥腫)」が作られやすくなる
- 4. 血管が詰まり、発作が起きる:プラークにより心臓や脳の血管が詰まり、心筋梗塞や脳梗塞を引き起こす
ある大規模な追跡調査(PAROKRANK研究)では、歯周病の人はそうでない人に比べ、心血管系の病気になるリスクが約1.26倍高かったという結果が出ています。(※2)
糖尿病の方はもともと動脈硬化が進みやすいため、歯周病の合併はリスクをさらに高めるのです。
肺炎など全身の病気につながることも
歯周病菌は口の中から気管を通って肺に入り込み、肺炎を引き起こすことがあります。
特に飲み込む力が弱くなった高齢の方では、食べ物や唾液が誤って気管に入る「誤嚥」が起こりやすく、その際に歯周病菌が肺に届くことで「誤嚥性肺炎」のリスクが高まります。日常的な口腔ケアは、肺炎を防ぐうえでも重要です。
さらに近年の研究では、歯周病菌をはじめとする口腔内の細菌が全身に巡り、心血管疾患や糖尿病の悪化など生活習慣病との関連も指摘されています。つまり、歯周病対策は口の健康だけでなく、全身の健康を守るためにも欠かせないのです。(※2)
歯を失って食事や生活の質が下がる
歯周病が進行すると、歯を支えるあごの骨が溶かされてしまいます。その結果、歯がグラグラになり、最終的には歯を失うことになります。歯を失うと、生活の質(QOL)にさまざまな影響が及びます。
- 食事の制限
- 食事の楽しみの減少
- コミュニケーションへの影響
特に糖尿病の方にとって、バランスの取れた食事は血糖コントロールの基本です。
歯を失って食事が偏ることは、糖尿病の管理をさらに難しくさせます。自分の歯でしっかり噛んで食事を楽しむことは、豊かな人生を送る上で欠かせません。
糖尿病と歯周病を防ぐための対策
ここでは、糖尿病と歯周病の悪循環を断ち切るための5つの具体的な対策について、わかりやすく解説していきます。
- 医科と歯科、両方で診てもらう
- 毎日の歯磨きとフロスで口の中を清潔にする
- 定期的に歯科でクリーニングを受ける
- 血糖コントロールをしっかり続ける
- 健康的な食事と生活習慣を心がける
①医科と歯科、両方で診てもらう
糖尿病の治療は内科医が、歯周病の治療は歯科医が担当します。しかし、この二つの病気は密接に関連しているため、別々に治療を進めるだけでは不十分です。医師と歯科医師が協力して治療を進める「医科歯科連携」が重要になります。
例えば、内科医は血糖コントロールの状態(HbA1cの値など)を歯科医に共有します。その情報をもとに、歯科医は抜歯などの外科的な処置を安全に行えるタイミングを判断します。逆に、歯科医は歯周病の治療状況を内科医に報告し、血糖コントロールに良い影響が出ているかを確認します。
②毎日の歯磨きとフロスで口の中を清潔にする

歯周病予防の全ての基本は、原因となる細菌の塊(プラーク)を毎日のセルフケアでしっかりと取り除くことです。特に糖尿病の方は感染への抵抗力が弱まっているため、より丁寧なケアが求められます。
毎日のセルフケアでは、まず歯磨きが基本になります。歯と歯ぐきの境目にある溝(歯周ポケット)を狙い、歯ブラシの毛先を45度の角度で当てて、軽い力で小刻みに動かして磨くことが大切です。特に奥歯や歯の裏側は磨き残しやすいので、意識して丁寧にケアしましょう。
さらに歯ブラシだけでは歯と歯の間の汚れを約6割しか落とせないため、歯間ケアも欠かせません。歯周病は歯の間から始まることが多いため、デンタルフロスや歯間ブラシを取り入れて、歯ブラシでは届かない部分のプラークをしっかり除去することが重要です。
③定期的に歯科でクリーニングを受ける
毎日丁寧に歯磨きをしていても、セルフケアだけでは落としきれない汚れが少しずつたまっていきます。特に、プラークが石のように硬くなった「歯石」は、歯ブラシでは取り除くことができません。
歯石の表面はザラザラしているため、さらにプラークが付着しやすくなります。これが、歯周病を悪化させる温床となってしまうのです。そのため、定期的に歯科医院で専門的なクリーニング(プロフェッショナルケア)を受けることが不可欠です。
歯科医院では、専門の器具を使って歯石をきれいに除去します。また、歯周病が進行していないか、磨き残しがないかなどをチェックしてもらい、一人ひとりのお口に合った歯磨きの指導も受けられます。
④血糖コントロールをしっかり続ける
歯周病を改善し、再発を防ぐためには、お口のケアと並行して、糖尿病そのものの治療をしっかりと続けることが何よりも大切です。血糖値が高い状態が続くと、体全体の免疫力が低下し、歯ぐきが細菌と戦う力を失ってしまいます。
また、血管がもろくなることで歯ぐきに十分な栄養や酸素が届かず、炎症が治りにくくなってしまいます。つまり、いくら歯科医院で治療を受けたり、丁寧に歯磨きをしたりしても、高血糖という根本的な原因が改善されなければ、歯周病はなかなか良くなりません。
内科のかかりつけ医の指示に従い、食事療法や運動療法、薬物療法をきちんと続けましょう。血糖値を安定させることが、歯周病の根本的な治療につながります。
⑤健康的な食事と生活習慣を心がける
糖尿病と歯周病の悪循環を断ち切るには、毎日の生活習慣の見直しが欠かせません。
まず、食事では食物繊維を多く含む野菜やきのこ類を取り入れることで、血糖値の急な上昇を抑えられます。腸内環境を整えることも免疫力の向上につながり、糖尿病や歯周病に良い影響を与えると考えられています。
次に、ウォーキングなどの適度な運動は血糖コントロールを改善し、全身の血流を促進しましょう。血流が良くなることで歯ぐきの状態も改善しやすくなります。
そして、禁煙は最も重要なポイントのひとつです。喫煙は歯ぐきの血流を悪化させ、歯周病を著しく進行させる大きな危険因子であり、治療効果も出にくくなります。禁煙は糖尿病と歯周病の両方の治療において必須といえるでしょう。
まとめ
糖尿病と歯周病は、一見別々の病気に思えますが、互いに悪影響を及ぼし合う密接な関係にあります。「歯周病の進行は血糖コントロールを難しくし、糖尿病が悪化すれば歯周病も進みやすくなる」というこの悪循環を断ち切るには、医療機関での治療に加えて、日常のセルフケアや生活習慣の改善が欠かせません。
糖尿病と診断された方は、かかりつけの歯科医にもそのことを必ず伝え、定期的な検診とクリーニングを受けましょう。お口の健康を守ることが、全身の健康、そして豊かな生活を守るための第一歩です。今日からできるセルフケアを始め、大切な歯と体を守っていきましょう。
参考文献
- Anderson MH, Ait-Aissa K, Sahyoun AM, Abidi AH, Kassan M.Akkermansia muciniphila as a Potential Guardian against Oral Health Diseases: A Narrative Review.Nutrients,2024,16,18,p.3075.
- Norhammar A, Näsman P, Buhlin K, de Faire U, Ferrannini G, Gustafsson A, Kjellström B, Kvist T, Levring Jäghagen E, Lindahl B, Nygren Å, Näslund U, Svenungsson E, Klinge B, Rydén L.Does Periodontitis Increase the Risk for Future Cardiovascular Events? Long-Term Follow-Up of the PAROKRANK Study.J Clin Periodontol,2025,52,1,p.16-23.