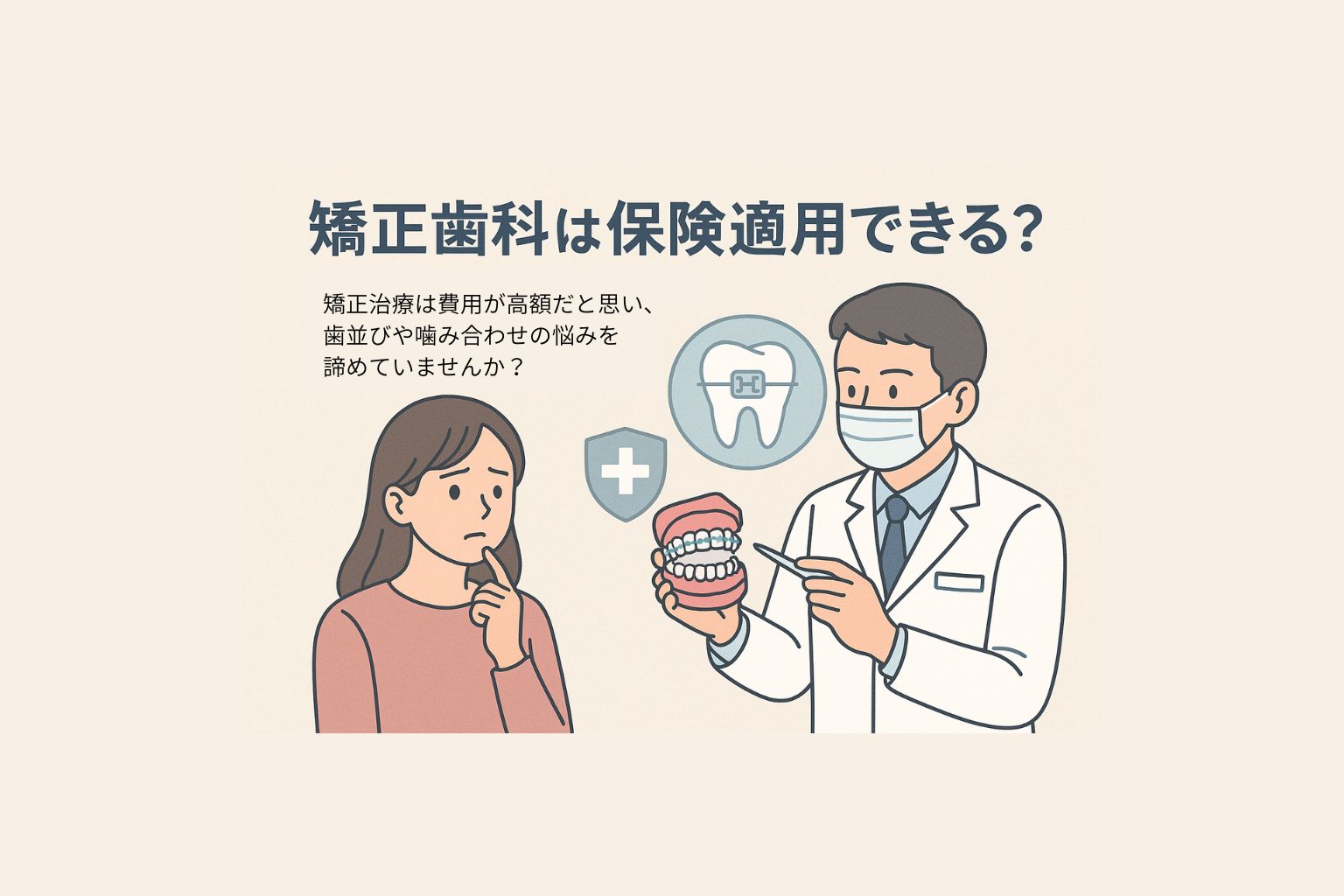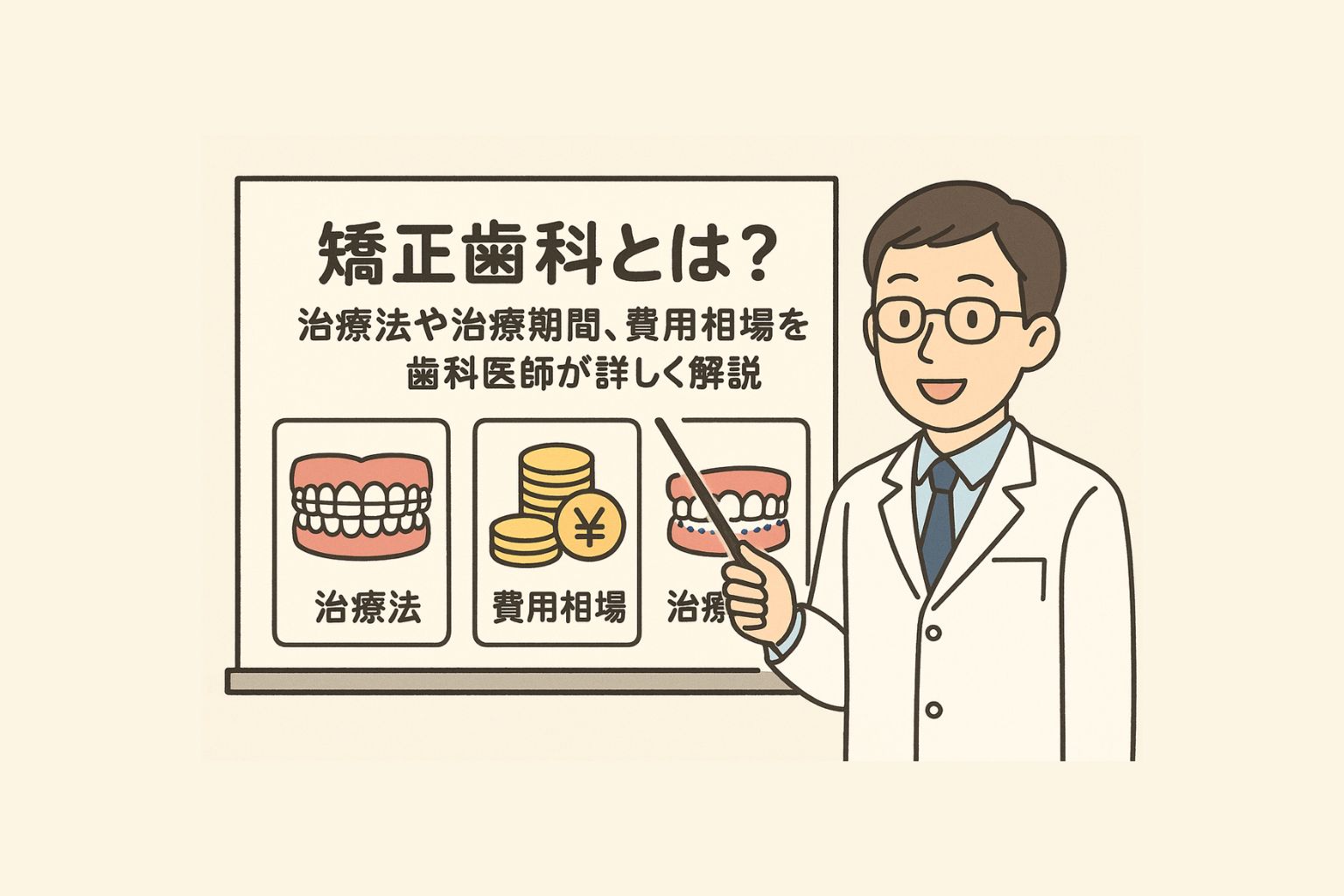矯正治療は費用が高額だと思い、歯並びや噛み合わせの悩みを諦めていませんか?
実は、すべての矯正治療が自費になるわけではありません。顎変形症などで外科手術が必要なケースや、先天的な疾患による噛み合わせの異常など、厚生労働省が定める条件を満たす場合は健康保険が適用されることがあります。
この記事では、保険が適用される3つの具体的な条件や対象となる症例、高額療養費制度や医療費控除などの費用を抑える仕組みについて解説します。ご自身のケースが保険の対象になるかどうかを理解でき、矯正治療を前向きに検討できるようになります。
関連記事はこちら
歯科矯正治療の保険適用の3条件
矯正治療の多くは、見た目を整える審美目的と判断され、健康保険の対象外(自費診療)です。
しかし、病気の治療と認められる特定の条件を満たす場合は、保険が適用されるケースがあります。健康保険の適用となる条件として、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 条件1: 厚生労働大臣が定める特定疾患がある場合
- 条件2: 顎変形症(外科手術が必要なケース)
- 条件3: 前歯・小臼歯の萌出不全による咬合異常
条件1:厚生労働大臣が定める特定疾患がある場合
矯正治療で保険が適用される1つ目の条件は、厚生労働大臣が定めた「特定疾患」が原因となっている場合です。生まれつきの病気により、歯並びや噛み合わせに異常が生じているケースです。
具体的な対象疾患は、以下のとおりです。
- 唇顎口蓋裂(しんがくこうがいれつ):唇や上顎が割れた状態で生まれる先天性の疾患で、歯の位置や数に影響が出やすい
- ダウン症候群:染色体異常により顎が小さくなる傾向があり、歯並びに乱れが起こることがある
- 6歯以上の先天性部分無歯症:生まれつき永久歯が6本以上ないため、歯のバランスを整える必要がある
上記は一例であり、対象となる疾患は50種類以上あります。特定疾患は、食事や発音などの機能面に影響を及ぼすことがあるため、治療が「医療行為」と認められ、健康保険が適用されます。
条件2:顎変形症(外科手術が必要なケース)
2つ目の条件は「顎変形症(がくへんけいしょう)」と診断されることです。また、治療のために外科手術を伴う矯正治療が必要な場合に限られます。歯を動かすだけでは改善が難しく、顎の骨を外科的に動かす重度のケースです。
顎変形症には、主に以下のような症状があります。
- 下顎前突:重度の受け口
- 上顎前突:出っ歯
- 顔面非対称:上下の顎が左右にずれている
- 開咬:奥歯で噛んでも前歯が噛み合わない
- ガミースマイル:笑った時に歯茎が過剰に見える
治療は、手術の前後で矯正治療を行い、以下の流れで進めます。
- 1. 手術前に歯並びを整える(術前矯正)
- 2. 顎の骨を手術で動かす
- 3. 手術後に噛み合わせを微調整する(術後矯正)
顎変形症の治療は、噛む・話すなどの機能を改善し、日常生活の快適さを取り戻すことを目的としています。手術に保険が適用されることで費用面の不安が軽くなり、治療を前向きに受け入れる患者さんが増えることも報告されています。(※1)
条件3:前歯・小臼歯の萌出不全による咬合異常
前歯や小臼歯の永久歯が三本以上生えてこない場合で、歯ぐきの中に埋まった歯を外科的に露出させる「埋伏歯開窓術」が必要なケースは、矯正治療が保険適用となります。
これは見た目の改善ではなく、噛み合わせや咀嚼、発音といった機能を回復するための医療的処置として認められているためです。
治療は口腔外科と矯正歯科が連携して行い、まず手術で歯を露出させた後、矯正装置を用いて歯を少しずつ引き出し、正しい位置に整えます。放置すると歯列のバランスや顎の成長に影響するため、早期の診断と治療が重要です。
指定医療機関(顎口腔機能診断施設)で治療する必要あり
保険適用でインプラントや外科的治療を受けるには、厚生労働省から「顎口腔機能診断施設」として指定を受けた医療機関で治療する必要があります。この制度は、設備や専門体制が整った医療機関で、安全に治療を行うことを目的としています。
顎変形症や唇顎口蓋裂などが保険の対象であっても、指定を受けていない一般の歯科医院で治療を受けた場合は保険が適用されません。指定医療機関には次のような特徴があります。
- 厚生労働省が定めた人員・設備などの施設基準を満たしている
- 矯正歯科や口腔外科など複数の診療科が連携して治療する
- 複雑な症例にも対応できる専門的な診断力と技術を備えている
指定医療機関は、地方厚生局のWebサイトなどで確認できます。保険適用での矯正治療を希望する場合、まずは近隣の指定施設を調べ、相談してみることをおすすめします。
保険適用の対象となる矯正治療の症例

矯正治療が保険適用になるのは、見た目の改善ではなく、食事や発音などの機能に支障がある場合です。ここでは、保険適用の対象となる具体的な症例について、子どもと大人それぞれに分けて解説します。
子どもの症例(唇顎口蓋裂など)
子どもの矯正治療で保険が適用されるのも、見た目の改善ではなく、成長や生活に支障をきたす機能面の問題がある場合です。
生まれつきの疾患などで顎の骨の発達や歯並びに問題が生じている場合は、機能回復を目的として保険が認められることがあります。噛む力や発音への影響が大きく、放置すると成長期の発達にも関わるため、早期の治療が推奨されます。
代表的な疾患は次のとおりです。
| 唇顎口蓋裂 (しんがくこうがいれつ) |
|
|---|---|
| 6歯以上の 先天性部分無歯症 |
|
| ダウン症候群 |
|
※個々の症状により適用の可否が異なる場合があります。
大人の症例(顎変形症など)
大人の矯正治療で保険適用となる代表例が、顎変形症です。歯並びだけでなく、顎の骨の大きさや形、位置が大きくずれている状態です。顎変形症には、主に以下のような症状が見られます。
- 重度の受け口(下顎前突)や出っ歯(上顎前突):歯が傾き、顎の骨全体が大きく前後にずれている
- 顔の歪み(顔面非対称):左右の顎の大きさや形が異なり、顔の中心線がずれている
- 前歯が噛み合わない(開咬):前歯の間に隙間ができ、食べ物を噛み切りにくい
これらの状態では、うまく咀嚼できず胃腸に負担がかかったり、顎関節に過度な力が加わったりして痛みや頭痛を引き起こすこともあります。
また、咬合の不調や片側咀嚼を引き起こし、歯周組織に負担をかけることで歯周病のリスクを高める可能性が指摘されています。顎変形症などによる顎機能の障害は、食事や会話など日常生活の質(QOL)を低下させる要因となります。(※2)
矯正治療で活用できる制度
矯正治療は費用の負担が大きい分、公的な支援制度を利用することが大切です。保険適用の有無にかかわらず、条件を満たせば自己負担を軽減できる場合があります。
ここでは、代表的な2つの制度「高額療養費制度」と「医療費控除」について解説します。
高額療養費制度
高額療養費制度は、医療費の家計負担が重くなりすぎないようにする公的制度です。
矯正治療では、顎変形症の外科手術や入院など、短期間に医療費が高額になることもあります。1か月(月初から月末まで)に支払った医療費には上限が設けられており、その上限を超えた分が後日払い戻されます。
高額療養費制度の適用は、健康保険が適用される場合で、自己負担の上限額は、年齢や所得によって区分されています。以下は70歳未満の方の目安です。
| 年収約1,160万円~ (区分ア) |
252,600円 + (医療費-842,000円)×1% |
|---|---|
| 年収約770~約1,160万円 (区分イ) |
167,400円 + (医療費-558,000円)×1% |
| 年収約370~約770万円 (区分ウ) |
80,100円 + (医療費-267,000円)×1% |
| ~年収約370万円 (区分エ) |
57,600円 ※一律の上限額となります |
| 住民税非課税者 (区分オ) |
35,400円 ※一律の上限額となります |
- ※表内の「医療費」とは、保険適用される診療費用の総額(10割)を指します。
- ※入院時の食事代や差額ベッド代、自由診療分は対象外となります。
事前に「限度額適用認定証」を申請し、医療機関の窓口で提示すると、支払いを上限額までに抑えることができます。申請先は、加入している健康保険組合や国民健康保険の窓口です。
ただし、マイナ保険証をお持ちの方は限度額適用認定証申請書の提出は不要です。
医療費控除
医療費控除は、納めた税金の一部が戻ってくる仕組みで、年間の医療費が10万円(所得200万円未満は所得の5%)を超える方が対象になります。1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の合計が一定額を超えた場合、確定申告を行うことで、所得税や住民税の負担が軽減されます。
この制度の大きな特徴は、自費診療の矯正治療も対象になる可能性があることです。ただし、単に見た目を美しくするための審美目的の治療は対象外です。
噛み合わせが悪く咀嚼に問題がある場合など、機能回復を目的とする場合に限られます。治療目的としての歯科矯正なのかは、歯科医師の専門的な診断に基づいて判断されます。
医療費控除の対象となる費用には、以下のようなものがあります。
| 治療費 |
|
|---|---|
| 交通費 |
|
- 対象外となるもの:自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車場代、審美目的(見た目の改善のみ)の矯正費用。
- 交通費は領収書が出ない場合が多いため、「通院日、経路、金額」をメモに残しておく必要があります。
- デンタルローン等の金利・手数料部分は控除の対象外です。
医療費控除を受けるには、ご自身で確定申告を行う必要があります。申告には医療費の領収書や交通費の記録が必須となるため、大切に保管しておきましょう。
費用や制度について不明な点は、通院している病院やクリニックにご相談ください。
矯正歯科における保険診療と自費診療の違い
矯正治療には病気の治療を目的とする保険診療と、見た目の美しさの改善を目的とする自費診療があります。両者の違いについて、以下の3つの観点で解説します。
- 治療費用
- 使用できる装置
- 治療期間・通院回数
治療費用
保険診療と自費診療の大きな違いは、治療にかかる費用です。それぞれの目的と費用の仕組みを理解しておくことで、治療計画を立てやすくなります。
保険診療は、顎変形症などの外科手術を伴う治療や特定の疾患に限って適用され、自己負担は原則3割です。
自費診療は、見た目の改善を含むすべての矯正治療が対象となり、費用は全額自己負担です。治療内容や装置によって金額の幅が大きく、医院ごとに費用設定が異なります。
それぞれの特徴を比較すると次のようになります。
| 保険診療 | 自費診療 | |
|---|---|---|
| 目的 | 機能回復(病気の治療) | 審美性の向上を含む、生活の質の改善 |
| 自己負担割合 | 原則3割 | 全額(10割) |
| 治療費の目安 | 約30~50万円 | 約60~150万円以上 |
| 活用できる制度 | 高額療養費制度 | 医療費控除 (治療目的の場合のみ) |
- 上記費用は一般的な目安であり、症例や医療機関によって異なります。
- 保険診療の適用には、厚生労働大臣が定める特定の疾患等の条件を満たす必要があります。
使用できる装置

保険診療と自費診療では、治療目的が異なるため、使用できる矯正装置の種類にも大きな違いがあります。保険診療は病気の治療による機能回復が目的のため、使用できる装置や材料は国の基準で定められています。
代表的な装置は、金属製のメタルブラケットです。丈夫で効率的に歯を動かせますが、見た目よりも機能性が優先されます。そのため、目立ちにくい装置を選ぶことはできません。
一方で、自費診療では見た目や快適さにも配慮した装置を選択できます。白や透明の素材を使った審美ブラケットは、装着しても目立ちにくいのが特徴です。歯の裏側に装置を取り付ける舌側矯正は、外からはほとんど見えません。
透明で取り外しができるマウスピース型矯正もあります。ライフスタイルや希望に合わせて、より自然で快適な治療を選ぶことができます。どの方法を選ぶ場合でも、装置を装着している間は毎日の口腔ケアを丁寧に行うことが大切です。
治療期間・通院回数
保険診療の場合、治療手順がある程度標準化されています。外科手術を伴う顎変形症の治療では、以下のような段階を踏んで進めるのが一般的です。
- 1. 術前矯正(約1~1年半):手術で顎の骨を動かしたときに、正しい位置で噛み合うように歯並びを整える
- 2. 外科手術(入院約1~2週間):顎の骨を切り、正しい位置に移動させる
- 3. 術後矯正(約1~2年):手術後に噛み合わせの最終的な微調整をする
治療全体で約2〜3年かかることが多く、通院は月1回が目安です。
自費診療は患者の希望に合わせて柔軟に計画を立てられます。症状や装置によって期間は異なりますが、全体で1〜3年程度が目安です。部分的な矯正なら数か月で完了することもあります。通院頻度は1〜3か月に1回ほどで調整可能です。
どちらの治療でも、歯を動かした後は「保定期間」が必要です。リテーナーを装着し、歯並びが元に戻らないよう安定させます。治療期間はあくまで目安であり、口や歯の状態によって個人差があります。
まとめ
矯正治療は自費診療と思われがちですが、すべてが対象外ではありません。国が定めた特定の疾患や、外科手術が必要な顎変形症などに該当し、指定医療機関で治療を受ける場合は、保険が適用されます。
ご自身の歯並びが対象かどうかを自分で判断するのは難しいため、まずは矯正歯科や指定医療機関で、歯科医師の診断を受けましょう。高額療養費制度や医療費控除などを利用すれば、費用の負担を軽くできる場合もあります。
一人で悩まず、信頼できる歯科医師に相談しながら、自分に合った治療方法を見つけていくことが大切です。
参考文献
- Greenlee GM, Lewandowski L, Funkhouser E, Dolce C, Jolley C, Kau CH, Shin K, Allareddy V, Vermette M, Huang GJ. Treatment acceptance in adult patients with anterior open bite: A National Dental Practice-Based Research Network study. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 2024, 166, 4, 363-374.
- Bhoi T, Riza N, Pandey H, Iman S, Jadhav P, Malik R, Gupta S. Association between the severity of periodontitis and temporomandibular joint symptoms in patients requiring prosthodontic rehabilitation: A cross-sectional study. Cureus, 2025, 17, 6, e86493.
Related articles
関連記事
Ranking
話題の記事ランキング

医療コラム
【医師監修】内視鏡検査後の腹痛はいつまで続く?翌日仕事に行ける?長引く場合の対処法と注意点
仙台さいとう産業医事務所 代表産業医
齋藤 雄佑

医療コラム
【医師監修】内視鏡検査の後は何を食べればいい?消化に良い食事例とNGフードを紹介
わだ内科・胃と腸クリニック 院長
和田 蔵人

医療コラム
【医師監修】燃え尽き症候群(バーンアウト)はセルフチェックできる?結果との正しい向き合い方も解説
産業医
中村 拓也

医療コラム
【医師監修】内視鏡検査で便が出ないときはどうする?下剤を飲んでも出ないときの対処法と判断基準
わだ内科・胃と腸クリニック 院長
和田 蔵人

医療コラム
【医師監修】燃え尽き症候群の12段階とは?段階ごとの特徴と対処法を解説
産業医
中村 拓也

医療コラム
【医師監修】インフルエンザの潜伏期間は何日?発症のタイミングを解説
高座渋谷つばさクリニック 院長
武井 智昭

ドクターの素顔
順天堂医院 総合診療科の齋田医師が語る「人を診る」医療とは?病院での役割や受診の目安
順天堂医院:総合診療科 医局長
齋田 瑞恵

医療コラム
【医師監修】黒い便の原因と考えられる病気|注意すべき症状と受診タイミングを解説
わだ内科・胃と腸クリニック 院長
和田 蔵人

医療コラム
【医師監修】内視鏡検査の後に運転しても大丈夫?鎮静剤使用の有無で異なる注意点を解説
わだ内科・胃と腸クリニック 院長
和田 蔵人

医療コラム
【医師監修】男性がキレるのは更年期障害のサイン?
イーヘルスクリニック新宿院 院長
天野 方一
Search
病気を調べる