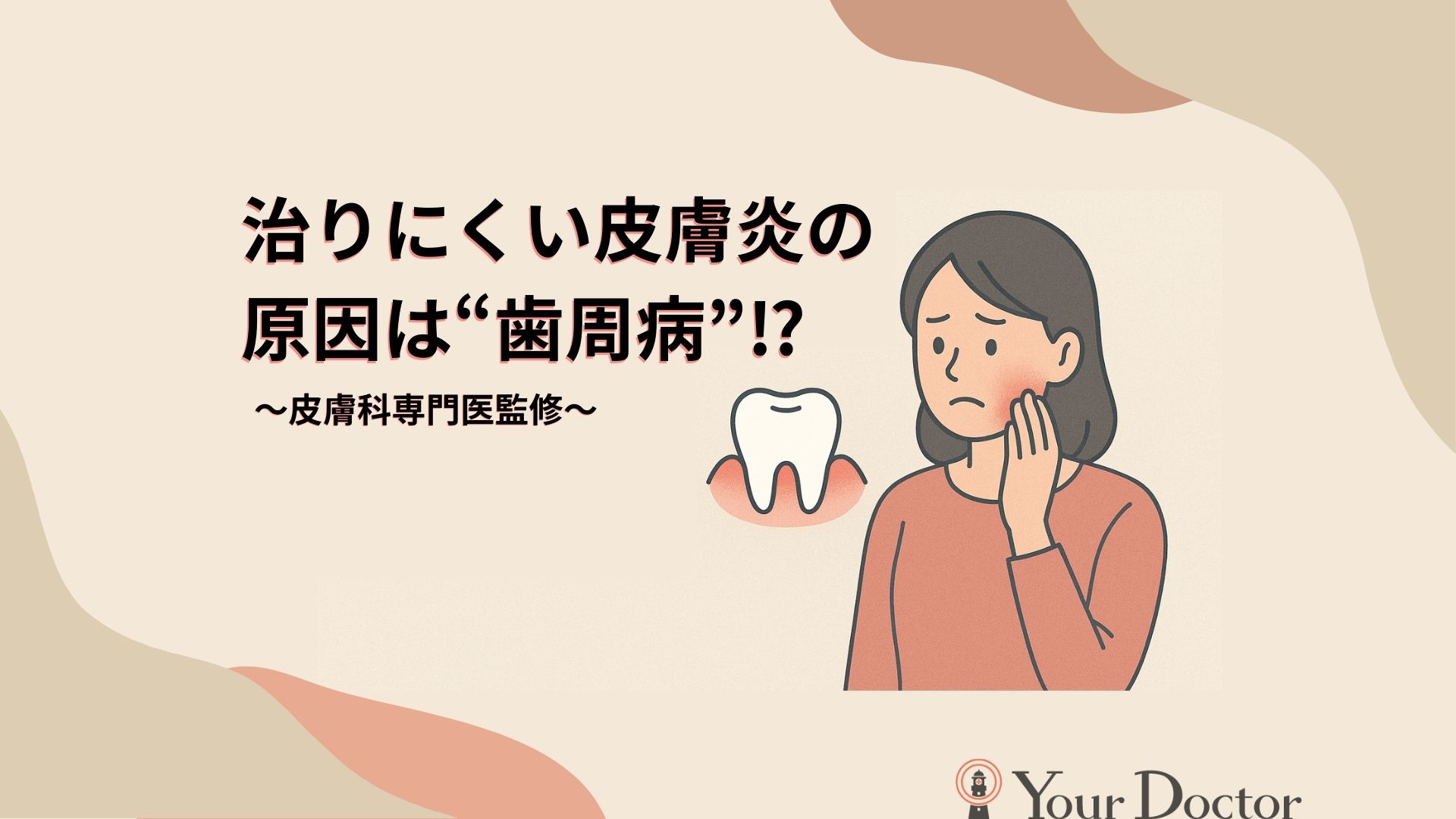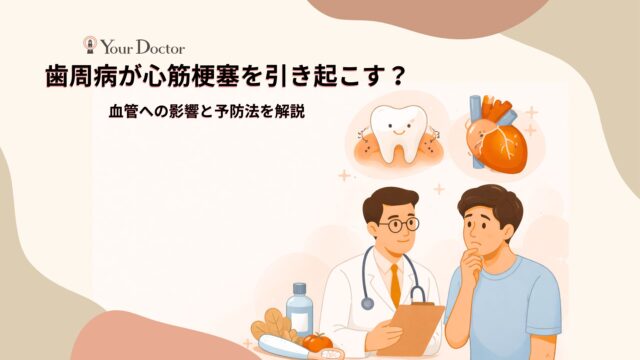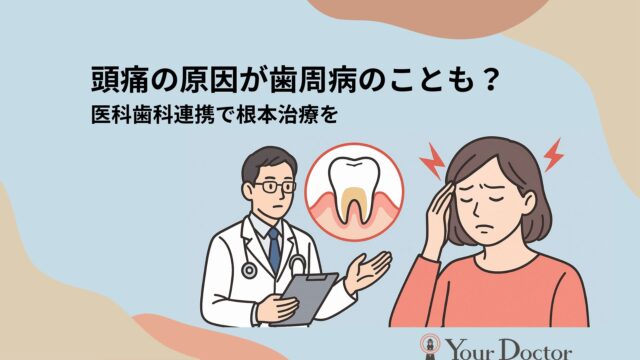皮膚科で処方された薬を使っても、肌荒れが治らない。良くなっても、すぐにぶり返してしまう。そんな皮膚トラブルに悩まされていませんか?
皮膚炎の原因として、歯周病が関与している可能性があります。口の中の細菌が血流に乗り、皮膚の炎症を悪化させることがあるからです。
この記事では、歯周病が皮膚炎を悪化させるメカニズムや、医科と歯科で連携して治療を進めていく重要性を解説します。
目次
歯周病が皮膚炎を悪化させる3つの理由
歯周病が皮膚炎を悪化させる主な3つの理由は、以下のとおりです。
- 病巣感染
- 免疫力の低下
- 関連性の高い皮膚疾患
①病巣感染
病巣感染(びょうそうかんせん)は、体の一部分の慢性の炎症(病巣)から細菌や毒素が血中に入り、全身を巡る現象です。そのため離れた臓器や組織に新たな病気を引き起こす原因になります。
歯周病は、病巣感染の原因の一つとされており、以下のような流れで起こるとされています。
- 1. 歯周病菌が血管へ侵入する
- 2. 血流に乗って全身を巡る
- 3. 皮膚で炎症を引き起こす
歯周病になると、歯ぐきは炎症を起こし腫れてきます。炎症を起こし歯ぐきの毛細血管はもろく、歯磨きなどのわずかな刺激でも簡単に出血する状態です。このとき出血した血管から、歯周病菌が血液の中に侵入してしまいます。
血中に入った歯周病菌は、心臓によって全身へと巡っていきます。これは、歯原性菌血症(しげんせいきんけつしょう)と呼ばれる現象です。
歯原性菌血症になると、血流に乗り皮膚に行き着いた歯周病菌や、菌が作り出す毒素、炎症性物質が皮膚の免疫細胞を刺激します。結果的に、皮膚に直接炎症が起きたり、もとの皮膚炎が悪化したりするのです。
②免疫力の低下
歯周病は、慢性炎症が口の中で続いている状態です。このとき体は、常に免疫システムを稼働させていますが、長期間にわたると、免疫システム全体が疲弊しバランスが崩れてしまいます。
免疫バランスが崩れると、無害な物質に反応してアレルギー症状が悪化する他、外部からの刺激や感染に弱い状態になり、肌荒れや感染症を起こしやすくなります。
③関連性の高い皮膚疾患
以下のように歯周病が関係していると考えられる皮膚の病気もあり、なかなか治らない場合は歯周病が原因になっている可能性があります。
歯周病との関連が考えられる皮膚疾患
- 掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)
- 手のひらや足の裏に膿を持つ小さい膿疱が繰り返しできる疾患です。
- 尋常性乾癬(じんじょうせいかんせん)
- 皮膚が赤く盛り上がり、銀白色のかさぶたがはがれ落ちる特徴があります。
- 滴状乾癬(てきじょうかんせん)
- 小型の赤いカサカサした皮膚の盛り上がりが体を中心に散発します。数週間で自然に引くことが多いですが、長引くと上記の尋常性乾癬に移行することもあります。
- 口囲皮膚炎
- 口まわりのニキビのようなプツプツや赤みが繰り返しでき、ステロイド外用薬が効かないことが特徴です。
蕁麻疹(じんましん)、結節性紅斑(けっせつせいこうはん)なども歯周病に関連する病気と考えられています。
歯周病の疑いを確認するセルフチェックリスト
口の中のちょっとした変化に気づくことが大切です。気になる方は、下のチェックリストで当てはまる項目がないか確認してみましょう。
歯周病の疑いを確認するセルフチェックリスト
- 起床時の口腔内がネバネバする
- 歯磨きすると歯ぐきから血が出ることがある
- 歯ぐきが赤く腫れるかブヨブヨしている
- 歯ぐきを押すと白い膿のようなものが出る
- 他人から口臭を指摘されたことがある
- 歯が長くなったように見える
- 歯の間にすき間ができ食べ物が挟まりやすくなった
- 硬いものが以前より噛みにくくなった
- 指で押すとグラグラする歯がある
チェックリストで3つ以上当てはまる場合は、歯周病が始まっている、または進行している可能性があります。
特に、「膿が出る」「歯がグラつく」といった症状がある場合は、できるだけ早めに受診しましょう。
歯科と皮膚科の連携による皮膚炎の治療の流れ
ここまで述べたように皮膚症状と歯周病の関連性は高いため、皮膚科と歯科が協力し治療を進める医科歯科連携が重要です。歯科と皮膚科が連携して皮膚炎の治療を進める際の流れを、4つのステップにわけて説明していきます。
- 受診の判断基準
- 原因を特定する検査(口腔内検査・皮膚生検・血液検査)
- 歯科の治療内容
- 皮膚科の治療内容
①受診の判断基準
以下のような状況に当てはまる場合は、歯科受診を検討してみても良いでしょう。
- 皮膚科の治療で改善しない
- 特定の皮膚炎と診断された
- 口の症状も気になっている
- 金属アレルギーの可能性がある
これらのサインは、口腔内の問題が皮膚に影響している可能性を示しています。特定の皮膚炎の代表例は、掌蹠膿疱症や尋常性乾癬です。
②原因を特定する検査
皮膚炎の原因を突き止めるために、歯科と皮膚科でどのような検査が行われるのか、以下の表で解説します。
歯科の検査
| 口腔内検査 |
|
|---|---|
| レントゲン検査 |
|
| 口腔内金属の確認 | 詰め物や被せ物の金属の種類 |
皮膚科の検査
| 皮膚生検 |
|
|---|---|
| 血液検査 |
|
| パッチテスト |
アレルギーの原因 (金属アレルギーが疑われる場合) |
上記の検査結果を歯科医と皮膚科医が共有し、治療方針を一緒に考えていきます。
③歯科の治療内容
歯周病が皮膚炎の原因や悪化させる一因と判断された場合、歯科では原因を取り除く治療を行います。
基本の治療は、歯周病の原因になる歯石やプラーク(細菌の塊)の除去です。専用の器具を使い歯周ポケットの深くまできれいにしていきます。歯科医院での治療だけでなく、自身でのセルフケアも重要です。
歯の根の先に膿がたまっている場合は、細菌に感染した神経などを取り除き、根の中をきれいにする根管治療を行います。
④皮膚科の治療内容
皮膚科では、皮膚の症状を和らげるための治療を行います。治療の内容を以下の表にまとめました。
| 治療方法 | 内容 |
|---|---|
| 外用療法(塗り薬) |
|
| 内服療法(飲み薬) |
|
| スキンケア指導 |
保湿剤で皮膚の水分を保持しバリア機能を回復させる |
歯周病と皮膚炎の根本改善のために大切なこと
皮膚の炎症を何度もくり返すときは、表面だけでなく原因にも目を向けることが大切です口の中のトラブルが関係している場合もあるため、歯や歯ぐきの状態も一度チェックしてみましょう。
これから、根本改善につながる内容を3つ紹介していきます。
- 歯科で歯周病の原因を治療する
- 皮膚科で皮膚の炎症をコントロールする
- 医科と歯科の連携で再発を防ぐ
①歯科で歯周病の原因を治療する
歯科治療の目的は、細菌や病巣の原因の除去です。
プラークコントロールは原因除去治療とも呼ばれ、歯周病の原因であるプラークや歯石を専用の機械で取り除きます。歯周ポケットの奥深くの汚れまで除去していきます。
歯の根の先に膿がたまる根尖病巣(こんせんびょうそう)のように、細菌が感染している場所があれば、その部分を取り除く根管治療などをしていきます。
歯科でのケアだけではなく、自身での歯磨きが治療の経過に影響するため、正しい歯磨きの方法やデンタルフロスなどの補助器具の使い方を覚えて実践することも大切です。
②皮膚科で皮膚の炎症をコントロールする
皮膚科の治療は、肌が本来持つ健康な状態を取り戻すために行います。歯科で根本原因の治療を進めても、かゆみや痛みで眠れないような状態では、治療の継続自体が困難になってしまいます。
皮膚科での治療には、炎症を抑える作用があるステロイド外用薬や、抗ヒスタミン薬(飲み薬)、炎症が激しく生活に支障をきたす場合はステロイド内服薬や免疫抑制剤を使います。この薬により症状が和らぎ、無意識のかき壊しも防げる可能性が高まります。
他には、皮膚本来のバリア機能を回復させるために保湿剤を使用します。炎症をコントロールしたうえで保湿剤を正しく使うことでバリア機能を整えれば、外部からの刺激やアレルゲンの侵入を防ぐことができます。
③医科と歯科の連携で再発を防ぐ
歯周病が関連する皮膚炎の治療では、歯科と皮膚科、どちらか一方の治療だけでは十分ではない場合が多いです。根本的な改善と、再発防止のためには、両科が専門性を持ち寄り協力し合う医科歯科連携が大切です。
両科の医師がそれぞれの視点から皮膚の状態を評価し、治療方針や経過を情報共有することで、より精度の高い治療が見込めます。
医科歯科連携のメリットは以下のとおりです。
- 正確な原因の特定
- 最適な治療計画の立案
- 再発の早期発見と予防
それぞれの専門分野から炎症や免疫の状態をコントロールすることで、体全体のバランスを整え、病気の根本的な原因を改善できる可能性があります。
患者さん自身も、皮膚科医には口の状態を、歯科医には皮膚の症状を伝えることを意識してみましょう。
まとめ
皮膚科の治療を続けても改善しない原因は、歯周病によるものかもしれません。歯周病菌による慢性的な炎症が全身に広がり、皮膚の症状を悪化させることが知られています。
根本的な改善のためには、皮膚科での対症療法と、歯科での原因治療を同時に進める医科歯科連携が大切です。
長引く肌トラブルに悩んでいる方は、皮膚科医だけでなく歯科医院でも一度相談を受けてみましょう。