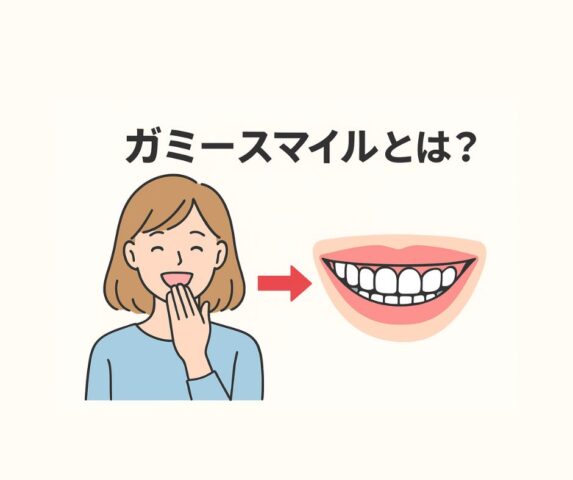歯周病は、厚生労働省の資料によると、日本のおよそ8割の成人に、歯周病の兆候または予備軍としての所見があるとされています。(※1)痛みなどの自覚症状がほとんどないため、「沈黙の病気(Silent Disease)」とも呼ばれています。
気づいたときには歯を支える大切な骨が溶けているケースもあります。「自分は大丈夫」という思い込みは危険なサインです。喫煙やストレス、全身の病気などが、気づかないうちに症状を悪化させている可能性があります。
この記事では、歯周病の本当の原因から症状、治療法、今日から実践できる予防法までわかりやすく解説します。手遅れになる前に、ご自身の歯を守るための正しい知識を身につけましょう。
歯周病とは歯ぐきと歯を支える骨の病気
歯周病とは、歯の土台である歯ぐきやあごの骨が、細菌によって静かに壊されていく病気です。歯周病の進行度は、以下の「歯肉炎」と「歯周炎」に分類されます。
| 段階 | 特徴 | 炎症の範囲 | 骨への影響 | 回復の可能性 |
|---|---|---|---|---|
| 歯肉炎 | 炎症が歯ぐきだけに留まっている状態 | 歯ぐきのみ | なし | 高い(元に戻せる) |
| 歯周炎 | 炎症が歯を支える骨にまで進行し歯周ポケットが深くなる | 歯ぐきと骨 | 骨が溶ける | 低い(現状維持が目標) |
進行すると骨の吸収が進み、歯の保存が難しくなるため、早期の予防とケアが重要です。歯科医院での定期検診は、歯周病から歯と全身の健康を守る基本となります。
歯周病の原因
歯周病は単に「歯磨き不足」だけで起こるものではありません。歯周病になってしまう主な原因は、以下の4つです。
- ① プラーク内の細菌(歯垢・歯石の蓄積)
- ② 喫煙・ストレスなど生活習慣の乱れ
- ③ 糖尿病・心疾患などの全身疾患
- ④ ホルモンバランスの変化
①プラーク内の細菌(歯垢・歯石の蓄積)
歯周病の主な原因は、プラーク(歯垢)に潜む細菌です。プラークは細菌が作るネバネバの塊で、わずか1mgに1億個もの細菌が存在するといわれています。
放置すると唾液の成分と結びつき、短期間で歯石に変化し、細菌の温床となります。歯周病の悪化につながる仕組みは、次のとおりです。
- 1. プラーク内の細菌が歯ぐきに炎症を起こす毒素を出す
- 2. 歯周病では、口の中が悪玉菌優勢になり細菌叢が変化する
- 3. プラークが約2~3日で硬い歯石に変化する
- 4. 歯石の表面はザラザラで、細菌がさらに付着しやすくなる
- 5. 歯周ポケットが深くなり、骨を溶かす菌が増殖する
歯周病の予防と治療の基本は、プラークと歯石をいかにコントロールするかです。
②喫煙・ストレスなど生活習慣の乱れ
歯周病は細菌だけでなく、生活習慣の影響も大きく受けます。特に「喫煙」と「ストレス」は、歯周病を悪化させる代表的なリスク因子であり、以下のような影響があります。
| 生活習慣 | 主な影響 |
|---|---|
| 喫煙 |
・血流が悪化して組織が酸欠になり、治療効果が出にくい ・免疫力が低下し、細菌への抵抗力が弱まる ・血流の悪化により、出血サインが隠されて、気づかぬうちに重症化する |
| ストレス |
・免疫機能が低下して感染リスクが高まる ・唾液の分泌が減り、自浄作用が弱まる ・歯ぎしりや食いしばりを誘発し、歯を支えている骨に過剰な負担がかかる |
喫煙やストレスを軽視すると、歯周病が知らない間に進行してしまう危険があります。生活習慣を見直すことも、治療や予防に欠かせません。
③糖尿病・心疾患などの全身疾患
歯周病はお口の病気に留まらず、全身の健康にも深く関わります。特に糖尿病は、互いに悪化させる「負の相関関係」があります。
相互作用によって、以下のような影響があります。
| 相互作用 | 主な影響 |
|---|---|
| 糖尿病が歯周病を悪化させる |
・免疫力が低下し、細菌感染しやすい ・組織の修復力が落ち、重症化しやすい ・「糖尿病の第6の合併症」と呼ばれる |
| 歯周病が糖尿病を悪化させる |
・炎症性物質が血流に乗って全身に広がる ・インスリンの働きを妨げ、血糖コントロールが困難になる |
糖尿病管理には、歯周病治療を含めた口腔ケアが不可欠です。また、歯周病は、心血管疾患や誤嚥性肺炎にも関連するため、注意が必要です。歯周病菌が血流に入り、血管壁で炎症を起こすと、動脈硬化や心筋梗塞のリスクが高まります。
唾液や食べ物とともに細菌が気管や肺に入り込むと、誤嚥性肺炎を引き起こします。特に飲み込む力が低下した高齢の方は、重症化することもあります。
④ホルモンバランスの変化
ホルモンバランスの変動は、女性の歯周病リスクを高める要因です。思春期や妊娠、出産、更年期などのライフステージごとに影響が異なります。
妊娠中は女性ホルモン(エストロゲン・プロゲステロン)が急増し、特定の歯周病菌が栄養源として増殖します。その結果、少量のプラークでも歯ぐきが腫れやすく出血を伴う「妊娠性歯肉炎」が起こります。
つわりによる歯磨き不足や食習慣の変化もリスクを高め、重度の場合は早産や低体重児出産のリスクにつながると報告されています。(※2)
思春期もホルモン分泌の活発化で歯ぐきの炎症を起こしやすく、更年期はホルモン低下により骨密度が減少し、歯槽骨にも影響します。唾液の分泌低下によるドライマウスも歯周病を悪化させます。
ホルモン変動の時期は、丁寧なセルフケアと定期的な歯科検診が欠かせません。
歯周病の症状
歯周病の初期段階に痛みはほとんどありませんが、体はサインを出しています。歯周病の主な症状は、以下の4つです。
- ① 歯ぐきからの出血や腫れ
- ② 口臭の不快・口の中のネバつき
- ③ 歯ぐきが下がって歯が長く見える
- ④ 歯がグラつき、うまく噛めない
ご自身のお口の状態と見比べながら、セルフチェックしてみてください。
①歯ぐきからの出血や腫れ
歯ぐきからの出血や腫れは、歯周病の初期症状です。痛みがないため軽視されがちですが、お口の健康状態を示すバロメーターであり、早期発見が大切です。
以下のようなサインには要注意です。
- 歯磨きやフロスで出血する
- 食事中に食べ物へ血が付着する
- 歯ぐきの色が赤や赤紫に変化する
- 歯ぐきが丸く腫れる
健康な歯ぐきは薄いピンクで引き締まり、通常の刺激では出血しません。プラークが溜まると細菌の毒素により炎症が起こり、歯肉炎につながります。
炎症によって血管の透過性が高まり、出血しやすくなります。初期段階であれば、歯科医院でのクリーニングと正しいセルフケアで健康を取り戻せる可能性が高いです。
②口臭の不快・口の中のネバつき
口臭や口の中のネバつきは、歯周病が進行しているサインです。炎症が続いて歯ぐきにすき間(歯周ポケット)ができると、その奥で細菌が増え、臭いの原因となるガスが発生しやすくなります。以下のような変化には注意が必要です。
- 朝起きたときに強い口臭がある
- 口の中がべたついて気持ち悪い
- 歯や舌に汚れがつきやすい
これらの変化は本人よりも周囲の人が気づくことも多く、口臭やネバつきが続くと日常生活での自信や人間関係に影響を及ぼします。だからこそ「一時的なもの」と軽視せず、早めに歯科医院を受診して原因を確かめることが大切です。
③歯ぐきが下がって歯が長く見える
歯ぐきが下がって歯が長く見えるのは、歯周病が進行しているサインです。本来隠れている歯の根元が露出するため、歯全体が伸びたように見えるだけでなく、見た目の印象にも悪影響を与えます。
歯の根の表面は刺激に敏感なため、冷たい飲み物や甘い食べ物でしみる知覚過敏の症状が出ることもあります。一度下がった歯ぐきは、自然に回復しにくいため、予防や早めの対応が何より重要です。
④歯がグラつき、うまく噛めない
歯がグラつくのは、歯周病がかなり進行しているサインです。歯を支える骨や歯ぐきが弱まり、歯をしっかり固定できなくなることで起こります。主な症状として、以下のような影響があります。
- 歯を指で押すと揺れる
- 食べ物をかむと痛みや不快感がある
- 硬いものや大きいものが噛みにくい
この状態がさらに進むと、自然に歯が抜けてしまうこともあります。歯のぐらつきは歯周病が最終段階に近い兆候であり、食事や会話などの日常生活の基本的な動作に大きな影響を与えます。そのため、違和感を放置せず早めの歯科受診が大切です。
歯周病の診断・検査方法
ここでは、歯周病の診断・検査方法をご紹介します。
- ① 視診
- ② 歯周ポケット検査
- ③ X線検査(レントゲン)
- ④ 動揺度検査
視診(歯ぐきの腫れ・出血の確認)
歯周病の診断は、まず口の中を直接観察することから始まります。健康な歯ぐきは薄いピンク色で引き締まっていますが、歯周病が進行すると赤く腫れたり、ブラッシングや軽く触れるだけで出血しやすくなります。
さらに、歯ぐきの形態や歯と歯ぐきの境目の状態、プラークや歯石の付着状況などもチェックポイントです。
歯周ポケット検査
歯周病の進行度を把握するために欠かせないのが、歯周ポケットの深さを測る検査です。専用の細い器具(プローブ)を歯と歯ぐきの間に挿入し、ポケットの深さを1本の歯につき6か所ほど測定します。
健康な歯ぐきでは2〜3mm程度ですが、歯周病が進むと4mm以上に深くなり、炎症や骨の破壊が疑われます。この数値をもとに、軽度・中等度・重度といった診断の目安を立て、治療方針を決定します。
X線検査(レントゲン)
歯周病は、歯を支える骨(歯槽骨)がどの程度吸収されているかを確認することが大切です。そのために行うのがX線検査です。レントゲン画像では、肉眼では見えない歯槽骨の高さや形態、炎症による骨の破壊範囲を把握できます。
初期段階では骨の変化は少ないですが、中等度以上になると骨の水平的な吸収や部分的な欠損が確認されます。視診やポケット検査と組み合わせることで、病態をより正確に評価でき、治療計画の立案に役立ちます。
動揺度検査
歯周病が進むと、歯を支えている顎の骨(歯槽骨)が徐々に失われ、歯がしっかり固定されなくなります。その結果、歯が揺れる「動揺」が大きくなっていきます。動揺度検査は、この歯のぐらつき具合を評価する検査です。
健康な歯でも、わずかに動く「生理的な揺れ」がありますが、歯周病が進行すると骨の支持が弱まり、揺れが顕著になります。動揺度は以下のように段階的に評価され、進行の指標として用いられます。
- M0(0度):正常範囲内のごくわずかな動き
- M1(1度):前後方向に軽度の動きがみられる
- M2(2度):前後・左右の複数方向に揺れる
- M3(3度):上下方向も含めて大きく動く
このように、数値化して評価することで治療の必要性や予後の見通しを判断することができます。
歯周病の治療法
歯周病と診断されても、病気の段階に応じた治療によって、大切な歯を守ることが可能です。歯科医院で行われる代表的な治療法は、以下の3つです。
- ● スケーリング・ルートプレーニング(歯石除去)
- ● 歯周外科治療(フラップ手術)
- ● 再生療法
スケーリング・ルートプレーニング(歯石除去)
歯周病治療の基本であり重要なのが、歯石を取り除く「スケーリング」と「ルートプレーニング」で、歯周基本治療とも呼びます。どちらも歯周病の原因であるプラークや歯石を徹底的に除去し、歯ぐきを健康に戻すための処置です。
処置の対象となる部位や目的には、以下のような違いがあります。
| 処置名 | 内容 | 使用する器具 | 効果 |
|---|---|---|---|
| スケーリング | 歯の表面に付着した歯石を除去 | 超音波スケーラー 手用スケーラー | 硬い歯石を効率的に取り除く |
| ルートプレーニング | 歯周ポケットの奥深くにある歯石や汚染層を除去し、歯根を滑らかに整える | 超音波スケーラー 手用スケーラー | プラークが再付着しにくい環境をつくる |
処置は通常、お口を4〜6つのブロックに分け、数回にわたって行われます。一度にすべての歯を治療すると時間が長くなり、食事にも支障が出るためです。必要に応じて局所麻酔を行うので、痛みが心配な方も安心です。
基本的な治療を行うことで歯ぐきの炎症と腫れが改善し、歯周ポケットが浅くなる効果が期待できます。
歯周外科治療(フラップ手術)
歯周病が進行し、歯周基本治療を行っても歯周ポケットが深く残る場合には、歯周外科治療が必要となります。代表的な方法が「フラップ手術」です。
フラップ手術は、麻酔後に歯ぐきを切開し、歯根を目視できるようにして深部の歯石や不良な組織を除去する治療です。原因を確実に取り除いた後は、歯ぐきを元の位置に戻して縫合し、清掃しやすい環境を整えます。
フラップ手術の目的は、歯周ポケットを浅くしてセルフケアを行いやすくし、再発を防ぐためです。治療後は歯ぐきの炎症や腫れが改善し、歯の寿命を延ばすことにもつながります。
再生医療
再生医療は、歯周病によって失われた骨や歯周組織を取り戻すことを目的とする治療です。外科治療が壊れた部分を掃除する処置であるのに対し、再生療法は失った組織を新しくつくり直す治療といえます。代表的な方法は以下の2つです。
- エムドゲイン法(保険適用外):歯の発育に関与するタンパク質を歯根表面に塗布し、骨や組織の再生を促す
- リグロスによる再生療法(保険適用):骨芽細胞や線維芽細胞を活性化させるリグロスを塗布し、骨や組織の再生を促す
- GTR法(保険適用):特殊な膜を設置して歯ぐきの侵入を防ぎ、骨が再生するスペースを確保する
いずれも条件が合った場合に適応される治療であり、すべての患者さんに行えるわけではありません。成功すれば、失われた歯槽骨や歯周組織の回復が期待でき、歯の寿命を延ばす可能性があります。
近年では、薬物送達システム(DDS)の研究も進み、病変部の環境に応じて薬を放出する新しい治療法も検討されています。(※3)
歯周病の予防法
歯周病は、「かからないこと」「再発させないこと」が大切です。今日から始められる歯周病の予防法として、以下の5つを解説します。
- ① 正しい歯磨き習慣を身につける
- ② デンタルフロスや洗口液を活用する
- ③ 歯科医院でメンテナンスを受ける
- ④ 睡眠・ストレス管理で免疫力を保つ
- ⑤ 禁煙と適度な運動でリスクを下げる
①正しい歯磨き習慣を身につける
歯周病予防の基本は、毎日の正しい歯磨きです。目的は、歯周病菌のすみかとなるプラークを取り除くことです。歯磨きの際は、以下のポイントを意識してください。
- 歯と歯ぐきの境目に毛先を45度で優しく当てる
- 幅5mm程度で小刻みに動かし、1本ずつ丁寧に磨く
- 強い力で磨かず、歯や歯ぐきを傷つけないよう注意する
- 奥歯の噛み合わせの面や裏側を意識して磨く
- 歯と歯の間、歯並びがデコボコした部分を重点的に磨く
- 歯ブラシはヘッドが小さめで毛の硬さは「ふつう」を選ぶ
- 歯ぐきが敏感な人は「やわらかめ」を使用する
毛先が開いた歯ブラシは1か月を目安に交換しましょう。歯科医院で磨き方の指導(TBI:Tooth Brushing Instruction)を受けると、セルフケアの質が向上します。
②デンタルフロスや洗口液を活用する
歯周病予防には、デンタルフロスや洗口液の併用も大切です。歯ブラシだけではプラークを完全に除去できず、残りの汚れを取り除くには補助的な清掃用具が必要です。
歯と歯のすき間が狭い方にはデンタルフロスが適しています。すき間が広い方や歯ぐきが下がってきた方、ブリッジを使用している方には歯間ブラシが適しています。特に汚れがたまりやすい就寝前の歯磨きに合わせ、毎日の使用を心がけてください。
洗口液は殺菌成分によって口内の細菌を減らし、プラークの付着を抑える役割を果たします。ただし洗口液だけでは汚れを落とせないため、歯磨きやフロスで物理的に清掃した後に使うことが大切です。
③歯科医院でメンテナンスを受ける
歯周病は、高血圧や糖尿病と同じ慢性疾患であり、生活習慣やケア次第で再発しやすいため、治療後のメンテナンスが大切です。歯科医院で行う主な内容は、以下のとおりです。
- 歯と歯ぐきの状態チェック
- 歯周ポケットの深さの測定
- 歯ぐきからの出血や腫れの確認
- 歯の揺れ具合(動揺度)のチェック
- 必要に応じてレントゲン撮影で骨の状態を確認
- 専門的なクリーニング(PMTC:Professional Mechanical Tooth Cleaning)
- セルフケアの確認と指導
これらは再発のサインを早期に見つけ、悪化を防ぐためのものです。PMTCでは、毎日の歯磨きでは落としきれないバイオフィルムを専用の機械で除去します。
メンテナンスの頻度はリスクに応じて異なりますが、一般的には3〜6か月に1回が目安です。定期的な管理を続けることが、歯周病の再発を防ぎ、自分の歯を1本でも多く守る方法です。
④睡眠・ストレス管理で免疫力を保つ
歯周病を防ぐにはお口のケアだけでなく、免疫力を保つ生活習慣も欠かせません。免疫力が低下すると歯周病菌が活発になり、炎症が悪化しやすくなるためです。特に意識したいのは次の2点です。
- 質の良い睡眠を心がける
- ストレスを上手に解消する
睡眠不足は免疫力を低下させる大きな要因です。睡眠中には体の修復や免疫機能の調整が行われるため、十分な睡眠時間を確保し、就寝前にスマートフォンやパソコンの使用を控えることが大切です。
過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、免疫力を下げます。また、無意識の歯ぎしりや食いしばりを引き起こして歯や歯周組織に負担をかけることもあります。自分に合ったストレス解消法を見つけることは、歯周病の予防につながります。
⑤禁煙と適度な運動でリスクを下げる
歯周病の進行を防ぐには、生活習慣の中でも「禁煙」と「適度な運動」が大切です。喫煙は歯周病につながるリスク要因であり、運動は全身の健康を支えることで歯周病への対策になります。
禁煙によって歯周病治療の効果は高まり、再発リスクを下げられます。ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動は、全身の血流を改善し、免疫力を高めるうえにストレス軽減にもつながります。
糖尿病をはじめとした生活習慣病の予防効果も期待できるため、日常生活の中に無理なく取り入れましょう。
まとめ
歯周病は、痛みなどの自覚症状がないまま静かに進行し、歯を失う原因になります。糖尿病をはじめとした全身の健康にも関わる怖い病気ですが、防げない病気ではありません。
毎日の丁寧なセルフケアと、歯科医院での定期メンテナンスによって進行を食い止め、健康な状態を維持できます。今は症状がない方でも、大切な歯と全身の健康を守るために、まずは気軽に歯科医院へ相談してみましょう。
参考文献
- 厚生労働省:「歯周疾患の有病状況」
- Foroughi M, Torabinejad M, Angelov N, Ojcius DM, Parang K, Ravnan M, Lam J. Bridging oral and systemic health: exploring pathogenesis, biomarkers, and diagnostic innovations in periodontal disease. Infection, 2025
- Sha Z, Wu Y, Zheng Y, Yang K, Gong X, Xuan L, Li X, Chen X. Advances in pH-responsive drug delivery systems for periodontitis treatment. Drug Deliv, 2025, 32(1), p.2522109.