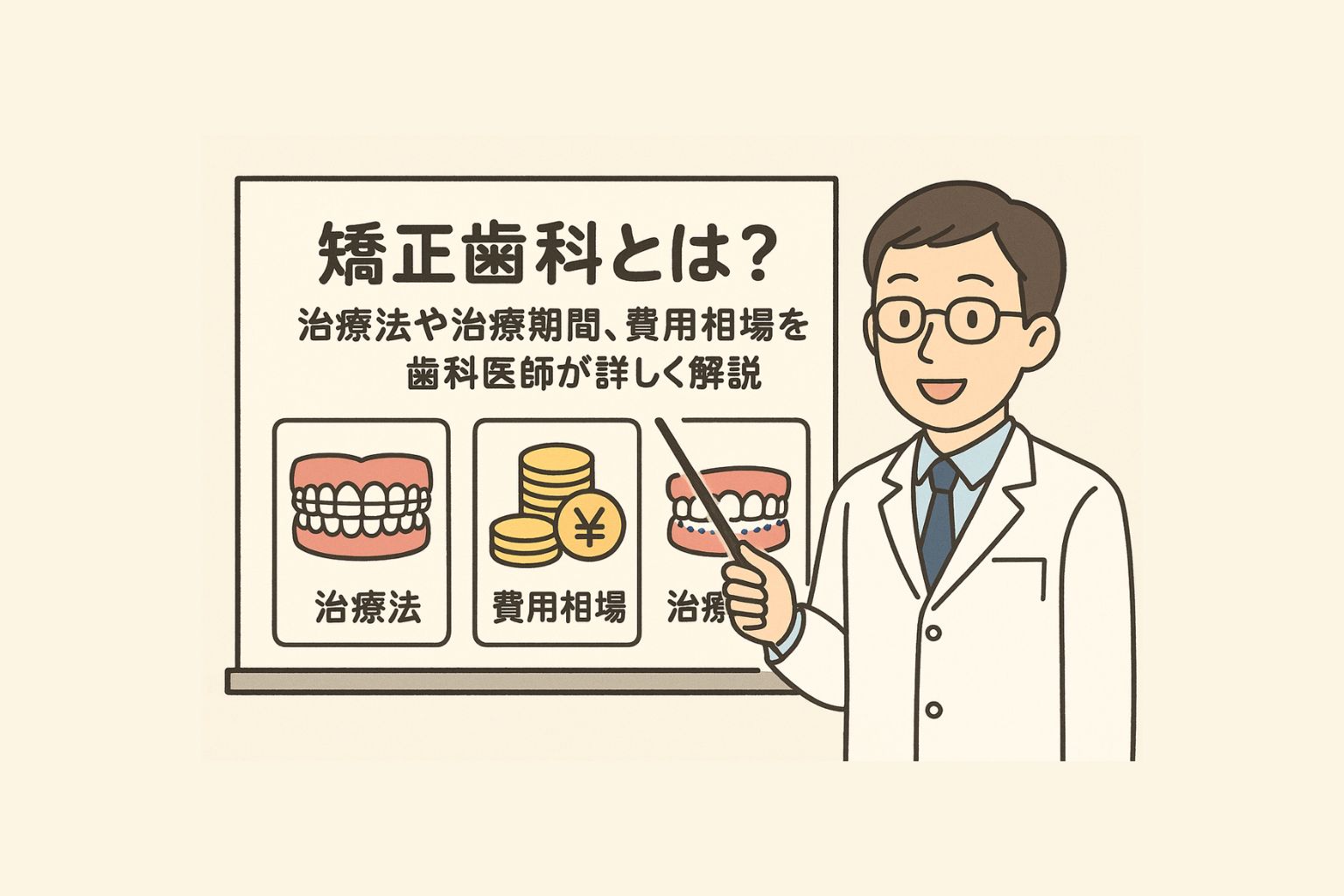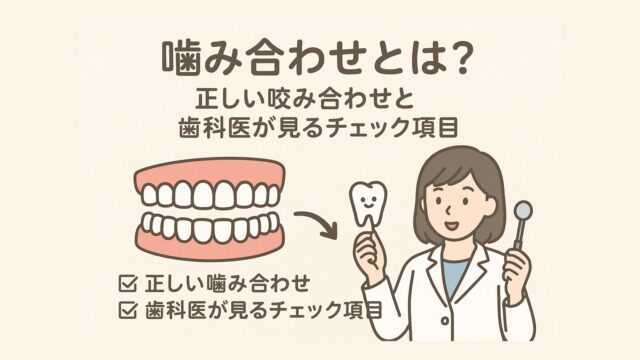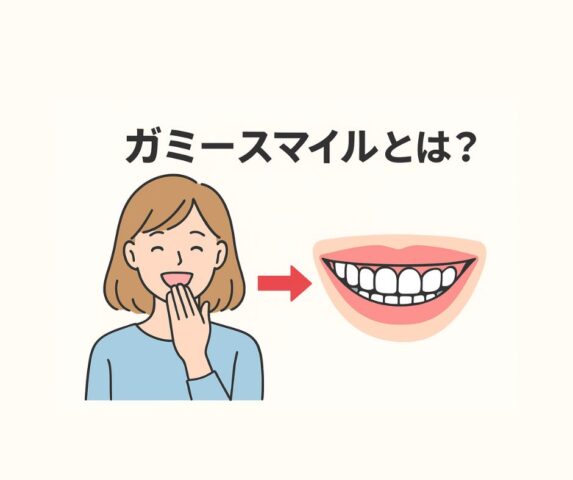- 「子どもの歯並びが気になるけど、できれば歯を抜きたくない」
- 「ワイヤー矯正は見た目が目立つし、痛みも強そうで心配」
このように感じる保護者の方は多いのではないでしょうか。床矯正(しょうきょうせい)は、お子さまの顎の成長を利用して、将来永久歯が並ぶスペースを確保する治療法です。取り外し式の装置を用いるため、生活への負担が比較的少ないのが魅力です。
ここでは、床矯正の特徴やメリット・デメリット、注意、治療の流れについて解説します。
関連記事はこちら
床矯正とは?3つの特徴
床矯正(しょうきょうせい)とは、子どものあごの骨の成長を利用して歯並びを整える矯正方法の一つです。
取り外し可能な「床装置(しょうそうち)」というプレート型の器具を口の中に入れて、ねじやバネの力で少しずつ歯を動かしたり、あごを広げたりしてスペースを作ります。
床矯正の主な特徴は以下の3つです。
- 取り外し式の装置を使用する
- 適応年齢がある
- 適応できる・できない歯並びがある
①取り外し式の装置を使用する
床矯正では、自分で自由に取り外しができるプレート状の装置を使います。入れ歯によく似た形で中央には特殊なネジが埋め込まれています。
保護者の方や本人がネジを定期的に回すことで、装置が少しずつ左右に拡大します。その力が顎の骨に伝わり、歯列の幅が広がります。ワイヤーを直接歯に固定する矯正法とは違い、自分で着脱できる点が特徴です。
②適応年齢がある
床矯正は、顎の成長を利用するため、効果が現れやすい年齢に限りがあります。
治療を始めるのに適しているのは「顎の骨が柔らかく成長が活発な時期」です。具体的な対象年齢は6〜12歳ごろであり、乳歯と永久歯が混在する混合歯列期と呼ばれる時期です。
この時期に始めることで成長力を活かし、永久歯がきれいに並ぶスペースを確保しやすくなります。一方、大人は顎の骨の成長が止まっているため、骨格そのものを広げることは困難です。
ただし、歯をわずかに動かしたり、他の矯正治療後の「後戻り」を防ぐ目的で装置が応用される場合もあります。子どもと大人では床矯正の目的が異なる点を理解しておくことが大切です。
③適応できる・できない歯並びがある
床矯正は万能ではなく、すべての歯並びに適応できるわけではありません。顎の骨を広げることで改善できる歯並びに有効性を発揮します。床矯正が適応しやすい歯並びは以下の場合です。
- 叢生(そうせい):顎が小さく、歯がきれいに並びきれずに重なっている状態
- 軽度の出っ歯:上顎が狭く前歯が突出してる状態
- 受け口:下の歯が前に出ている状態
一方で、骨格的な問題や、歯の移動量が大きくなる場合は、床矯正での治療は難しいです。床矯正での治療または床矯正だけの治療が難しい歯並びは以下のケースです。
- 骨格のズレが大きい歯並び(重度の出っ歯や受け口)
- 抜歯が必要とされる重度の叢生
- 歯のねじれや傾きが複雑
顎の適切な発育は、鼻呼吸のしやすさや気道の広さの確保など、全身の健康に影響を与える可能性があります。お子さまの歯並びが床矯正の対象かどうかは、精密な検査と診断に基づき、総合的に判断する必要があります。
床矯正のメリット
床矯正は身体への負担を抑えながら、治療ができる利点があります。床矯正が持つメリットは以下の4つです。
- 抜歯を回避できる可能性がある
- 装着の着脱が自由にできる
- 痛みや違和感が少ない
- 虫歯リスクを抑えやすい
①抜歯を回避できる可能性がある
床矯正は、永久歯を抜かずに並ぶスペース確保の可能性を高められます。ワイヤー矯正では、歯のスペースを作るために、健康な永久歯を抜歯する場合があります。一方、床矯正は歯を動かすだけでなく、顎の骨の成長をサポートし、歯の土台である骨そのものを広げるアプローチを取ります。
近年の矯正治療の研究でも、顎の幅を広げる重要性が示されています。(※1)床矯正はこの考え方に基づき、抜歯せず歯並びを整えることを目指す治療法です。
②装置の着脱が自由にできる
床矯正で用いる装置は自分で取り外しができる「可撤式(かてつしき)」です。24時間装置をつけて過ごす固定式とは異なり、以下のように生活の場面に応じて柔軟に対応できるのが利点です。
| 場面 | メリット |
|---|---|
| 食事 | 硬いものや粘着性のあるものも食べられる |
| 歯磨き | 装置を外し隅々まで磨ける |
| 運動や写真撮影など特別な場面 | スポーツや写真撮影など外したい時に外せる |
自分のライフスタイルに対応できるため、ストレスを大きく軽減できます。
③痛みや違和感が少ない
床矯正は他の矯正方法と比較して、治療に伴う痛みや違和感が少ないとされる治療法です。ワイヤー矯正は、歯に強めの力を直接かけて動かします。
一方、床矯正は顎の骨全体をゆっくりと広げる治療法です。歯そのものを無理に動かさないため、歯根や周囲の組織への負担が少なく、強い痛みを感じにくいです。
ただし、装置を使い始めた直後や調整後の数日間は、歯が押されるような圧迫感があります。軽い痛みや違和感を覚えることもありますが、多くの場合、数日で自然に慣れていきます。
④虫歯・歯周病リスクを抑えやすい
床矯正は衛生管理がしやすく、虫歯・歯周病のリスクを抑えることが可能です。ワイヤーを固定する方法では、装置の周りや歯と歯の間に食べかすが溜まりやすくなることに加え、歯磨きが難しくなります。
しかし、床矯正では装置が外せるため歯磨きがしやすく、装置自体も簡単に掃除ができるので衛生的です。磨き残しがでやすい小さなお子さまにとって、保護者が仕上げ磨きをしてあげられることもメリットです。
床矯正のデメリット
床矯正には注意が必要なデメリットも存在します。主なデメリットは以下の3つです。
- 装着時間の自己管理が必須
- 治療時期に制約がある
- 後戻りのリスクがある
①装着時間の自己管理が必須
床矯正の治療を左右する重要な要素は装着時間を守れるかどうかに尽きます。装着時間は1日12〜14時間以上が推奨されます。(※2)装着時間を守れないと、計画通りに顎が広がらず、治療効果が不十分になる可能性があります。
長時間の装着が必要なのは、骨や歯を動かすためと、後戻りを防ぐためです。弱い力でも持続的にかかることで骨や歯は少しずつ動いていきますが、装置を外している時間が長いと歯は元の位置に戻ろうとします。
そのため、安定した効果を得るには、長時間の装着が重要で、食事と歯磨き以外の時間常に装着しておくと最大の効果が得られます。
②治療時期に制約がある
床矯正は始めるタイミングによって効果に大きな差が出ます。特に効果が期待できるのは、顎の骨がまだ柔らかく変化しやすい成長期(6〜12歳ごろ)です。
上顎は左右二つの骨からできていて、その二つが真ん中で合わさっている部分を「正中口蓋縫合(せいちゅうこうがいほうごう)」と呼びます。完全に骨化していないこの時期は、正中口蓋縫合が左右に拡大しやすいため、床矯正を始めるのが有効です。装置で少しずつ力を加えることで縫合部が広がり、将来の永久歯が並ぶためのスペースを作ることができます。
成長が終わった後では縫合部が固まるため、同じ方法では十分な効果を得ることが難しくなります。
③後戻りのリスクがある
矯正治療で動かした歯は、その直後は骨や組織が安定せず、元の位置に戻ろうとする「後戻り」のリスクがあります。床矯正で歯並びがきれいになっても、治療が完全に終わったわけではありません。
床矯正特有の問題ではなく、ワイヤー矯正やマウスピース矯正を含め、すべての矯正治療に共通する課題です。後戻りが起こる主な原因は以下のとおりです。
- 歯や骨が元の位置を記憶している
- 舌で前歯を押す癖や口呼吸などの癖
- 親知らずの影響による圧迫
後戻りを防ぐために、治療後は保定装置(リテーナー)を一定期間使用する必要があります。歯をその位置に固定する役割を果たす、リテーナーの使用までが矯正治療の一環です。
床矯正における注意点
床矯正は患者さんご本人と、支えるご家族、歯科医師がチームとなる必要がある治療法です。床矯正の注意点として、以下の3つを解説します。
- 装着時間を守る
- ワイヤーの破損に気をつける
- 定期的に装置をお手入れをする
①装着時間を守る
推奨される装着時間は、1日12〜14時間以上です。装着時間を守れないと治療が長引いたり、十分な効果が得られなかったりする可能性が高まります。
「学校から帰ったらすぐに装着する」など、生活のルーティンに組み込む工夫をしながら、装着時間を確保する必要があります。
②ワイヤーの破損に気をつける
床矯正で用いる装置は、オーダーメイドの医療機器です。ネジやワイヤーが組み込まれており、繊細な構造をしています。そのため、強い力が加わると変形したり、ワイヤーが折れたりする場合があります。
装置の破損は、治療の中断だけでなく、口の中を傷つける原因にもなります。以下のような原因で破損するので注意しましょう。
- 硬い食品や粘着性のある食品を装置をつけたまま食べる
- 取り外す際に指や爪でワイヤーを引っ張ってしまう
- 歯ぎしりや食いしばり
- 顔への強い衝撃(スポーツなど)
装置の破損や変形があった場合は、自分で直そうとせず、使用を中止して速やかにかかりつけの歯科医院に連絡をしてください。
③定期的に装置のお手入れをする
床矯正の装置は毎日使うので清潔に保つことが重要です。口内は、常に細菌が存在するため、お手入れを怠ると装置に歯垢が付着し、細菌が繁殖して虫歯や歯肉炎、口臭の直接的な原因になります。
基本的な手入れ方法の流れは以下のとおりです。
- 1.装置を外したら水で洗い流す
- 2.柔らかい歯ブラシで磨く(歯磨き粉は使用不可)
- 3.週に数回は専用の洗浄剤を使用する
- 4.外している間は専用ケースに保管する
熱いお湯で洗浄すると装置が変形する恐れがあるため、水かぬるま湯を使用してください。正しいお手入れを習慣にして治療を続けましょう。
床矯正の治療の流れ

初回相談から治療完了までの一般的な流れは以下のとおりです。
- 初回カウンセリング
- 精密検査・診断
- 治療計画の説明と同意
- 装置の作成・装着
- 定期的な調整
- 治療完了・保定期間
①初回カウンセリング
患者さんやご家族が抱えている歯並びの悩みや、治療に対するご希望、不安などをお伺いします。そのうえで、床矯正の治療法やメリット・デメリット、期間や費用について説明します。
②精密検査・診断
口の中の状態を検査します。治療計画を作るために重要です。検査内容を以下の表にまとめています。
| 検査内容 | 目的 |
|---|---|
| レントゲン撮影 | 顎の形や大きさ・永久歯の位置を確認 |
| 口や顔の写真撮影 | 歯並びや顔とのバランスを記録 |
| 歯の型取り | オーダーメイド装置の設計 |
| 虫歯・歯周病チェック | 健康な口腔環境で治療を始めるため |
③治療計画のご説明と同意
治療は十分な説明と同意を得てから始まります。まず患者さんに合わせた治療計画を立てます。内容は治療の方法や期間、費用、想定されるリスクなどです。これらを丁寧に説明し、ご理解とご納得をいただいたうえで治療を進めます。
④装置の作成・装着
装置はオーダーメイドで作成します。歯型をもとに、一人ひとりに合わせた床矯正装置を製作します。完成後はお口に装着し、正しい使い方を確認します。ネジの回し方や日々のお手入れ方法も丁寧に指導します。
⑤定期的な調整
床矯正では定期的な通院が欠かせません。およそ1〜2か月に1回の来院が必要です。通院時には次のような対応を行います。
- 口の中の状態を確認
- 顎の成長に合わせて装置を調整
- 治療の進行状況を評価
このサイクルを繰り返すことで、計画通りに治療を進めることができます。
⑥治療完了・保定期間へ
歯並びが整い、顎の成長が安定したら、床矯正装置による治療は完了です。治療後は歯が元の位置に戻るのを防ぐため、リテーナーを使う期間に移ります。この段階まで進めば、きれいな歯並びを安定して保つことができます。
床矯正の治療期間・費用の目安
治療期間や費用は、顎や歯の状態によって異なります。治療計画が完全なオーダーメイドで作成されるためです。ここでは、床矯正の「治療期間と通院頻度」「費用の内訳」を解説します。
治療期間と通院頻度
床矯正の治療期間は、顎の骨の成長を促す「第一期治療」と、歯並びを安定させる「保定期間」に分けて考えます。内容は以下の表にまとめています。
| 項目 | 目安期間 | 内容 | 通院頻度 |
|---|---|---|---|
| 第一期治療 | 1〜3年 | 顎の成長を促し永久歯が並ぶスペースを確保 | 月1回程度 |
| 保定期間 | 1〜3年 | リテーナーを使用し後戻りを防ぐ | 2〜3か月に1回程度 |
定期的な通院と適切な装置の使用を続けることで、将来にわたって安定した歯並びを守ることができます。
費用の内訳
床矯正は自由診療のため、費用は全額自己負担となり、クリニックにより料金設定が異なります。治療にかかる費用の総額は、お口の状態や治療範囲によって変動しますが、20〜50万円程度が一般的な目安です。
費用の主な内訳を以下の表にまとめています。
| 項目 | 目安金額 | 内容 |
|---|---|---|
| カウンセリング料 | 無料〜約5,000円 | 悩みや治療概要の説明 |
| 検査・診断料 | 約3〜5万円 | レントゲン・歯の型取りなど |
| 装置代 | 約15〜30万円 | 片顎か両顎かで変動 |
| 調整料 | 約3,000〜1万円/回 | 通院ごとの調整・観察 |
| 保定装置代 | 約3〜6万円 | 後戻りを防ぐリテーナー |
矯正治療は医療費控除の対象になる場合があります。詳しくは、お住まいの地域を管轄する税務署にご確認ください。
まとめ
床矯正は、歯を抜かないといけなくなる可能性を減らし、痛みも少なく、生活への負担を抑えながら歯並びを整えられる治療法です。しかし、効果を引き出すために1日12〜14時間以上の装着時間を守るご本人の意思と、ご家族のサポートが欠かせません。
特に効果が期待できるのは、顎の成長が活発な6〜12歳ごろ、乳歯と永久歯が混在する混合歯列期です。お子さまの歯並びで少しでも気になることがあれば、まずは専門の歯科医師に相談しましょう。
参考文献
- Jamilian A, Jamloo H, Majidi K, Zarezadeh M.The Impact of Mini-Screws and Micro-Implants on Orthodontic Clinical Outcomes: An Umbrella Meta-Analysis.Clin Exp Dent Res,2025,11,5,e70220.
- Emad Eddin Alzoubi, Simon Camilleri, Mohammed Al Muzian, Nikolai Attard. The effect of tooth borne versus skeletally anchored Alt-RAMEC protocol in early treatment of Class III malocclusion: a single-centre randomized clinical trial. Eur J Orthod, 2023, 45(5), p.517-527.