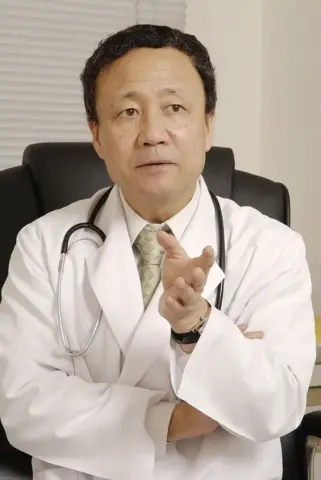目次
はじめに
空前の健康ブームと言われる今日でも、私たちが意外に見落としがちなこと。それは、人の身体は毎日取っている食事の栄養素からできているということです。そのため、たとえ体調不良になったり、検査値が悪かったりしても、食生活を見直すことで以前の健康な状態に戻すことは可能なのです。
今回ご登場いただいたのは、2025年に77歳となるイシハラクリニック院長の石原結實先生。今日までほとんど病気知らずで、老眼もなくメタボとも無縁の健康体を誇り、365日休みなく診察・講演・執筆・メディア対応をこなす。石原先生が自ら長年実践して効果を上げている「食事の取り方」「健康習慣」などを紹介してもらいました。
健康を維持し、若々しさを保つために毎日の生活にぜひ取り入れてください。
Q1 身体を老けさせない食べ物、食べ方について教えてください。
アンチエイジングの食べ物や食べ方がいろいろと雑誌やテレビなどで取りざたされていますが、私は基本的には好きなものを食べ、好きなものを飲んで、大いに結構だと考えています。それでも元気に長生きできるでしょう。
ただし、重要ことが2つあります。それは「食べ過ぎない=少食」と「断食」です。「少食」と「断食」が身体を老けさせず、健康維持に役立つことは、科学的に証明されています。
Q2 具体的に教えてください。
たとえば、米国のマサチューセッツ工科大学生物学のレオナルド・ギャラン教授は、24歳前後の寿命を持つサルを「食料をたくさん与えるグループ」と「腹六分目程度の食料を与えるグループ」に分けて20年間飼い続けました。すると、「食料をたくさん与えるグループ」のサルは頭髪が抜け、シワだらけの顔になり、「腹六分目程度の食料を与えるグループ」のサルは頭髪がフサフサで、顔のシワが少なく、CTで見た脳は萎縮などの老化現象が見られませんでした。
また、アメリカ国立老化研究所のマーク・マットソン博士は、マウスを3つのグループに分けて実験しました。それは、A=好きなだけ食べさせる、B=摂取カロリーを60%に抑える、C=一日おきに食べさせて翌日は断食する、です。すると、Cグループが一番健康で、寿命が長く、老化による脳の損傷がありませんでした。
スペインの養老院では、1,800キロカロリーの食事を毎日与えたグループと、1,800キロカロリーの食事を食べた次の日は断食したグループを比べています。すると、後者の老人たちが圧倒的に長生きしたのです。
Q3 単に「少食」を続けるだけでなく、時に断食を取り入れる方がいいということでしょうか?

そうです。様々な動物実験の結果を総合すると、腹十二分、腹十分(普通の量)、腹六分では、腹十二分が最も短命で、腹六分が最も長寿です。しかしさらに見ると、腹六分より、腹十二分と断食を1日おきに繰り返しているほうがより長生きなのです。
先に紹介した米マサチューセッツ工科大学生物学部のレオナルド・ギャラン教授は、人体60兆個の細胞内にはサーチュイン遺伝子、別名長寿遺伝子が存在し、これは病気を防ぎ、健康に長生きさせる働きを持っているのですが、飢餓状態になると活性化し、老化を遅らせ、寿命を延ばす働きをする、と研究結果を踏まえて話しています。
また、米エール大学のトーマス・ホーバス博士は、「空腹時に胃からグレリンという飢餓ホルモンが分泌されて、海馬の領域の血行をよくして、脳の働きをよくする」と述べています。
Q4 腹六分を続けるのは、あまりにストイックすぎて現実的ではないように思います。
その通り。腹八分、腹六分の生活を毎日、問題なく送れる人はその通りにすればいいですが、社会生活を送っていれば難しいですし、生きる楽しみがありませんよね。それは、私も理解できます。
私がオススメしているのは、時には友人や家族らとの会食で存分に食べ、飲み、しかし時々は断食で空腹の時間を過ごす方法です。
実際、私自身がそういった生活を20代の頃からずっと送っているのです。食事は1日1回、夕食だけ。運動も、少食・断食と同様に、健康維持には欠かせません。私は毎日ウエイトトレーニングと10キロのジョギングをしています。みなさん、継続的な運動は、食事と同様に大事ですよ。
この生活で、50年間一切病気知らず。76歳にして、メタボリックシンドロームとは無縁で、余分なぜい肉はなく、老眼もありません。テレビ出演、講演、出張、研究などで、国内はもちろん世界のあちこちにしょっちゅう出かけていますが、疲労感など覚えたことがないのです。
Q5 どういう食事をしているのですか?お酒はやはり飲みませんか?
朝はジューサーで作る人参とリンゴの生ジュース、昼は黒糖とすりおろし生姜を入れた紅茶。
人参やリンゴは、血管の酸化、つまり老化を防ぐ抗酸化物質が豊富です。黒糖とすりおろし生姜は、体を温める作用に優れています。
生活状態と白血球の関係について調べると、入浴後と運動後に白血球の機能が増強することが明らか。共通しているのは体温の上昇です。加えて、食品、衣類などで体を温めて体温が上がると、白血球の殺菌力や貪食力が促進されるのです。1度体温が低下すれば免疫力が30%低下する、言い換えれば体温を上げれば免疫力も上がることも報告されています。そのため、私は朝と昼は抗酸化物質や体を温める作用のある食品を飲み物で取っているのです。
そして夜は好きなものを食べます。といっても、私は肉を食べず、魚もほとんどがダメ。魚介類ではエビ、タコ、イカを食べるだけです。たとえば昨夜は、エビのてんぷら、イカの煮物、納豆、味噌汁、ご飯1膳。お酒はほぼ毎晩飲んでおり、ビールや日本酒、焼酎などです。量が過剰にならなければ、お酒も飲んで構いません。
私が少食、断食、運動を勧めるのは、研究で実証されていること、科学的な根拠があることに加え、自身の経験に裏付けされているからです。もともと私は虚弱体質でした。特に胃腸が弱く、頻繁に下痢を繰り返していました。大学に入り、民間療法を知り、実践してみると体の調子がいい。その後、健康長寿食の大家の先生方との出会いがあり、現在の食事法や運動を取り入れるようになったのです。
Q6 身体の老化を遅らせるために、積極的に摂取したほうがいい食材や栄養素はありますか?
まずは、抗酸化物質や身体を温める食品。さらに、昔から「血管とともに人は老いる」と言われているように、血管を若々しく保つ食材を意識して取るといいでしょう。
動脈硬化を防ぐ食べ物としては、タウリンが豊富なエビやイカ、悪玉コレステロールを貪食するマクロファージの働きを促進する硫化アリル。これは、玉ネギなどに豊富です。血液をサラサラにする納豆キナーゼが取れる納豆。動脈硬化を防ぐ不飽和脂肪酸がたっぷりのゴマ。
塩分と水分を排泄する食べ物を取れば、血管を老いらせる高血圧対策になります。スイカ、キュウリ、レモン、緑茶や紅茶がいいでしょう。
ストレスも「若さ維持」の大敵。シソ、生姜、セロリ、レタス、ハッカなどのそれぞれに含まれる成分には、ストレスに対抗するのに必要な働きを期待できます。
人間は、下半身を温め、強くしてくれる食材を取ると、血圧が下がり身体の老いを遅らせます。これまで紹介した食材と重複するものもありますが、人参、ゴボウ、ヤマイモ、玉ネギ、生姜がよいですよ。
Q7 運動はどのようなものがお勧めですか?これまで運動習慣がない人でもできるものを教えてください
それなら、ウォーキングが一番でしょう。ウォーキングをすると、下肢をめぐる血液の量は安静時の10倍以上になり、血圧が下がります。これは下半身の筋肉運動の即時的効果。足腰の弱りは老化、生命力の低下と完全に比例するので、継続的にウォーキングをし、下半身の筋肉運動を行うことで、足腰の弱りを防げます。
ポイントは、速く歩くこと。アメリカ老人病学会会報には、「患者の体調がよくなって歩行速度が速くなると、死の危険は反比例して低下する」という論文が過去に掲載されました。ピッツバーグ医大のステファニー・ストゥデンスキー博士が、高齢者500人の日常生活の歩行速度を測定して、9年後に同じ人たちの健康状態を調べると、歩くスピードが速かった人ほど、9年後の死亡率が低かったのです。
速く歩くほどエネルギー消費量が多くなり、血流がよくなって血管が柔らかくなります。人は血管とともに老いると申し上げましたが、血管の若さをウォーキングが保ち、身体全体の若さも保てるのです。
Q8 先生の美学を教えてください
人生で一番大切なことは、相手のことを想うこと。自分の考えよりも他人の考えを優先にする「利他主義」を信条にしています。そのために、謙虚、親切、努力、忍耐、継続、義理、人情。これらを大切にしているのです。
この記事を監修した医師
-
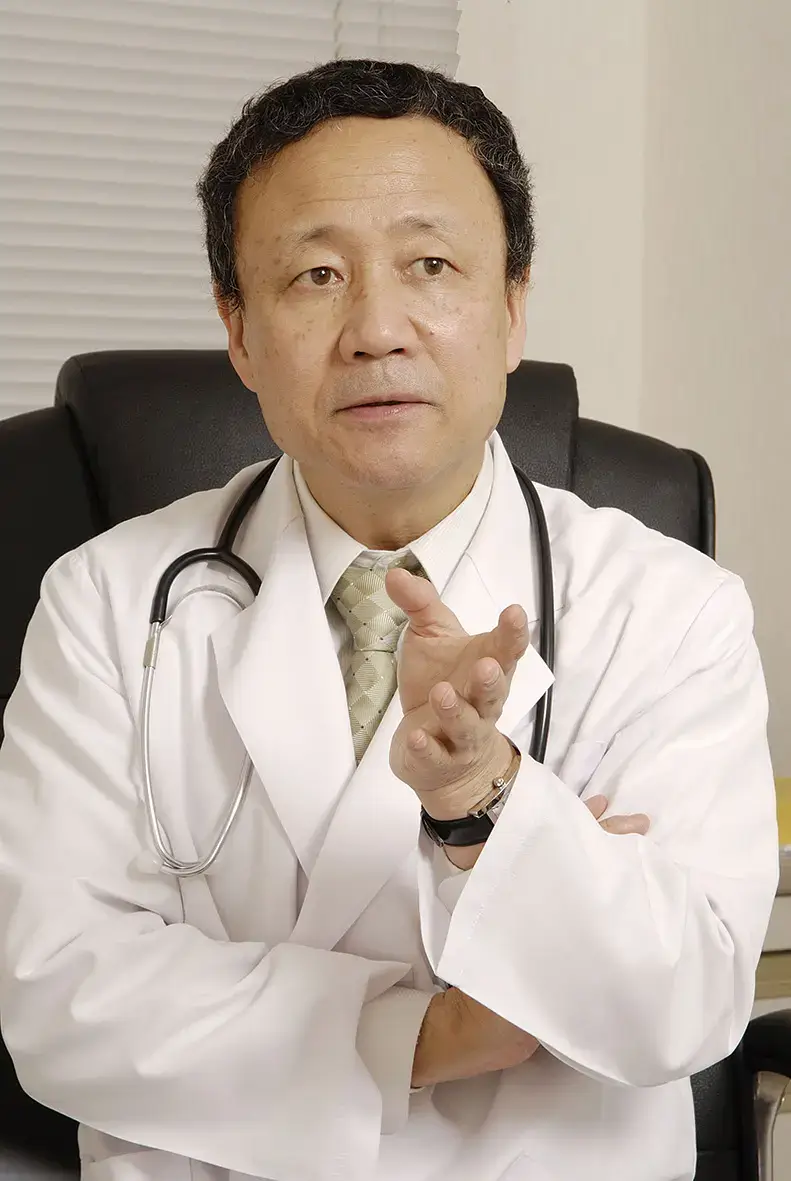
医学博士/ジョージア共和国科学アカデミー長寿医学名誉会員
石原 結實
1948年長崎市生まれ。先祖は種子島藩の御殿医。長崎大学医学部卒業、同大学院博士課程修了。幼少時より虚弱でよく発熱し、高校時代は慢性の下痢で悩まされた。大学に入り「西式健康法」に出会い、青汁(キャベツジュース)で改善。二木謙三博士(東大医学部内科教授)や森下敬一博士(お茶ノ水クリニック院長)の著書に感銘を受けて玄米食を始め、諸症状が完治。ウェイト・トレーニングも始めて、更に体調が向上。こうした経験が自然医療を目指すきっかけになる。 コーカサス地方の長寿村やスイスの自然療法病院で自然療法を研究。ヒポクラティック・サナトリウム所長を務める傍ら、東京のイシハラクリニックで漢方処方を中心とした治療を行う。これまで、生姜紅茶・ニンジンジュース・少食・身体温めなど独自の健康法を「おもいッきりテレビ」はじめ各メディアで発信。著書は1979年の『病気はかならず治る』(善本社)の処女出版以来、350冊以上。ベストセラーになった『生姜力』『体を温めると病気は必ず治る』『医者いらずの食べ物事典』他、10万冊以上のベストセラーが11冊。米国、ロシア、ドイツ、フランス、中国、韓国、台湾、タイ、インドネシアなどで計100冊以上が翻訳出版されている。自身の提唱する超小食生活(朝は人参ジュース、昼は生姜紅茶、夜は和食)を続けながら、年間365日休みなく診察・講演・執筆・メディア対応を行う。 その合間に週5日、1日に約10kmのジョギング、週2回のウェイトトレーニングを習慣とし、「運動」「少食」を実践している。2023年に医師生活50年の集大成である「石原医学大全」(青春出版社)を上梓。